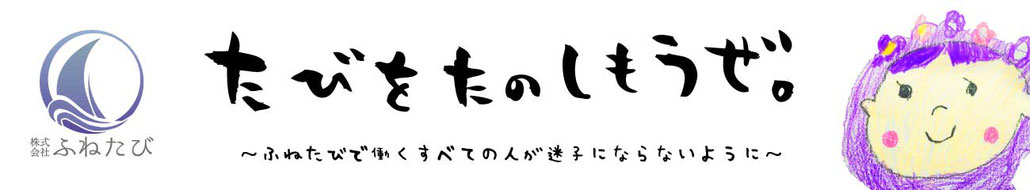ゴールド・スタンダード
宮本法子
【6・7月課題図書】
前書きにある“ノーという語彙はない”。最後に“質の高いサービスが時代を超えて求められること。プロとしてのサービスをいかに提供すべきかを理解していこと”の言葉に、どうしたらその土台に一歩一歩近づくことができるのか、以前の図書と同様、なぞ解きのように読み進めることのできた図書でした。
見えてきた答えは、課題図書として与えられたすべてに共通する“クレド”です。極限すればビジネスの本質は外交術の一言につきる=自己を理解できなければ相手を見ることはできない。何のために他者を知るのか。仕事をする楽しみは進歩的な改革に参加できること=変化を好み成長が喜びであること。お客様を家族と考える、そしてもう1つの我が家を超えるもの=ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式。他多数の答えに現在の取り組み、そして足跡が着実に未来に繋がっているように感じました。
組織は永続性を担保することも社会的責任の1つであり、地域に根差し感謝する企業にも通じます。今、自身がここで取り組んでいることは小さくても消えない足跡を残せる取り組みであるのか。見据える先は小さくても消えない足跡を想像する行動を取れているのか。信用を信頼に変え、尊敬に変える取り組みはできているのか。課題は山積ですが、マズローの5第欲求説になぞらえた、信用を信頼に変え、さらに尊敬に変える取り組みに、自己の力を発信するエンパワーメントが明るく見えたようで改めて未来が輝きました。同時に、なすの斎場でしか聞くことのできない語彙がかすかですが見えてきました。
与えられた教育の中で頂く知識はそれだけでは無力です。知識が行動になって初めて力になる。大切な教育の機会を無駄にすることなく、力に変える学びを今後も継続していきます。毎回気づきを下さる図書と、その機会を与えて下さる社長には感謝します。
相馬親太郎
なすの斎場グループ
【6.7月 読書感想文】
成功には柱がある。
根底として、時代と共にどんなに変化が起こり、それに対して自分がどんなに変化しても、柱、芯となるものがしっかりあってこそ。響きます。それが自社の『ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式』と捉えながら読みましたが、自分自身、変化に対応しようとし過ぎてブレてはいけないなと感じました。
今回の図書は、普段、勤務しているときに耳に入る言葉が、実例として書かれており、『こういうことだったんだ!』と、実際の出来事と擦り合わせすることができました。
【サービスの3つのステップ】も、やっているけど、自分のやり方がお客様に響いているのか振り返り、これもシンプルな言葉ですが、実践しようとするとかなり深いと感じます。
【ワオ体験】も、多感覚でないと難しいですし、【気付き】のレベルの高さがサービス業には必須ですが、そこを高めていきたいなと思いながら読み進めておりました。
最後の大阪の理髪店のストーリーも、奥さん美容師って運じゃん!って思ってしまいましたが、6章の【他人の長所に目を向ける】をなるほどと思いながら読んでいたのにさっそく、ラストで否定してしまいましたが、最後の最後までハッとさせられました。
事例も多く、すぐに独創的になれずとも、事例を参考に一歩ずつ始めていければ必ずたどり着けると思いました。
【人のためになる】そんな仕事がしたくて就職活動をしていた学生時代を思いだし、私もしっかりと足跡を遺せるように現状維持せずにがんばっていきたいと思います。
田中 勝
なすの斎場グループ
【6.7月 読書感想文】
ゴールドスタンダードを読ませていただきました。
しっかりした土台なしに質の高い仕事をする事ができない。ゴールドスタンダードの規律があったからこそしっかりした土台ができた。この文章がすごく心に響き、尚且つ、我々の仕事にも言える事だと感じました。
サービスの3ステップ
こちらも、我々にとって必要な内容だと思います。
CRMから始まり、プランナー&ディレクターとバトンが渡されます。心を込めて意識したいです。
金の鉱脈を探そう
未来どうするべきか?先読みがどれだけ大事かが勉強になりました。
伸ばす事と成功すること
従業員が業績向上に貢献してくれる事を信じている
やはり全ての答えは数字にありと、思いました。
全て、従業員のポテンシャルを高めたり、スキルアップにつなげるような内容でした。とても読みやすく考えに共感を持てました。現在なすの斎場で実施している内容に近いと思いました。
人を育てる側、教わる側共に考え方を変え、ティール組織を目指す必要があると改めて思いました。
管理職も現場訪問してますか?するべきだと感じました。
1
飯島芳美(解約済)
【6・7課題図書】
部門を超えたサービス内容・紳士淑女の姿勢に感心しました
実例とともにホテルを利用するお客様一人一人にストーリーがあり又その時のお客様の心情や体調の変化を察知し従業員が同じ目線・立場に立ち心配りで痒いところに手が届くおもてなしのサービスにプロフェッショナルを感じました 「それはわたしの仕事ではありません」ノーとは言わないお客様の立場を考えた真心のサービス 幸福 創造 感謝そして僕のおばあちゃんにしてあげたかったお葬式…自分の身内なら…と考えてのサービスになすの斎場のクレドが重なりました お客様へのサービスも創意工夫をして心に残る感情面でのつながりを作るワオ体験のサービス提供 大阪のワオストーリーの「プロポーズプラン」成功率100%はさすがです 様々な例が従業員のあらゆる角度から考えられていてその質の高さとブランドを維持するサービスに圧巻 顧客情報管理の共有上手くラインナップが活用されていると思いました 細かなところまで行き届く従業員 新入社員の教育指導 素晴らしいホスピタリティでした お葬儀の現場でも紳士淑女を見習いどんな時でもお客様に寄り添い対応行動できるように日々努力をしたいと思いました
1
村上絢美
なすの斎場グループ
【6.7月読書感想】
こちらの本、とても読むのが大変でした。なんだか文字が小さい気がして眠さが増しましたがなんとか読み終わりました。
クレドとは…ラテン語で『私は信じる』本にも書いてありましたがたしかにぴったりだと思いました。
信頼がもたらすもの…信じることは質の高いサービスを生み出す結果につながる。私もスペシャルを使わせていただき、そして金額も1万円までとのことで購入しておりますが、実際にお渡しして、少しでも思い出として残れば嬉しいなと思います。
第一印象は一度だけ…もちろん初めて会う際の第一印象は大切です。が、その際ワオ体験の提供することが大切。例文としてあること、とても素晴らしいと思いました。こういった行動ができるようになればとてもすごいなと思います。
1
平山 智美
なすの斎場グループ
読書感想文
お客様に関する情報を、ホテル全体で共有していて、その情報を集めるだけでなく活用することが大切…なすの斎場のイベントに参加したお客様の個人のちょっとした情報を共有することにより、ワオの手掛かりになるのではないかと思いました。
『お客様に喜んでもらう時代』は終わりそれ以上のことが期待されている。なすのスタンダードの『ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式』自分の身内ならと考え行動することにより、満足を超える…お客様の頭と心に訴えるようなサービスの提供ができるようにまず、お客様のお名前を覚えたりお客様に関心を持つことから始めていきたいと思いました。
1
月井 優二
なすの斎場グループ
6・7月課題図書
ヒアリングスキルが向上するとお客様の期待値も上がる、現場で言うとスペシャルの為のヒアリングが不発に終わると満足度が下がる。薬が欲しいお客様はなぜ薬が欲しいのか? 体調がすぐれないから、当たり前だがここをすぐに考えて次の行動ができるか、薬を渡して終わりではない。15時チェックインで朝8時にきたお客様に「お部屋の準備が整っていなくて申し訳ございません」と言える姿勢。自分が考えるお客様目線を超えていました。
いまなすの斎場で行なっている朝礼・ラインナップの理由を自分の価値で感じる事ができました。
1
宮本法子
なすの斎場グループ
【8月課題図書】
大変なことに宮本の一番苦手とする漫画(自分の中では絵本とは全く種類が異なります)が今月の課題図書でした。期限に間に合わないと焦り文面を構成し、脚本のような形でイメージを作ったところ、予想外に読破することのできた図書でした。
同じ葬儀はないのと同様に、1人の人が歩む人生に同じは決してありません。明るい人柄だから明るい過去しかない、抑え目な人柄だから暗い過去がある訳でもない、そんな当たり前のこと思い返しました。言葉にできない葛藤や、今抑えなければいけない気持ち、そして口に出してしまったら泡のように消え去ってしまうのでないだろうかという不安。あの時我慢したことが仇になったのかと自分責める気持ち。そんなことはないだろうにと感じる自分は、人の気持ちに寄り添えていないのか。答えのない答えに、応えきれないこと。他者を理解するには足りない何かを感じ、同時に虚しさも残る図書でした。
葬儀は断絶感が謙虚に表出されるが故に、グリーフの重要な場面と捉えられることは一般的ではあります。しかしながら、人生の中での断絶感(=グリーフ)は歩んだ人生の数だけあると言われるのも事実です。個人の人生を点ではなく線、そして広い面で捉えることの重要性を再確認すると同時に、“グリーフケアのはじまりを”をどう捉えるのかの必要性を痛感しました。
死生観を問われるような図書でもありましたが、個人的には目に見えない人の心を扱う職業において、葬儀社として必要な視点と捉え方、そんな気づきを与えられたように思います。いつもなくてはならない気づきを下さる図書と社長には感謝します。気づきを現場で活かせる何かを見つけます。
1
赤羽根奈央子
なすの斎場グループ
読書感想文
はじめにのところで裏方で働く人たちと話がしたかったとあり、読み進めていくと、離職数が少ないとありました。お客様ももちろん大事ですが、そこに働く紳士淑女を大事にされていてその大事にされた紳士淑女たちはお客様を大事にするとつながっているのだと思いました。
コミュニケーションが何よりも大切とありました。スタッフ同士のコミュニケーションがしっかりしていればワオな体験につながるとも思いました。
1
宮内 佐知江
なすの斎場グループ
6・7課題図書
クレド:お客様をおもてなしする姿勢を示したものです。これが私たちの仕事であり、目的です。リッツカールトンのすべての従業員がこのクレドを目的としクレドに誓ったサービスを行っているからこそ、リッツカールトンが同じ業界から基準にされる理由なのだろうと思いました。第3章の適合性を高めるというなかで、当社のサービスは時代遅れではないか...の疑問に対して今の時代さまざまなお客様がいて世界各国に展開しているからこそ、その変化に応えていかなければならない、お客様や地域とともに成長しなければなりませんという文を読みなすの斎場のクレドで考えると、地域に根差し感謝される企業として各地域にある、なすの斎場の会館に置き換えて考えてみたところ、会館がある地域に合わせ変化して成長に繋げていかなければならないし、従来のお客様、新規のお客様のニーズに応えられるよう日々変化していかなければならないと感じました。そしていつの日かリッツカールトンのように存在だけで地域社会を強化できたらとても素晴らしいと思い、変化と伝統を両方大切にしている部分を見習っていきたいと思います。
8月課題図書
最初手にしたとき、題名と絵を見て内容が全然想像できませんでした。読んでみたら内容は重いはずなのになぜか笑えてあっという間に読み終わってしまいました。ただ、主人公を自分に置き換えたら自分ならあんな風にサラッと現実を受け流せなしきっと落ち込で日々の生活を送ることはできないだろうと思ったし、残り時間のカウントをしていくのはツライだろうと考えさせられました。もし主人公のような状況の人が近く現れたら自分は、上手く言葉をかけられるだろうか、一緒に日々を過ごしていけるだろうかや、お客様として考えご家族へのグリーフケアをどのようにすれば良いかなど読み終えたあと漫画自体は面白いけど、色々考えさせられる内容はいい意味で重く感じました。
1
渡邊勇二
なすの斎場グループ
6月7月読書感想文
高いサービスを提供する為に行っているサービスの3ステップは意識の問題なのですぐに取り組めるものです。お客様をお名前で呼ぶと言う部分は自分自身、最近特に意識していて、反応もすぐ出るのでした。
問題が起こってしまった時の対処は迅速に対応する事。現場を信頼して権限を与えているからこそできる事だと思いました。
逆に今の時代あっという間に悪い情報も広まってしまう。迅速さ+そこにもワォ体験を提供して満足に持っていく事も可能になる。いかなる時でもお客様に喜んでもらいたい、弊社で言う自分の身内ならと言う考えはブレてはいけないと思いました。
ページのまとめの金の鉱脈を探そうは疑問文で問い掛けている。リッツカールトンの考えを重んじてるからこそ、その問い掛けに大丈夫と思えたり、ハッとしたりしました。振り返りのツールになりそうです。
1
相馬 なつみ
なすの斎場グループ
6・7月課題図書
お客様が言葉にしたニーズも、言葉にしないニーズも見つけなければならず、そのためには3つのC(収集、蓄積、伝達)を実行することが必要だと知りました。
現代のお客様は適切なサービスだけでなく、期待を超える価値や心遣いや楽しさなど非常に高い満足感やワクワク感を求めていることを知りました。商品そのものが持つ魅力ではなく、お客様の頭と心に訴えるようなサービスの提供によって「ワオ」が生まれます。「ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式」という理念を常に考えながら、まずは、ワオ体験を作り出すチャンスに気づけるようになりたいと思いました。
1
高橋清志
なすの斎場グループ
【6.7月読書感想文】
毎朝のラインナップの大切さ、社員全員がクレドを理解し同じ意識を共有できること。
これが実践できるかできないかでは業務の質が格段に違う。
リッツカールトンの社員は皆お客様と同じ紳士淑女であれ、
自分がその会社の一員であることを誇りに思えるような職場であったらいいなと思わせられるような非常に良い文面だと思いました。
そうなることで安心してお客様が望むサービスも提供できることができるし、自分たちの自信にもつながっていくのではないかと感じ取れました。
数あるゴールド・スタンダードがありましたがどれも会社が今後成長、進化していくためにはかかせない素晴らしいものが記されていました。
自身興味を示した項目がいくつもありましたが書き出すと切りがなくなってしまうので、実践できる事がありましたらどんどん実践出来ればいいなと思います。
当社もより良いサービスをお客様に提供していくためにはもっとエンパワーメントが根付いていけばいいなと感じます。
1
大金久美子
なすの斎場グループ
6・7月課題図書
これどけ読み応えのある本の中で一番記憶に残ったところ
サービスの3ステップ(1.あたたかい、心からのごあいさつを。2.お客様をお名前でお呼びします。一人一人のお客様のニーズを先読みし、おこたえします。3.感じの良いお見送りを。さようならのあいさつは心をこめて。お客様のお名前をそえます。)
これは、なすの斎場でも全社員が取り組め、予算のかからないことなので全社員でこれを取り組み、その他自社に取組め真似するべきところは実践していこうと思いました。
このサービスの3ステップから基本の徹底、価値の向上など一人一人がお客様へ期待を超えたサービスをお届けすることへつながっていて、社員を人間として尊重し、常に向上心がある信頼関係クレドにあがあるからこそ、自社の価値観を社員みんなでインプットして会社全体が常に進化し続けていると考えました。
ラインナップについても忙しいときだからこそ、大変な時だからこそラインナップを数回行うなどラインナップの重要性を再確認できました。
一度読んだだけではすべては頭に入らないけれど、素晴らしい内容がたくさん書かれていたので時間がある時に何度も読み直そうと思います。
1
藤田 裕子
なすの斎場グループ
【課題図書感想文】
紳士淑女がどっち忙しい時こそのラインナップ。お客様への名前でのお声掛け。部署間の壁を除き、お客様にワオ体験を提供する、お客様にあったサービスの実行。実行するには私達従業員一人一人の連携。ホテルでのサービスはコミュニケーションが1番。『すぐになんとかします。』この、言葉はなかなか言えない言葉かと思います。自分達が何をすべきなのかお客様への、おもてなしの、基準をみんなが共有する。期待を超える事が出来たからこそ『ワオ体験』につながるのだと思いましす。葬儀社とホテル業は、一見繋がらないようにも思いますが、心地よい時間を過ごしていただく為の基本は同じだと思いました。5つの定義を守り続ける事が、難しいと考えず私たちのクレドにそったものを大切に、しようと思いました。葬儀社として、紳士淑女としてお客様の心に残る思い出を作り上げるため ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式をお手伝いできるように今以上に頑張らなくてはとかんじました。
1
高橋 真人
なすの斎場グループ
(7月課題図書感想)
なすの斎場のクレドの土台となる部分や、こんな時・こんなお客様にはどのように対応するべきかということがたくさんちりばめられて勉強にもなりました。電話対応でいつもの対応に少しだけ+αで質問をするだけでお客様のことを知ることができたり、飲みすぎたお客様へのドアマンの対応などは、「細やかなことの積み重ねが大切」という教訓になりました。
「トイレにペーパータオルの切れ端が落ちていたら必ず全従業員が、必ず拾う」ということを実践できているかというと、なかなかここまで自信をもって言い切れないと思います。ただそうしたほうがいい・そうすべきだと知っているのと知らないとでは大きな違いになってくるので、今回読んだこのゴールドスタンダードをもとに、日ごろの習慣を少しずつでも変えていきます。
1
櫻井 裕子
なすの斎場グループ
【課題図書感想】
サービスの質、お客様への対応に問題があると感じた時に、従業員にまず話を聞き問題がどこにあるのかを探して改善していく。従業員に対して敬意を持って接するなど、業種に関係なく共通する部分、クレドの基盤となる事など挙げればキリがないほどヒントがたくさんありました。全てはお客様の為に、記憶に残るサービスが何なのか、お客様が必要としている事、物は何なのか意識していこうと思います。
1
寺門 大輔
なすの斎場グループ
【7月課題図書】
今回の本の中で特に印象に残ったことは、「問題への対応」の姿勢の点でした
著書では、「問題・クレーム発生」におけるポイントを「問題発生の際のレスポンス」「発生の理由の洗い出し」に2点に大別し、分析している点が大変に参考になった
「問題発生の際のレスポンス」を大切さは、自身が葬儀においてクレーム案件を出した際に強く体感しており、この著書を読むことで、改めてその際に感じた手ごたえを、肯定されたような印象を受けた
理屈では頭でわかっていても、心情的に怒り心頭のお客様のところにすぐに出向くというのは抵抗があるが、「お客様のため」という勇気をもって向き合うべきである、と本に背中を押されたように感じた
また、問題発生時の対処だけでなく、「発生の理由の洗い出し」に重点を置いているのは、自身にとっては新しい視点だった 特に、自身のクレーム案件の際は報告書を書き、反省をすることで再発を防ぐことができるが、他者のミスを共有する、という部分が抜け落ちていることを自覚した
こういった点のためにイントラにクレーム報告書がアップされているので、改めて再確認すべきだと感じた
また、こういった観点の全てが「お客様のため」という「ゴールド・スタンダード」に繋がっていることは、ある意味で清々しさを感じた また、こういった下地の整備こそが、全社で方向性を合わせるためには不可欠だとも強く実感する機会を得ることが出来たと思う
1
栗田祐里
なすの斎場グループ
【6、7月課題図書感想文】
お客様が口に出さないニーズを先取りすることが最終目標。お客様によって異なるニーズをそれぞれのお客様が望むやり方で満たすと書き出された7章により引き込まれました。対お客様と面と向かうことが少ないCRMに所属している私にマークが書いたメールのような内容がかけるのか・・・と。この先1年離れる現場で皆さんと同じように何ができるか顧客情報を最大限に活用し細部まで配慮したサービスやワオ体験など、ひとつでも多くお客様が望むやり方で満足いく結果を出したいと復帰へのワクワクが止まりませんでした。
1
3
1
4
星 大地
なすの斎場グループ
課題図書
葬儀でもありがちな、堅苦しい、または単調な~~というものをサービスの質を変えることでお客様のニーズに答える。
という言葉が凄く刺さりました。
お客様が心の底で臨んでいる見送り方、故人様のご遺志を汲み取り具現化して心残りの無い葬儀がスタンダードでできる葬儀社を考えると凄く良いなと感じます。
第一印象は一度だけ。弊社でいうと月井さんがそんなことを今にも言いそうですが、本当にそうだなと今は感じます。
リッツカールトンでは家を出る前から旅行とありますが、私たちも亡くなる前から葬儀ははじまっているのかもしれません。
マーケティングから事前相談、その他全員の業績、それを決める段階から葬儀は恥じ合っていると考えると気が引き締まります。
1
竹中紗智
なすの斎場グループ
【6.7月読書感想文】
今まで多数受けたセミナーや研修、なすの斎場で知ったクレドという言葉。その総復習の様に感じた内容でした。クレドが自身に浸透し、こんな会社なんだよと外部の人間に話した時、『会社の理念って、一種の宗教だよね』といった知人の言葉が脳裏によぎりました。ザ・リッツカールトン・ベーシックにあった内容は、接客業に勤務する上で・経営する上で当たり前の内容だと感じました。個人個人の『普通こうだよね?』というのは誰目線での考えなのか。求められるのはお客様を第一に考え、高品質のサービス。その『普通』とはどこを指すのか。しばし考えさせられました。この本を読んで、今後生かしたい点としては、同じつむぎでも矢板のつむぎはこういったコンセプトがあるなど各会館の味があるとよりお客様から見て矢板のつむぎと覚えてもらえるのではないと思います。矢板を盛り上げる上でも、再度読み込んで形にしようと思います。
1
渡辺悟
なすの斎場グループ
課題図書
かなり分厚い本ですがリッツ・カールトンの事例などをがたくさん書いてあるのですごく読みやすかったです。
なすの斎場にもクレドがあり
リッツ・カールトンのクレドでは【紳士淑女をおもてなしする我々もまた紳士淑女である】と書かれていて、身だしなみなどを気にして、お客様の対応を考えさせられる本でした。
企業として、情報の共有、気持ちの共有、向上心と言うところがリッツ・カールトンにはあるなーっと考えさせられました