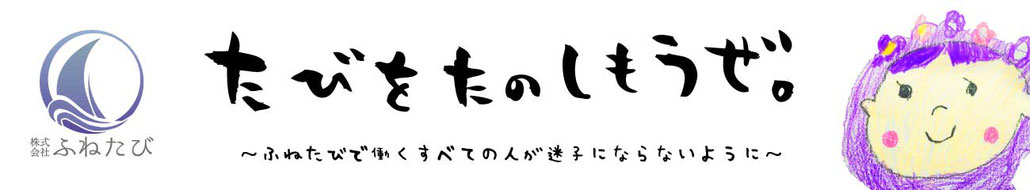the team 5つの法則
宮本法子
なすの斎場グループ
【5月課題図書】
3か月続いたシリーズ編から一遍新たな課題図書。冒頭より国語ではなく算数、足し算と引き算の方程式はおろか掛け算や割り算も知らない~文面に特段理数系が大の苦手の宮本にとっては内容についていけるか不安を持ちつつも、分かりやすい説明のお陰で読み進めることができた図書でした。
落としどころとして深く心揺さぶられたのは”理解してから理解される“でした。こちらは図書として読んだことはありませんが、自身の基礎となる”アイムOKユーOK“に繋がる面を感じ取れ、点ではなく面でみることの大切さを再確認することができました。また、1つ1つの方程式に自分はどれに当てはまる?を考える以前に、他者にチェックされるのを待つのでは自身で発信していくことの必要性を理解できました。
要所要所に出てくる心理学、経済用語など前職で深く学びを得たつもりが、継続して活かせる知識しか意味あるものにならないことを再確認しました。カラーバス効果、社会的手抜き、集団浅慮、集団凝集性、同調バイアス、ファーストチェス理論などなど…。気づきは成長への足掛かりになります。
投げかけれらた方程式はポジティブに方向転換させられた今回の図書。抽象のハシゴ理論に匹敵するような感覚に、着地点はクレドの理解と落とし込みなるのかと個人的に感じました。理数系は苦手な宮本ですが、感覚だけも感じ取れたことは大きな成長です。いつも気づきを下さる図書とその場を与えてくれる社長にはただただ感謝です。いつもありがとうございます。
宮内 佐知江
なすの斎場グループ
5月課題図書感想
今回の本は前回の本から打って変わってまさにビジネス本って感じではありましたが読み続けていくうちに、なるほどと感じる事ばかりでした。
ルール設定の4つのポイントとしてあげられていた内容で「ルールはできる限り少ない方が良い」「チーム内の責任範囲は明確な方が良い」ルールは多い方が良い、チーム内の責任範囲は曖昧が良いや一般的とは反対だあっても良いことと、チーム内のコミュニケーションは簡素な方が良い、その真逆でチーム内のコミュニケーションに無駄があっても良いなど本来とは真逆な事が効果的だったり、ごく当たり前のルールと思っていた事が状況によってはその真逆もありなのだと勉強になりました。会社員、社会人として一般的な考え方が主流と思い込んでいた部分が違っていたと感じさせられました。他にコミュニケーションのことで経験、感覚、志向、能力を理解する必要があるとの事なのでそれらの事を踏まえて伝えることを意識していこうと思いました。
飯島芳美(解約済)
【5月読書感想文】
チームとグループの違い 共通の目的を持ち目標の設定と達成に向けて編成がある事 チームの人員選定の意義がスポーツに例えられている事で納得が出来る分かり易さでした 合わせて男子バレーボールチームの監督の話を思い出しました カッコいい選手のお陰でバレーボールの盛り上りを吹替えし人気を持ち返す事が出来た しかしオリンピックではメダルを勝ち取るとゆう目標に向けてかっこいい選手ではなく勿論強い選手が必要だと仰ってました 目標に向けての言葉でメンバーのモチベーションをあげる事又女子バレーボールの実例も有りましたが相互理解を深める為費やした無駄のない時間の使い方そしてチームには多様性・均質性がありそれぞれチームの目標に合った人材を集める事が大切である事チームには1人1人役割りがあり(適材適所)目標達成の為に人選が不可欠である事 1人1人が大切なメンバーである事又意思疎通の法則の中のモチベーションタイプの4つの分類とポータブルスキルで相手を知るコミュニケーションの大切さを興味深く読ませて頂きました
1人1人がクレドに添いより良いチームを目指し又最強のチームをつくりあげる事を様々なチームの法則を通して学ぶ事が出来ました
平山 智美
なすの斎場グループ
読書感想文
共通の目的がない集団はチームではなくグループ。共通目的…目標を適切に設定することが大切。数値を定めるだけでなく、『意義目標』をしっかり考えることがとても大切なんだと思いました。私が印象に残った一言ですが、『意思決定者は反対や孤独を恐れずに1人で決めよ。しかし、メンバーは意思決定者を孤独にするな』意思決定までにはコミュニケーションが大切で気持ちの行き違いであったり、感覚や考え方の違い人数が増えればそれぞれあると思いまが、お互いが理解するコミュニケーション・安心して意見を言える場つくりのコミュニケーションができる環境目指していきたいと思いました。
赤羽根奈央子
なすの斎場グループ
5月の課題図書
読み進めていて、自分のチームはどこに当てはまるのか?柔道団体戦型かな?など考えながら読んでいて今、施行チームもCRMチームも生花商品管理チーム固定されたメンバーでたまにシャッフルしたらまた新しいアイデアがでておもしろいのではないかと思いました。実際にはメンバーシャッフルは難しいかと思うのであるチームのミーティングに別のチームメンバーが参加するなどするのもいいと思いました。
モチベーション第5章のところでもチームに何に共感してもらうか?魅力を感じる仕組みがあるか?など考えてさせられ業績OKRにあったら楽しそうだと思いました。
高橋清志
なすの斎場グループ
5月読書感想文
THEチームを読み終えて
チームであることの意味、ただ人がいるだけ、各々が特に目標を意識することもなく動いていたのではそれはチームとは呼ばずただのグループである。
冒頭よりなぜかものすごくインパクトのあるフレーズから始まりました今回の書籍ですが
なぜかすごく心に響きました。
チーム内に置いて絶対的に権限を持つ人も必ず必要ではないという事、目標を立てて進んで行く上で皆が同じ技量や同じ志向を持つこともない、切磋琢磨することももちろん素晴らしく大事なことですが、コミュニケーションをしっかり行い、互いを理解し適材適所に対応していけることがチームにおける最高のパフォーマンスを発揮できる環境ではないかと考えました。
素晴らしいスタッフが当社にはたくさんいると思います。そんな中で自分居場所である商品管理部ですがこちらでもどこにも負けないチーム作りができると確信しています。
今月も素晴らしい読書ができました。
田中 勝
なすの斎場グループ
5月の課題図書
ザ・チーム 5つの法則を読んで
色々参考になる部分がありました。チームの行動目標というより意義目標を設定する。読んでいてなるほどな理解しました。そして目標を確実に達成するのが良いチーム、目標を適切に設定するのが良いチーム、より力を注ぐべきだと勉強になりました。
一番興味がある内容として、サッカー日本代表南アフリカワールドカップベスト16
ベスト16位に導いた岡田監督のお話の中で、チームの雰囲気がすごく悪かった。その中で6つの指針をたてたとありますが、新たな意義目標・成果目標・行動目標を設定した事によりチームの活性化、結果ベスト16位となりました。Aimの法則でチームパフォーマンスが最大化した結果と言える。
積極的に意見を出し合えるチームはとても素晴らしいと改めて感じました。
この本を通してチームの法則を当てはめて考える必要があると思いました。
櫻井 裕子
なすの斎場グループ
【5月課題図書】
題名からして興味をそそられる本でした。自分のチームはサッカーチームかな?柔道チームかな?など考えながら読みました。
相手を理解してから理解される、相手の特徴を知らなければコミュニケーションは成立しない、などグサっとくる言葉も多く自分の役目は何なのか、社内の役割とお客様に対しての役割など両立できるよう勉強しながら役割を果たしていきたいと思いました。
星 大地
なすの斎場グループ
課題図書
自分で驚いたことは、これまでで一番入ってこないというか、、なんとなく苦手な本でした。
題名からして凄いそそったのですが、なにやら例えが多く自由度が少なく感じました。
ただ、サッカーのお話もありましたがチームの内部からパワーが伝わり、周囲に伝染していくようなチームはやはり強いのだなと感じました。
相手を理解する、というよりは相手を肯定し理解する努力から始めたいと思います。
村上絢美
なすの斎場グループ
5月読書感想
あれ?難しい??と思いながら読み進めていましたが何度か読み理解ができました。ただ理解するのに時間はかかりましたがグループとチームの違いや目標の振り分けをする。
また、いいコミュニケーションを短く簡潔に→相手を理解する、あっ。なるほど!と思いました。
やはり同じ目標があると行動の仕方が違うのは分かっていました。私自身クレドに沿って自分の身内なら…と思いながらお葬式のお手伝いをしていきたいと改めて思いました。
そして、意思決定。意見を出して、多数決を取りチームのリーダーが決定する。難しかったですが勉強になりました。
栗田祐里
なすの斎場グループ
【5月課題図書感想文】
先月までとは変わり難しいかなと思いながらも、途中でスポーツでの例が挙げられていたり、挿絵のように簡単な図や説明が入っていたり、章ごとに最後にまとめが書かれていたりしたので、分かりやすく次は何のことが書かれるのか楽しみながら読み進めることが出来ました。どの仕事においてもコミュニケーションをまったく取らないということはないので、その取り方を自分たちはどのタイプになるか意識することがさらに効率的になると感じたことと、これを実践しないわけにはいかないと強く思いました。また、意思決定をするのが苦手な私には意思決定の項目も強く印象に残りました。リーダーやチーム長に任せるのではなく強い・速い意思決定を心掛け、チームにとって最適な方向へ導けるように影響を出していきたいです。
渡邊勇二
なすの斎場グループ
5月の課題図書
4つのスポーツに例えたチームの特徴は非常に分かりやすかったです。弊社においては野球型なのかなと思ったり、他のタイプにも当てはまるなと思うところもあり、色々な側面を持った業種だと思いました。
心理的安全のところでは色々な不安から意見する事を辞めると言う話がありました。1つのアイディアが物事を大きく変える可能性を持っていると思うので、意見を言いやすい雰囲気を作る事はすごく大切な事だと思います。
チームが崩壊する落とし穴、割り算のパフォーマンスは少しの甘えでいつでも落ちる可能性があるので気をつけていかないといけない所だと思います。場合によってはチーム全員が落ちる事もあると思います。
相馬 なつみ
なすの斎場グループ
5月課題図書
4月まではお客様に対してのお話しでしたが、今月はチームのお話しでした。
まず、チームが4タイプに別れる事を知りました。そして、チームのタイプによってのルール作りの設定のポイントものっていました。まずは、自分のチームがどのタイプに当てはまるのだろうと思いました。
目標設定について、意義目標これはOKRでした。目標設定は他に、成果目標MBOをきちんと定量的に設定することや、行動目標=振り返り評価とこの3つの目標をきちんと理解する事が大切だと知りました。
藤田 裕子
なすの斎場グループ
【5月課題図書感想文】
名前の通り チームの法則?がたくさんのっていて 自分に当てはめると納得できるものがありました。チームの構成を変え進んでいくスポーツの話。ルールよりコミュニケーションにより臨機応変さを大切にし連携をとる。アイディアを殺してしまう言葉も、どうせこれだったしなど 頭の中で言い訳し進まなかった自分がいる事も気づきになりました。チームに必要なことの自分の理解が違っていたので 良いチームつくりをするうえで自分のタイプを見極めこれからの取り組み方を変えてみようと思わされました。リーダーは反発を恐れない事。メンバーを導く。必要な時の意思決定。なかなか言い出せないことも言わなければ伝わらない、否定的な話だけではなく ポジティブに23期下半期進もうと思えた本でした。
月井 優二
なすの斎場グループ
【5月課題図書感想文】
当たり前ですが改めて「チーム」に対して学べた事が多かった。知識がないからこそ自分の価値観や経験でしか伝えられていないなと実感しました。環境を整える、特性を理解する。整備やルールを守る事なら私でもできる!いや、やる!イメージ湧きました。
高橋 真人
なすの斎場グループ
5月読書感想
難しい話と、それをわかりやすく伝えるために映画の話やスポーツの話、AKB48の話など馴染みのある題材を使ってくれていて、難しいながらも読み進めやすかったです。
特に印象的なのは3章の部分で、今時分が悩んでいることについて書かれていたのでとても勉強になりました。「コミュニケーションには無駄があってもいい」ということを肝に銘じながら周りと連携していきたいと思います。
後ここにも1on1のことが書いてあり、うちの会社はすでにやってるなと少し嬉しくなりました。
そして終わりに、にあるように、組織づくりは誰がするのか、自分がするのだという意識がより強くなりました。まず自分から、意識してやっていきたいと思います!
大金久美子
なすの斎場グループ
5月課題図書感想文
目標を確実に達成するチームが良いチームだと思われがちだが、本来大事なのは目標を適切に設定することである。
今月はちょうど上期の業績面談など、目標やチームのことを考えることが多かった分読みやすかったです。
共通目的のない集団はちーむではなくグループ。チーム作りに絶対解はない。あるのは最適解。最高の空間をつくれ。進むべき道を示せ。力を出しきれ。
コミュニケーションやルール、意思決定など勉強になりました。
意義目標をチームメンバーが意識し自発的に成果をあげれる最適な方向に行けるチームを目指します。
竹中紗智
なすの斎場グループ
【5月課題図書】
題名はそそられる題名なのですが、正直・・・チームというのと、このタイプのビジネス本は個人的に苦手なジャンルでありました。読んでいてちんぷんかんぷんになり、ネットにパワポの資料を見つけたので照らし合わせながら読み進めました。一番しっくりと来たことはエンゲージメントの4Pについて。(理念方針)(活動成長)(人材風土)(待遇特権)、ただ全てをメンバーに与える事は難しい為、メンバーの嗜好を踏まえて、この4つの中から1つを高める為の戦略的に決めていく必要がある。リーダーに見つけてもらう必要というより、自身でもどれに当てはまり、高めていく必要があるのか・・・チームといえど集まるメンバーの素質も目標によって変わってくる、海外ドラマのクリミナルマインドFBI行動分析課を思い出しました。1つのチームに選抜されるにしても、自身の強みについて改めて気付き、理解する必要があると感じました。今月もありがとうございました。
相馬親太郎
なすの斎場グループ
5月読書感想文
本書を読むにあたり、上期の業績や自チームでの自分のことを振り返りながら、読み進めました。
まず、目標設定の部分が未だあやふやなところがあったのですが、本書のように行動目標、成果目標、そして意義目標をあらためてしっかりと理解できました。
また、自分がやっていること、やらなくてはいけないことも、何型のチームなのかを考えながら読むことによって、下期はチームの一員としての役割を想像しながらも学ぶことができました。
自分が苦手なアイデアの創造についても、やはりネガティブな気持ちがアイデアを殺してしまうとの一文にハッとしてしまい、自分自身についてブレイクスルーしていかないとと感じました。
そして最後にモチベーション、エンゲージメントの4Pのところで、なすの斎場の4P【理念・方針】【活動・成長】【人材・風土】【待遇・特権】というものをしっかりと意識しながら、今後も取り組んでいきたいと思います。
最近、様々なことでわからないことが多い日々でしたが、日々の場面を振り返りながら読むことにより、あれはそういうことだったんだなと、感じることができ、素晴らしい一冊でした。
渡辺悟
なすの斎場グループ
5月読書感想文
遅くなりましたすいません!
マネージメントがタイプ別に別れていてすごく読みやすかったです
コミュニケーションのところで自ら相手の事を理解をするのが先で相手に理解してもらうのはその後。相手を知りたいのなら自分の事をオープンにして伝えると書いてありなるほどと思うようなことがたくさん書いてありすごく勉強になりました。
1
寺門 大輔
なすの斎場グループ
5月読書感想文
まず、チーム作りとしてもっとも大切な観点は「目標設定」ということを大きく掲げ、その中でのチームメンバーを統括するポイントを5つに分け、体系化しているところは非常に理解しやすかった。中でも、「Aimの法則」として目標設定の大切さを説いており、また「目標を全員で共有できているかどうか」という点がクローズアップされていたのが印象的だった
「A」のポイントはこれまでの課題書籍でも多く触れられており、新しい発見は少なかったが、
「E」のポイントはこれまで触れている書籍が少なく、非常に参考になった
特に、これまで「どの期間までに、このような目標を目指し、どういった成果を出すか」という点はチーム内ミーティングでも強く意識されていたが、「目標を達成したときに、どんな成果があるのか」という点は、見逃されがちだったのではないかと思った 本書ではチームメンバー全員が、それが金銭報酬や地位報酬だけでなく、理念や「やりがい」を源泉にもつことがなにより重要である、と解説されており、この点は今回の課題図書を読み進めるにあたって非常に大きな発見になった 「手段と目標をはき違えるな」というのはビジネスの格言とされるが、これまで自身の目標設定は、「手段をやることが目的」になってしまったのではないかと考えるきっかけになった
今後は「目標と、成果」へ、先のことをより分析すべきだと感じた