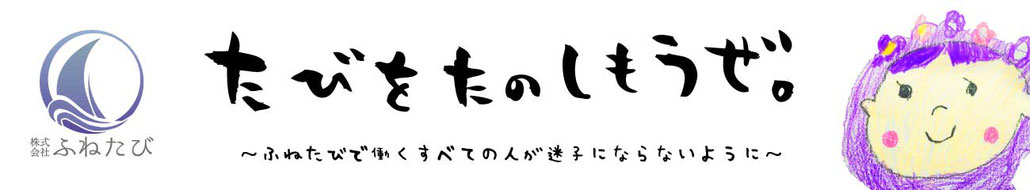リッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間
宮本法子
なすの斎場グループ
【12月課題図書】
12月の課題図書の変更が、さらに楽しみを倍増させた課題図書。後書きで「感性を磨くステージ」を実現するための努力を続けるとの文面に読む意欲が一層増す本でした。(宮本は後書きから入る癖があります)
全体的にサービスについての内容ではありますが、最高のホスピタリティの提供のための具体的な文章には、現在なすの斎場で取り組んでいる場面が要所要所に出、自身の仕事への取り組み方への反省に加え、来期の業績への意欲を突き動かされました。「サービスは科学だ」という文言には衝撃でしたが、仕事の枝葉として成長させたい“サービスは幸せの連鎖である”に繋がる面もあり安心して成長させていきたいと思いました。
自身が成長できる環境が整っている、だからこそその中でサービスの質を高めるための想像力を鍛え、適切な判断力と高いスキルを身につけていきます。心のサービスは無限大、その気持ちと言動が“お客様からの通信簿”に繋がる未来を描きます。
毎回貴重な機会を与えて下さる社長にはいつも感謝しています。頂いた価値を会社へ還元できるよう5%の自己投資を来年3月に実現します!
田中 勝
なすの斎場グループ
12月の図書
サービスを超える瞬間を読んで、感謝されながら成長できる仕事術から始まり第7章までがとても頭にすっと入る内容でした。機械的なトークではなく人情ある対応こそが顧客満足度につながるのでしょう。特に興味があった内容としまして
良いブランドはリピート率・紹介率が高い
どの企業でも会社のブランド力を高めて商品を販売する。そしておもてなしの精神
とても共感しました。ブランド力が高ければ、リピーターや口コミ宣伝も強化出来ます。この本を通して思ったのがやはり常に気持ちを初心にかえりブランド力強化、そして社員の教育を徹底する必要があると感じました。
最も素晴らしい対応としまして、(ノーとは言わない姿勢で対応する)
これは実際に体感することがあると思います。店によってはたらい回し等される事もありますが、やはりプロとして選択肢を考えてお客様に提案するという対応は素晴らしいです。なすの斎場でも同じシーンがある場合もありますが、ノーとは言わない対応を心掛けたいと思いました。
そしてお客様に尊敬される会社になろうと改めて思いました。
渡邊勇二
12月の図書
お客様ひとりひとりに対するサービスが素晴らしいと思いました。
葬儀社のお客様は必ずしもご遺族様だけではなく、参列者やセミナー参加者など多岐にわたると思います。
関わる時間が少ない方も沢山いるかもしれませんが、会館に来る全ての人に感謝される行動をとる事が必要だと感じました。
祭壇が素晴らしい、会館が綺麗などの視覚的な感動の他に人的サービスによる感動をごくわずかな時間で感じてもらえる言動が出来ればお客様がより増えていくと思います。
当家様がまた当社を選んでくれたり、参列者が後日会員入会をしてくれたりが、いかにホスピタリティの精神を持ち対応出来たかのバロメーターになると思います。
著書に書いてある通りまずは『マニュアル』ですが、マニュアル通り出来るようになった部分、場面からホスピタリティを意識していきます。
また、新人の感性を発揮するチャンスを与えると言う点では、まさにこの期間はもう戻れない時間です。業界のあれこれ、仕事のあれこれがわかる前にとメモ帳にこうしたらどうか、、、。というものを今の段階で30前後書き留めていましす。都度先輩方に質問してみたりはしてますが、今の感性は大切にしたいと思いました。
ホスピタリティマンの入口はいつも相手のことを考える事。実践していきます!
高橋清志
なすの斎場グループ
【12月読書感想文】
サービスを超える瞬間を読み終えて。今月もなすの斎場グループの社員であると言う事と
本の内容を重ね合わせて一気に読ませていただきました。クレドの大切さ、会社の一員であることの意識をいかに高く持つことができるか。非常に心に残る内容が書いてありました。
なすの斎場の経営理念であるお客様の立場になって考える(自分の身内なら)と考えて自分にはそんなことがお客様にして差し上げられるか。私は生花を通じてお客様に感動喜びを伝えてあげられたらいいなと考えました。
ブランディング力を上げるという項目がありましたが、それは当社においても実に通ずるものがありました、コースの高いお客様から火葬式のお客様まで当社にも様々なお客様がいらっしゃいますが、質を下げることなくすべてのお客様にすべての高品質のサービスをこれからもおこなっていけたらいいと考えました。
今月も素晴らしい読書ができました。
宮本法子
なすの斎場グループ
【1月課題図書】
前書きと後書きは短いですが面白いです、との社長のお言葉に、ワクワクしながらも、いつも通りに後書きから入りました。正直“面白さ”を実感できるほどの理解はできませんでしたが、“何かに突き動かされる”ような感覚で、一気に読み進めることが出来た本でした。
エンパワーメントについては、前職(福祉)での利用者支援の際に深く学んだことがありますが、あくまでも対象は他者であり“自身の解放”という意味合いは初めての受け止め方で衝撃でした。知ってはいる“つもり”は本当に怖いです、時代遅れと知識不足を痛感、と合わせて幾つになっても勉強することの大切さを学びました。
実践の過程は1つ1つ頷くより、これを実践したらこうなるのかという確認作業的なものになってしまいましたが、エンパワーメント実践の3つの鍵を実践したからこそ言える新たな鍵、“出発と方向づけの段階、変化と落胆の段階、適用と精緻化の段階”には未来がか輝くような感覚で、キャリアデザインと繋がっている感覚にワクワクさせられました。
教育は人を育てること、学習は自分を育てること。与えられた教育にとらわれずに自身の持っている力を自覚することと合わせ、何よりも自身が思い描く仕事への想いを発信することがクレドにも繋がるのではと感じました。いつも大切な想いに気づかせてくれる社長には感謝の想いです。自分の気持ちに鈍感な宮本ですが、これを機に敏感になれるように励みます!
高橋 真人
なすの斎場グループ
12月図書
まず私自身、この本に書いてあるような「こちらからお客様にこんなことを聞いていいものだろうか?」と思ってしまう日本人特有の感覚が先行してしまう方なので、そうではなくお客様のためを思うこそ声をかける、というのを実践していきたいと感じました。
そしてこちらもより考え直さなくてはと思ったのは「クレドを自分のものにしているか」ということ。内容を理解し、何度も読み返し、意味を知っていることと、それを自分の最も大切なものとして心の中心に置き行動に移せているか・・・100%それができているかというと、いないかもしれません。クレドをもっと自分の中に持っていられるようにしなければと改めて帯を締めなおす気持ちです。
そしてなにより合間合間で出てくるこんなおもてなしをして差し上げたというエピソードを見ていると、自分たちももっともっといろいろなことができるなぁと思えてきました。個人的にはもっともっと横のつながりを今以上に強化して、チーム全員でよりお客様に寄り添ったお手伝いができるようにしていきたいと思います!
星 大地
なすの斎場グループ
12月読書感想
おもてなしの究極形態だと感じました。
この本を読んで思うことはまず、先読みの重要度だと感じました、何気ない会話からも感謝されるための想像ができます。
リッツカールトンのクレドである【ゴールドスタンダード】が凄く自信に満ち溢れていると感じました。
弊社の理念、おばあちゃんにしてあげたかったお葬式。
誰が聞いても優しい雰囲気になる言葉だと思います、私たちもお客様が故人、親族、私たちとの感謝を紡いでいけるような葬儀を目指したいと思います。
下限品質の高い葬儀を共有して自分も周囲も巻き込んでいきたいです。
櫻井 裕子
なすの斎場グループ
12月読書感想
なすの斎場のクレドがリッツカールトンを参考にしているからか、共通点も多く同じサービス業として考えると仕事内容は違うけど、勉強になることばかりでした。クレドをよく理解し、クレドに立ち返れば何とかなると思うと、指針だけではなく支えになるものだと思いました。
藤田 勝文
なすの斎場グループ
12月読書感想
一見すると、クレドにそった素晴らしいサービス事例が盛りだくさんで、参考にしたいことや、共感できる内容だなぁと感じました。その中で、ところどころに出てくる「土台」というキーワードこそ、今の私たちにとって重要で、考え、見直すべきだと私は思います。当たり前に感じすぎて見過ごしてしまうこと・・・身嗜み、あいさつ、整理整頓、清掃・・・etcこの辺が均一に出来ている状態で、全社員がクレドに沿ったホスピタリティ溢れるサービスを提供できる葬儀社を目指します。
平山 智美
なすの斎場グループ
12月読書感想文
この本を読んでリッツ・カールトンに泊まってみたくなりました。
臨機応変に対応するスタッフ同士の価値観の共有ができていてすばらしいなと思いました。相手が何を求めているか、相手の幸せのためになにができるか…私も、生花の仕事で感動や笑顔をお客様にお届けできるようになりたいです。
リッツ・カールトンが大切にする「思いやりの心」仕事だけではなく、普段の人との接し方としてとても大切なことだとおもいました。
相馬親太郎
なすの斎場グループ
12月読書感想文
リッツカールトンが目指しているものとして、最上級のホテルの運営でなく、新しいライフスタイルの確立ということに主眼を置いている点がすごいなと感じました。
そのためのクレド。あらためてクレドの精神をしっかりと持ち、自分たちの使命をしっかりと果たし、感動を提供していけるようになりたいです。
特に自分では思いつかなかったこととしては、やり方次第ですが、お客様に手伝ってもらうことも大切だということは、実践していければと思います。
他にも参考になることが多かったので、この本も携帯していようと思いました。
以上です。
竹中紗智
なすの斎場グループ
【12月読書感想文】
接客業のアルバイトを始めた16歳の頃、よく職場の方に一流の接客を見た方が良いと言われた記憶があります。表情や立ち振る舞い、声のかけ方など、日常の中でお店に行った際よく見るようになり、自身も接客をする中でお金を投げて出す人・顔面にツバを吐いてくる人・電話で話しながらレジに来てこちらの問いかけに「あ゛?」としか返して来ない人など様々なお客様と出会いました。そんな中で、たかが接客でもされど接客業だと思い、ただのスタッフではなく名前を覚えて貰えるスタッフになろうと心に決めた時がありました。改めて一流の考え方を読ませて頂き、うんうんと共感できる所と目からウロコの視点や考え方がありました。そして、1人ではなし得ない、チームでのおもてなしというものは、会社として今後より良い物を提供するなら、なすの斎場ではクレドがあってこそだと思いました。今後はどこでもいつでも「なすの斎場のスタッフは、本当にいつ会っても気持ちいいわね」と言われていたいです。
関口将仁
なすの斎場グループ
メンバー「 渡辺悟」を追加しました。
渡辺悟」を追加しました。
渡辺悟
なすの斎場グループ
12月読書感想文
リッツ・カールトンでは一人一人のお客さまと話をし、気持ちを汲み取る事でお客様が求めているものを考えてそれを行動に移ししかもそれがマニュアル以上の提案やサービスで満足してもらえてこそがおもてなしと書いてありすごく勉強になると思いました。
葬儀社に置き換えて考えるとまだ打ち合わせなどは同行でしかやった事ないですが打ち合わせなどもお客様と話をして、お客様の気持ちを汲み取りなにをして欲しいのかなにをして欲しいのかなにが不安なのかを考えて打ち合わせができる人間になりたいです。
葬儀社では楽しむって言うことはあまりふさわしくない表現かもしれませんがお客様に喜んでいただくため、自分自身も楽しむって言う事を言っていてものすごく共感ができました。
お葬儀が終わるとご遺族の方がいいお葬式だったありがとねって言って帰るお客さまが多くて凄く嬉しく思います。
お葬儀の準備をしていてもお客様が喜んで帰ってもらうためにどんな業務もワクワクして取り組むことができます。全てのお葬儀同じものが無い100人お客様がいたら100通りのお葬儀があり100通りの想いがあるその思いを大切にしようと思う本でした。
宮内 佐知江
なすの斎場グループ
12月課題図書
数々のお客様への接客のエピソードを読み、何故リッツカールトンに高い宿泊料金を払って泊まりに行く方がいるのかが良く分かりました。お客様の要望に対して自分ができる最高のおもてなしとは何かをつねに考え実践されていることや電話対応時、オペレーターが顔が見えなくても笑顔で電話を取るためにPCの脇に鏡を置いて目の前にお客様がいるときと同じような笑顔で対応されてることなど、このようなおもてなしを実際に宿泊されて目の当たりで感じたら、また宿泊したいと思うだろうと感じました。クレドには奥深い意味があるという文章を読み、今以上になすの斎場のクレドの意味を理解していきたいと思いました。
藤田 裕子
なすの斎場グループ
12月読書感想文
リッツカールトンのこの本は今までで一番たのしく読めた本でした。サプライズだらけの内容でこんなことをされたらお客さまは一生忘れない。マニュアルではなく一人一人の心のおもてなし。会社が従業員を信頼し権利を与えている、そして従業員の声を拾ってくれる。いい人財が自分の心で考え、そこから感動を生む発想が出てくる。お客様に喜んでいただくためにお客様の温度を感じる。私もずっと接客業をしてきましたが こんなおもてなしがあるのか・・・というくらいの内容でした。悲しみの現場ですが 「良かった」「ありがとう」の言葉、ご遺族様の悲しみの時間、区切りの時間を共有させていただきながらこれからもなすの斎場の従業員として胸を張って仕事に励もうと思います。
月井 優二
なすの斎場グループ
12月課題図書
「ホテルの温度」という言葉が出てきましたが、肌で感じる温度ではなく、その空間のスタッフが出す雰囲気、活気、リラックス出来る空間の事を指します。初めて会った所なのに落ち着ける、初めて話す人なのに信頼できる気がする、きっと皆さん経験あると思います。会葬者の方や事前相談の方が式場に来た際にこの「温度」が感じられる空間を作りたいと思いました。
相馬 なつみ
なすの斎場グループ
12月読書感想文
この本は事例を載せたりしてとてもわかりやすく、そして読みやすかったです。
従業員1人1人が、マニュアルにそってではなく、マニュアルにはない、お客様が望んでいる以上のサービスを自然に行動出来ているというのが、とてもすごいと思いました。そして、チームを超えて協力が出来ているからここまでできるんだなと思いました。
大金久美子
なすの斎場グループ
12月課題図書
従業員も紳士淑女と定義し、お客様と同じ目線で積極的にコミュニケーションを取り、気軽に相談してもらえる存在になる。
従業員同士もお互いに、紳士淑女にお仕えする紳士淑女という目線で認識を共有しているという点。常に向上心を持ち、熱意を持って”楽しみながら”顧客を接客するからこそ素晴らしいサービスが出来るんだなと思う。
マニュアル化された業務と、スタッフの感性が発揮されたサービスとの絶妙なバランスが、リッツ・カールトンのサービスの強みだと思いました。感性を共有するスタッフのチームワークの良さからお客様の立場に立った感動が誕生してくることなどチームワークの大切さを改めて学んだ気がします。
こんな最高のホテルに一度は宿泊してみたいなと純粋に思いました。
藤田 裕子
なすの斎場グループ
村上さんの読書感想です。部屋に入ってなかったので私からチャットあげます。
12月読書感想文
この本を読んで思ったことはビジョンを持てば成功に結びつくということです。何も考えずにする行動と考えて動くことはもちろん違うのは分かってはいましたが意識をし知識を吸収しながら作業をするのはとても自分に役立つことしかありません。
そして今の自分には人生設計図を意識をしたりしていませんのでとても、心に響く文章でした。私も意識をしていきたいと思いました。
栗田祐里
なすの斎場グループ
12月読書感想文
どんなサービスを超える瞬間があるのか楽しみながら読み進めることができました。事例も多く、私だったら・・・と考える以上の内容が記載されており、やはりリッツカールトンで勤められいる方々は違うなとも思いましたが、日本にもまだ少し残っている認識のお客様は上の存在でサービススタッフは下から仕えるものというものではなく紳士淑女にお仕えする我々も紳士淑女であることと定義されていること、従業員にクレドが浸透仕切っていることが大きく関係するのだと感じクレドの大切さを改めて認識いたしました。また満足から感動→感謝のレベルを行えることでサービスを超えてお客様に愛されるブランドになる。サプライズやアフターフォロー等でお客様に感動や感謝を感じてもらい、葬儀社と言ったらなすの斎場だねと今以上に言ってもらえるようなそんな会社がスタッフみんなで作れたいいなと感じます。個人的に今年日光にリッツカールトンが出来たのでいつかは泊まってみたいなと思ってましたが、この本と出会えたことでどんなことが起こるのか体験しに行きたいなと強く思いました。
寺門 大輔
なすの斎場グループ
12月読書感想文
リピーター獲得のためのサイクル作りの点が非常に参考になった
お客様の満足度を不満ー満足ー感動ー感謝の4点にわかりやすく分割し、不満のお客様へは不満度を数値化し、分かりやすく目視できるようにして改善に努めている点は、いま現在なすの斎場には無い視点だと感じた
また、感動ー感謝のライン作りもまだまだ不明瞭ではないかとも感じる この著書では感動ー感謝のラインを「リピート・顧客呼び込み・ファン層化」として腑分けしているが、なすの斎場ではこPP会員という取り組みはあるものの、この「感動ー感謝」のラインがまだまだ定義化されておらず、不明瞭だと強く意識した
この本を経て思うことは、「不満層」を数値化することでここにいるお客様の底上げを図り、「感動ー感謝」を定義化することでファン層の獲得を強く意識することと感じた
また、気になった著書の中でフレーズで、「企業のブランドが高まれば高まるほど、顧客の期待度は高くなる」というものがあった
県北地域で、なすの斎場のブランドが高まれば高まるほど、お客様の要求する期待度も高くなっていく、と考えると襟を正すような気持ちになった