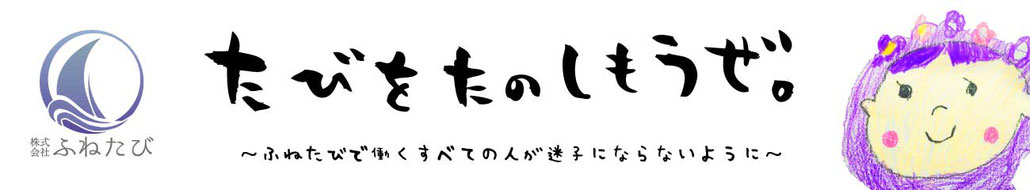宮本法子
昭和生まれの宮本にとっては、OKRという横文字のタイトルに違和感があり、中々手の付けられない図書ではありましたが、業績、仕事に直結するものと、気合を入れ読み進めた図書でした。
OKRに取り組む前に、自身の覚悟“組織の目的に自分の目的を重ねられるか”“共通の目的に共感できていないのであれば組織に属している理由はない”と、この組織にいることの意味などを再度考えさせられました。自身の立ち位置をしっかり見極めること、自立の重要性など入社してからのことを大きく振り返るきっかけにもなりました。
目標を見誤ると破滅に向かう。目的を明確にするとどうなるのか、抽象のハシゴ理論のような例題。フィードバックの手法には山本五十六の名言に似た文面。人を動かす三原則など、それぞれが、今まで読み進めてきた図書にリンクしており、改めて図書から学ぶことの多さに気づきました。
本気が無ければ達成もありません。会社の目的と自身のわくわく感が常に良いバランスを取れるよう、日々振り返りながら業務にあたっていきます。いつも大切な気づきをくださる図書と社長には感謝します。
松村千晴
「本気でゴールを達成したい人とチームのためのOKR」
組織の全員が同じ方向を向いてひとつの目標を達成するためにOKRが重要であると理解しました。
今日からすぐに行動するのは難しいですが、自分が成長できるための目標を設定したうえで日々の業務にあたっていこうと思いました。前職でも取り組んでいたフィードバック。フィードバックが成長にどのように重要かを学びました。
矢古宇隆之
本気でゴールを達成したい人と
チームのためのOKR 感想
「目的」と「重要な結果指標」という部分に着目しました。
「重要な結果指標」においては、目的と結びついていること、計測可能であること
容易ではないが達成可能な水準を目指すこと、重要なものに集中と書かれていますが、
目的に対する一気通貫な部分が感じられました。具体的な指針を立てなければ目標にはたどり着けないし、現状の判断力、目標への推進力、核となるものを見極める。目的に至るまでのプロセス論として成り立っています。実際の自分の経験に落とし込むと、目標は立てているものの、具体的ではない部分もありました。また、現状、推進力、核となるものを見極めきれなかったので、自営業を行っていた時に達成できなかったのだと感じました。
個人でもそれであるのに、会社組織の場合は共通の目的を持たなければなりません。
進むべき先がてんでバラバラにならないようにしなければならないからです。
戦場においても兵士がバラバラでは戦には勝てません。大将がいて、軍師、将軍、兵士などが共通した戦略をもって勝利に結びつくのです。会社でも27期のOKRを設定いたしましたが、挑戦的であるか、魅力的なものであるか、会社のクレドに沿ったものであるか、そこの所まで思いをはせてみました。自分はまだ兵士の部分であるので、兵士の目線から考えるOKR、リーダーになった際のOKRなど、その時々によって目標が変わってきます。どの段階でも、その時のOKRを引っ張り出しながら、その現状の時のOKRを追っかけた行ければと思いました。