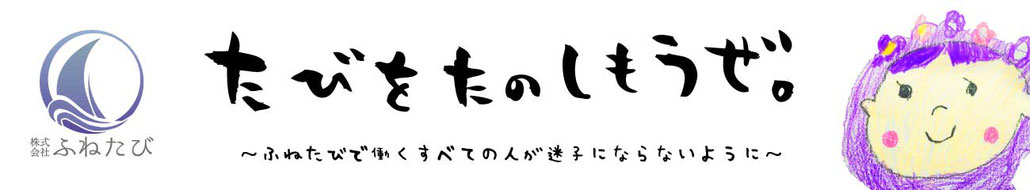末広がりのいい会社をつくる
高橋清志
なすの斎場グループ
11月読書感想文
末広がりの会社を作るを読み終えて、経営者の方がいかに良い会社を作るかの内容をよく示した内容の本でした。
弊社のクレドにも組み込まれている、業務の内容は違いますが地域に感謝される企業を目指して様々なボランティア活動を行ったり、社員がハッピーであるためにどのような環境を作って会社(仕事をする場所、環境)作っていくか本当によく書かれていました。
私も現在ずばり施設横紋やアレンジ教室などで多くと方と接する機会が多いのですがさらに喜んで頂き、なおかつそれをなすの斎場の為につなげていけるかもっと深く考えていこうと思いました。
コミュニケーションを作ることも仕事をしていくうえでとても大事なことである、それはどこの会社、生活の場所でも一緒であるという事ですね。
これが出来るかできないかでは生き方もだいぶ違ってくると思います、私はこれからも自ら進んでコミュニケーションを取れるようさらに頑張ってまいります。
11月も素敵な読書が来出ました
平山 智美
なすの斎場グループ
読書感想文
ファンは年輪経営の強力なサポーターであり、ファンづくりは商売安定の源。会社のファンになった人はその人自身がリピーターになるだけでなく周囲の人たちにも紹介し勧めてくれる。しかし今いるファンに頼っているだけでは年月を経て減っていく…。
アレンジ教室で『マンネリにならぬような仕掛けが必要』と、社長が言っていたことと重なりました。
少しでも人の役に立てるような行動を常に常に心掛けて、当たり前のことをきちんと継続できるように心がけていきたいと思いました。
宮内 佐知江
なすの斎場グループ
11月課題図書
この本で初めて伊那食品工業さんという会社の存在を知りました。会社、従業員のことを幅広い観点・視点から考えられていてとても凄いというのが率直な感想です。
「会社経営はまちづくりの一端を担うもの」という信念はなすの斎場の地域に根ざし感謝される企業にすることのクレドに値していると感じなすの斎場が今行っている寄付や協賛の他、駐車場の貸出など様々な地域貢献を会社の一員として自発的に何が出来るか考えつつ、本にも書かれていたように「いずれも一時的な取り組みで終わらせることなく継続的におこなっています」と言えるように取り組めることを探していこうと思います。
赤羽根奈央子
なすの斎場グループ
読書感想文
印象的だったのが、右脳型、左脳型にバランスよく配慮するというところでした。右脳型、左脳型を意識してみるとよいとありました。色んなお客様がいるなかで右脳と左脳を意識することはイベントにいかせるなぁ~と思いました。
もうひとつは、快適さは職場づくりの大切なキーワード、会社も人生、家庭も人生通勤時間もまた人生とありました。思い返してみれば私の人生色々大変な事がありました 40も半ばになった私にはがむしゃらに仕事をするばかりではなく楽しめることをしようと思うようになっていて、ちょっとこの本の言いたいこととはずれているかもしれませんがワクワクしました。
40も半ばになった私にはがむしゃらに仕事をするばかりではなく楽しめることをしようと思うようになっていて、ちょっとこの本の言いたいこととはずれているかもしれませんがワクワクしました。
大金久美子
なすの斎場グループ
読書感想文
良い会社ではなくいい会社。
いい会社とは、社員、お客様、取引先、地域の人からいい会社だねと言ってもらえる会社。
そんな会社にするために社員の幸せを通じて世の中に貢献するという会社のあり方を実践し、地域の方からも信用していただける会社になった。
そして、ザッポスのコアバリューのようないい会社をつくるための10箇条もわかりやすかったです。
社員が社員を幸せにすること、そして、それを通じて世の中の幸せに貢献すること。
この本にたくさん出てくるハッピーや、幸せという文字がこの社長さんが本当に社員の幸せを考えて動いていること、そして社員も会社を愛し動くことでいい会社が出来上がったのだと思います。
なすの斎場も何気に近いなと思うとこが多々ありました。
ひとりひとりが自分の意思で行動できる、そこを目指して頑張ります。
月井 優二
なすの斎場グループ
11月課題図書
会社が掲げた目標10か条を会社が率先して実行。実行内容が従業員・地域の方々の目に見える、形に残る、心に響く。何十何百と積み重なれた事実を従業員がみて、自分が働いている会社に愛を持ちそれを伝えるために自主的に行動する。
社員発信の改善や要望が、自分が働く環境よりも地域の方に何ができるか、地域の方にどうみられるか、この視点で意見が出てくる事に本当に驚いた。
でも「利益は健全な事業活動をおこなった結果として生じるウンチのようなもの」というパワーワードにすべて持っていかれました。
車で行ける距離なので、春先くらいにドライブがてら訪問したいと思います。
村上絢美
なすの斎場グループ
11月読書感想文
この本を読みいい会社を目指すということ、とても大変なことっていうわけではないですが、周囲への配慮が必要で誰に対しても平等に接する…周りを気にしながら親切にする。地域の方へ貢献をしていく…とてもクレドを感じました。
出勤後朝礼前に清掃をすること、周りを見て配慮する力になると考えたらいいことが多く今後もしっかり清掃をやっていきたいと思います!!
星 大地
なすの斎場グループ
課題図書
読書を始めた当初はあまり乗り気ではなかったのですが、現在ではすんなり吸収できるようになってきました。
会社の目標を実行するためには、やはり会社スタッフがやる気にならなくてはいけない。
そうなるためにはスタッフが自分の会社に愛を持つ。
会社に愛を持つって物凄いことを書いているなぁ・・・・と思いますが、著者は「自分の会社スタッフは絶対自社を愛している」という絶対的な自信があるんだろうなぁ・・・と感じました。
正直、最初は綺麗ごとばかりな印象でしたが読み進めるうちに理想に見えてくる不思議な本でした。
屋代 実沙紀
なすの斎場グループ
伊那食品というとプリンやゼリーの素で有名な会社、というイメージです。最高顧問の方が作成された本、また、有名企業の社長が絶賛する本とのことで、経営者向けの内容なのかなと思いながら読み始めましたが、途中「幸せ」という単語が沢山出てきたことが印象的でした。10箇条がなすの斎場のクレドに通ずる部分もあると感じ、「いい会社」を目指すと自然と理念も似通ってくるのかな、と思いました。
社員だけでなく社外の方からもいい会社だね、と言って貰えるような会社の一員になるため、忘己利他を念頭に置いて仕事をしていきたいです
渡邊勇二
なすの斎場グループ
11月課題図書
尊敬される会社だけが真のブランドになれるというところが共感出来ました。お客様、地域の方々、取引先方々を幸せにし、尊敬され選ばれる会社になれば価格競争も必要ありません。施行やイベント、地域行事などを通してみんなハッピーになれるような行いをしていきたいです。葬儀でハッピーは少し違うかもしれませんが、『いい葬儀』と感じられるものにしたいと思います。
弊社で行っているキャンプクレドやクレドカードなど似たようなものもありましたし、ザッポスやリッツカールトンなどの考えと通ずる事があったりと、社員が一枚岩になれる図書でした。
藤田 勝文
なすの斎場グループ
【11月課題図書感想文】
一番印象的なフレーズは~「一緒に楽しもう」「苦労も分かち合おう」という気持ちを全員が共有出来る組織には、大きなパワーが宿ります~です。そしてこれこそ、「いい会社」をつくるベースになるのだと感じました。そして、うわべだけでは無く、本気で取り組み、何十年も継続することが年輪経営、理念経営であり、私たちの目指すティール組織にも繋がっていくイメージが出来たことに本書の価値を感じました。また、「四方よし」の概念を、ご遺族・地域・会社・将来としたときに、施行グループの5年物語とリンクしており、自分たちの進もうとしている未来が明るく感じられました。グループ独自のMVVを掲げたこのタイミングに、本書に触れる機会を提供していただいた社長に深く感謝申し上げます。ブレずに突き進みます!
竹中紗智
なすの斎場グループ
11月 おとなの読書感想文
3分間スピーチや理念のカード、会社が尊敬されるほど社員のモチベーションが高まる・・・所々・・・あら?リッツカールトン?と思う箇所があり、後半にある【名を残すのではなく名が残る生き方を】このフレーズに、スタッフへ名声欲しさや売上高めたいがために、がむしゃらにやれ!!ゴラァ!!ではなく、スタッフ全員がモチベーションが高く幸福であれば、必然と【いい会社】になり、脅迫レベルの落とし込みや指導をせずとも、世に名が残っていく。歴史上の聖職者にも繋がる内容だなと思いました。やはり葬儀社勤務といえばまだ(え?葬式屋なの?)と返される現在。ですがただの葬儀社ではなく身内の様に寄り添い、自社でお花を用意し、スタッフそれぞれにしっかりとした考えや想いのある なすの斎場という葬儀社に勤務しているので(そうだけど、うちの会社は他の葬儀屋とは違うよ)と胸張って言葉を返す事が出来ます。今月も課題図書を読み、より感じている事に間違いはないんだと再認識出来ました。今月もありがとうございました。
渡辺悟
なすの斎場グループ
11月大人の読書感想文
伊那食品工業の社長として派遣されたが、就任された時にはもう倒産寸前で、人、お金、設備何もない中で今いる人材でやる気になってもらうところから始まり、
自分で設備を改良、倉庫を作り、営業し、商品開発すべてやって見せてその姿をみた社員が、やる気になり協力的になったと書いてあり、文字で見るのは簡単に見えますが、考えるとものすごい事をしてると感じました
会社には終わりがありません。ですから、成長を急ぐのではなく、働く人が幸せを感じるような会社をつくるというのが印象的でした。
宮本法子
なすの斎場グループ
【11月課題図書】
普段のみるるではなかなか手にすることのないジャンルではありますが、幸福度合いが増すような題名にワクワクしながら読み進められた図書でした。末広がり、本当に良い響きです。
会社の存在意義を根底に、末広がりの良い会社を作るための幸福度には納得できる面が多くあり、社員の幸せの実現には、まさにサービスは幸せの連鎖である、その道筋が記されているように感じました。また、ドラッカー、二ノ宮尊徳、孟子、松下幸之助、渋沢栄一、千利休などなど、その考え方の土台となる数ある書籍から学び出るもの、そして学びを止まない姿勢が見えてきました。
働く人が幸せを感じるような会社を作って永続させていくことは地域に根差し感謝される企業に繋がります。利益の最大化は必ずしも人を幸せにはしませんが、人の幸せに向かう商品やサービスはいつか必ず報われる。その取り組みが他者貢献度(アドラー)と合わせて幸せの渦に呑み込まれ、図書冒頭のハッピーに繋がるのだと個人的には感じました。なすの斎場の100年カレンダーには未来のたくさんの幸せがつまっています。日々創造しながら、真に人の幸せに貢献できる働きができるような人間になりたいと強く想いました。
毎回大切な気づきと想いを伝えてくれる図書と社長には感謝します。想いと実現できることに差は生まれても、なすの斎場の名が残るよう、微力でもその学びを続けていきます。
寺門 大輔
なすの斎場グループ
11月 読書感想文
ほぼゼロの状態から経営者として、土台作り、社内規則の運用、そして発展まで進めていく過程を時系列的に学ぶことができた 特に、今後白河やさくら市への地域出店を行う際に、この本で取り上げれている「地域への貢献度を高くし、地域の一員となる」という点と、「社外へのブランド力の向上」の二点は非常に参考になった 特に「社外へのブランド力の向上」という点において、「地域貢献度の向上」から「社外ブランドの向上」、さらに「社外ブランドの向上」が「社員の能力向上」に繋がる点が明確に提示されており、この3つがサイクルとしてかみ合うことを深く理解することができた
今後の地域出店の際に、まずスタート地点として「地域貢献の向上」として思考をスタートできる点は、大きな学びになったと感じられる
櫻井 裕子
なすの斎場グループ
11月読書感想文
「利益は社員の幸せを実現するためにある」「会社が尊敬されるほど社員のモチベーションも高まる」など、結論からの内容にとても読みやすかったです。利益は会社の為と思っていましたが、最終的には社員の幸せにつながるのだと思ったと同時に、社長はじめ役職者の方々が社員の幸せの為に尽力してくれているのがなぜなのか気づかされました。
社員はお客様の為、また会社の為に、会社は社員の為に取り組むことでみんなの幸せにつながる。という解釈をしました。
相馬 なつみ
なすの斎場グループ
11月課題図書
経営についてはまったくわかっていなかったのですが、始めに読んでいて、究極の目的と一歩手前の目標を明確に捉えるというところで、奥田先生の勉強会で目標と目的の違いの話を思い出しました。
性善説の経営をすれば、結果的にコストは安くなるというところで社員が幸せを感じ、高いモチベーションをもって働いていれば、誤った経費の使い方をする者はいなくなるというところで、社長が目指している社員全員が幸せである葬儀社にするというところにむすびつきました。
年輪経営経営のお話では、社員や地域に貢献することを第一の使命とすべきとかいてありました。
やはり、社員が幸せで、地域に根差す会社にしていくことが大切なのだと感じました。
そのために、私がやるべきことは何なのかを考えながら行動できるようになりたいです。
相馬親太郎
なすの斎場グループ
11月【読書感想文】
まずは『みんなハッピー』とは、究極的な考え方だなと思いながら読んでいきました。会社が利益を求める理由として、社員の幸せと社会貢献をしていくためとは、すべてが巡り巡って最終的にみんなの幸せにつながるんだなとあらためて気づかされました。その中で、『良い会社』と『いい会社』の違いの部分は学びがあり、技術や経験、実績ではなく、人として中身、その成長が『いい会社』を作り、会社を成長させ、本当の意味で社会に貢献できるんじゃないかなと思います。人柄、人間性を大切にし、私もしっかりとそこを磨いていきます。自社の理念と近い内容であり、五年後をイメージしながら読むことができました。
藤田 裕子
なすの斎場グループ
11月課題図書
「みんなが幸せに人生を過ごせるように」「みんなハッピー」という言葉は深いと思いました。快適な職場作りは利益があるから・・利益は社員の幸せを実現するためにある・・・なすの斎場で置き換えると 社長が作ったクレドの 「自分にとってなにが幸せかを真剣に考えます。」ここだ!と思いました。儲けだけに走ってはいけないなどもありますが この本を読んでいて やはりファンを作る事が一番なのだと、この会社がすきだ・・・と言ってくれるファンの方がなすの斎場にもいてくれたらいいなと思いました。たくさん売るよりもきちんと売る。ここも今の自分たちに当てはまるものです。社会貢献、地域貢献、含め 自分たちに出来る事を自ら考え行動する。まさになすの斎場の未来につながる本でした。
高橋 真人
なすの斎場グループ
11月読書感想
内容はザッポスの本が少しボリューム重かったので今度も覚悟して読み始めましたが、かなりサクサク進めることができとても安心しました。
リーダーとして多少なりとも人をまとめる立ち位置にある私にとって耳が痛い話が多かっただけにとても勉強になりました。性善説で物事を考えることができなかったり、急がば回れとは言うけども・・・急いでるんだから近道したい、とか。ほかにもたくさん改めなければならない部分があり、もっと勉強して考えていかなければと感じるところでした。
ただ最後の方にあった「名が残る」生き方はとても印象的で、何かを成し遂げる、こうなる、というのは大切ではありますが結果こうだった、こんな風に思われたというのはとても見ていてこう生きようというとても分かりやすい指標になりました。
会社の細かな話から最後にはとても大きな人生というテーマになり、本を読んでいるのに自分自身と向き合うような気持になる、不思議な本でした。
田中 勝
なすの斎場グループ
11月課題図書
この本を読んで印象に強く残った言葉
利益は社員の幸せを実現するためにある
素晴らしい言葉である。利益があるからこそ給料もいただけて、幸せな人生をおくる事が出来ます。この本に書かれている内容はどれもいい会社にする為のモデルだと思いました。
我々社員も人間的成長が重要だと思います。会社の永続的な成長を目指していかないといけません。
また、年功序列型の待遇という内容も昭和から令和に続いてますが、こちらに関しては、年功序列型というより能力の高いという判断基準の方がいいのかなと感じました。
全体を通して、賛否両論があるかもしれません。令和の時代にあったやり方、昭和 平成のやり方は様々です。私個人的にはハッピーになれればいいのかと思いました。