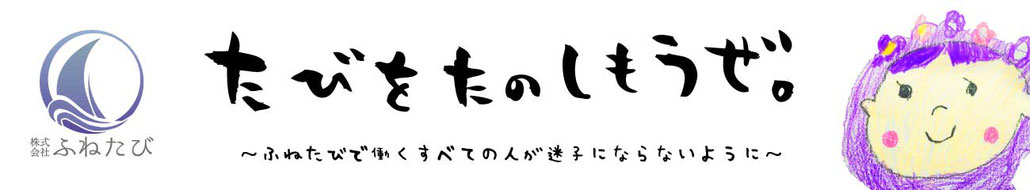常識をくつがえせ! 小さいは、強い 町の電気屋 VS 巨大量販店1450日の攻防
寺門 大輔
なすの斎場グループ
読書感想文【カデンのエトウ】
巨大量販店と町の電気屋、という教科書的な「巨人vs小人」という構図から、新規商圏への参入としての内容として読み砕くことができた。特に、冒頭の量販店オープンからのブランド力での圧倒、開店セールに向けての買い控え、オープン後のヘッドハンティングによる人材引き抜きといった場面は、巨大な資本力やブランドでじりじりと摺り潰されるような恐怖を感じた。
この点について、「社内理念の浸透」「差別化戦略」の2点がより強調されているように感じた。「社内理念の浸透」として、カデンのエトウでは「家電のレスキュー隊として、地域のお客様に愛される企業になる」という社内理念を浸透させることで、家電販売から家電の修理といった業種の返還や、ヘッドハンティングに対抗していたが、これもなすの斎場における「地域に感謝され、社員全員が幸せな葬儀社にする」というクレドに合致しているように感じた。この点は、クレドワークなどを通じて徹底されているように感じたが、時点の「差別化戦略」という点で、まだまだ改善の余地があるのではないかと感じた。
家電量販店では、ヤマダ電機といった明確な「巨人」が存在しており、葬儀業界では今後参入を目指す地域では、「さがみ・アルファクラブ」という「巨人」だけでなく、「とちそう」や「地元葬儀社」といった、ある種の「巨人」が乱立しているように感じている。現在でも、「山木屋」「さがみ」「アトラス」の3つの競合他社が乱立している大田原などが、この状況に近いと感じられる。その際に、全ての競合他社に対して、どのように差別化を打っていくのかが、ある意味「カデンのエトウ」よりも求められる要素なのではないかと感じた。
「カデンのエトウ」では、家電販売の物流を逆手にとり、ヤマダ電機から家電を仕入れ、それを修理販売するといった「差別化」で生き残れたが、葬儀業界では、「葬儀は山木屋、49日法要はさがみ、初盆はなすの」などといった共存は存在しえないので、49日法要から、初盆から、アフターから、大本である葬儀施行を引き抜く試みを広く考えなくてはならないのではないかと考えた
宮本法子
なすの斎場グループ
【4月課題図書】
町の電気屋が巨大量販店との闘いの末に掴んだ勝利。どのような仕組みや仕掛けがあるのかと興味本位で読み進めましたが、まるでドラマのようなストーリーに一気に読み終えてしまった図書でした。
商売の本質でもある不を取り除く4つのポイント。①不快を快適に変える②不満を満足に変える③不便を便利に変える④不安を安心にかえる。これには大きく頷きました。日々取り組んでいる業務は何のために行っているのか。言い換えればなすの斎場のクレドにも置き換えられるものです。また、“ありがとうや助かった”の声に“笑顔が人を幸せにな気分にすることを学んだ”には、当たり前のことに感じることでもそれを心から感じ取れることができたからこそ一歩前に、されに一歩進めたのかもしれないと感じました。どの過程も描写は抽象のハシゴ理論のようで、とても晴れやかな気分です。
お客さんが大事にしているものを同じように大切にしたい。その想いはなすの斎場での“ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式”そのもの。差別化は経営理念の素晴らしさ、そしてそれが普遍的なもの。なすの斎場の未来も輝かしいです。
病に冒されながらも“やっぱり人がすき”とさらなる未来を描く著者。やはり人は人と触れ合うことでしか磨かれないのかと個人的に感じました。スタッフのみでなく、お客様との触れ合いも大切に、業務に邁進したいと思います。今月も大切な想いを感じさせてくれたこと、それを提供して下さった図書と社長には感謝します。
宮内 佐知江
なすの斎場グループ
4月課題図書
この本を読んでカデンのエトウさんという会社・名前を初めて知りましたが読み終えてこんなお店が身近にあったらいいなと感じました。巨大な組織に立ち向かう、とても壮大で先が見えない挑戦を諦めずにあの手この手の試行錯誤のなか代打ちした結果、今のエトウさんが存在し会社として信念を貫いた結果がお客様に思いが伝わったのかなと感慨深い内容でどんなに主流でもダメなものはダメと経営理念に則した商品提供、お客様の生活を守るということまで考えて提供してくれるなんて消費者側としてはとても有難いし信用性にも繋がると感じました。
形見のホース修理の話で「お客さんが大事にしていることを、おなじくらい大事にできる店でありたい」この文面の言葉のように、こんなふうにお客様に寄り添った対応が出来るように自分もひとつひとつ真摯に対応していこうと強く思ったのと経営理念の素晴らしさ大切さを念頭にお客様対応をしていく必要性を感じることができとても勉強になる1冊でした。
田中 勝
なすの斎場グループ
4月課題図書
この本を読んで、最初は中々頭に入ってきんでしたが、色々私の仕事でも参考になる内容があり読み切れました。
笑顔が本当に人を幸せな気分にするという事。そしてお客様に喜んでいただく事。その2つを改めて学んだ気がします。
私と一緒な考えがあり、テキパキ スピーディー あるいは正確さ等、家電のエトーさんも大事な事なんだと。とても共感持てました。家電のレスキューとして看板を出し、どこにも負けないくらい企業を大きくし、なすの斎場としても真似をするべき所がありました。企業を大きくする分岐点として、兄弟で完全文業しての取り組みが大成功に繋がった。正しく今の我々が実施している個々の能力を発揮させるシーンではないでしょうか。
そして経営理念がしっかりあるからこそ、経営が下向きになったとしても、理念がしっかりある企業とない企業では天と地の差がでる。
個々の能力を活かした分業化
アイデンティティの確立
ミッションインストール
初めて聞く言葉なので、ネットで色々調べてみました。結果、今までの考えが如何に古い考えかと勉強させられました。今は令和でしたね。
お客様に対しての接し方も改めて考えさせられました。不満を満足に。全ての内容を意識し、今後の仕事に取り組みたいと思います。小さくてもいずれ強くなります。我々もお葬式のレスキューになりたいと思います。また、エトーさんの成功の秘訣を参考に色々考えて提案していきます。
月井 優二
なすの斎場グループ
4月課題図書
課題図書の中で声を出して笑ったのはこの本が初めてでした。ヤ〇ダ ル〇バ ダ〇ソンなどの表記も面白いですが、ヤ〇ダ電気を第二の展示場としてお客様をお連れする、その光景はぜひ目の前で見たかった。
タイトルだけ見るとどうやって撤退させたか?と気になったが理念(アイデンティティー)に沿った行動でお客様にどう選んでもらったか?
これからの自身の全ての業務について、誰に何を届けるべきか再確認する図書でした。
相馬親太郎
なすの斎場グループ
【4月読書感想文】
物を売るのではなく、価値を売る時代になってきたことをあらためて実感する内容でした。駕籠屋の話しはわかりやすく、担ぐのではなく安全に運ぶの例え、手段と目的の違いをしっかり認識しなくては本当の価値はわからないと感じました。その中で、アイデンティティの確立、自分は何者か?何をすべきか?そこをわかっていないと自分自身に理念は浸透しないんだなと思います。少し半沢直樹のドラマに出てきそうな内容に感じ、楽しめて読むことができました。
今後もしっかりと、ただの物売りにならないようこの本を参考にしていきたいと思います。
村上絢美
なすの斎場グループ
4月読書感想文
この本を読んで初めて知った会社でした。
まず最初に大型店が目の前にできたらどうするのだろう…と先に思いました。
家電量販店では私の感覚になりますが、安いお店で同じものを買うことが一番だと思っていました。ですがこの本で学べたことは金額だけではないと感じました。一番の学びは、基本方針!!
『断らない』『すぐに対応します』『納得するまでフォローします』
とても勇気がいる誓いの一つです。
そしてもっと私も信頼を得れるようご対応していきたいと感じました。
高橋清志
なすの斎場グループ
4月読書感想文
常識を覆せ!小さいは強いを終えて。
街の小さな電気屋と大型店舗との戦いのお話でありました。
普通常識で考えると、小さな町の電気屋では全国規模の大きな家電量販店には絶対に敵わないと思いながら話を進めていきました。
しかしながら、徹底したお客様に対するサービス、情報戦、値段も重要ですがこの電気屋さんなら安心してお仕事を依頼できる。そんな信頼関係を気付けたからこそ最終的には生き残り戦争に勝ち、地域の一番店としての地位を盤石にできた原因であるのではと思いました。
当社のクレドにもありますが「すべて自分の身内なら」と考え行動、サービスを提供できることが大事なことなのですね。
どんな規模が大きなお仕事でも、小さなお仕事でも仕事には変わりありません。
どんなささやかな事でもお客様は見ておられます。
紳士であり偽りのないまっすぐな自分を作っていきたいと考えました。
4月も素晴らしい読書が出来ました。
高橋 真人
なすの斎場グループ
4月読書感想
改めての感想文になります。家電の江藤さん、実際に大分に出張に行かせていただき大型電気店との距離感や、店舗の内装など肌で感じてより一層すごいなという実感でした。
そして何よりもやはり感じるのはクレド、企業理念の大切さですね。大切なのはいわゆるウルトラC,裏技的なものではなく、日ごろからのクレドの浸透とそれをいかに行動に移すことができるかというところにかかってくるというのはまさに当たり前のこと、かもしれませんが、その当たり前のことをしている会社、続けている会社がいかに少ないことか・・・。
自分たちがすべきこと、しなければならないことは何なのかというところで「ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式」をいかに行っていくかというさらになすの斎場の葬儀をとがらせるきっかけを与えてくれた江藤さんには本当に感謝でした!原点に立ち返ってこれから進んでいける!と感じました。
どれだけ会社の規模が大きくなろうと、従業員の数が増えようと、そこだけはぶらせてはいけないという一つの軸になったので、この軸を大切に日々仕事に取り組んでいきたいと思います!
藤田 裕子
なすの斎場グループ
4月課題図書
常識をくつがえせ。の表紙、兄弟で仕事を分担している光景。途中で出てきた地域を守る 家電のレスキュー隊のコンセプト、○○レンジャー、アホっぽく見えるそれでもいい。一生懸命に取り組むかっこよくやる。中身がともなわいとどうしようもなくなる。そりゃそうだと思いましたが、私たちもある意味○○レンジャーじゃん!と思いました。お客様の役に立つために何が1番か?目指す場所が一点なら、使命を果たした結果が、売上につながる。
ホースの話のなかでも大切なものを修理依頼お客様によりそってなんとかしてあげたいとの気持ちが目に浮かびました。
そしてヤ○ダ電機を展示場と呼び、お客様を連れて商品案内、自社に連れ帰り商談…倉庫とさえ呼んでました。これありえません。考えられません。と私には面白い本でした
大きな会社だから…とかそうゆう視点は消そうと思いました。しっかり自分たちのクレドを中心に考えて行動できるようにこれからも悩んだ時はクレドに立ち返ろうと思いました。
平山 智美
なすの斎場グループ
4月読書感想文
この本を読んで、カデンのエトウさんかっこいいと思いました!『エトウ品質』ガイドラインにもとづいてお客様の「不」の解消。お客様に寄り添って耳を傾けることで「モノ」ではなくて「コト」のご提供が出来るんだと思いました。いろいろな事例を読み、こんなにお客様のことを考えているなんて感動でした。ライバルを利用した商品案内などもビックリしましたが、行動力が素晴らしいと思いました。
これからの業務で、お客様との接し方や業務との向き合い方などとても勉強になりました。
藤田 勝文
なすの斎場グループ
4月課題図書
課題図書でもあり、実際に視察にもいかせていただき、よりリアルに家電のエトーの世界観を実感することがでしました。自分は何者なのか?アイデンティティから生み出された念とその理念が共有されたチームは強い。ことを目の当たりにすることが出来ました。30万人都市、競合他社が寡占しているエリアに出店を仕掛ける我々にとって、大いなるヒント、見本となる世界観だと感じています。ビビりチャレンジをどれだけ行えるか?自分自身の課題を見出すことが出来たことに感謝します<m(__)m>
星 大地
なすの斎場グループ
4月課題図書
本の中でも、スタッフ1人1人へ想いの浸透に触れる部分は多々ありました。
家電のレスキュー隊と看板に大きく書いてあると思うのですが、家電って割と自分が使用しているものに愛着がわくので直して使う。
を全面に打ち出すことはシンプルに地域に密着していると思いました。
アイデンティティというものを1人1人が理解し、常に軸に考えて行動することで乗り越えられたのだと思います。
私はWEBとCRMという、どちらも規模が大きくなるとそのまま大きくなる部署ですのでクレドが一番浸透すべき場所だと考えています。
今から何を目指すべきなのか、そのためになにをするかをしっかりと考えていきたいと考えます。
渡邊勇二
なすの斎場グループ
4月課題図書
アイデンティティを磨き上げ、ミッションを叩き込み、経営理念を深く浸透させる。これを徹底的に繰り返す。これが巨大量販店に勝った方法と解釈しました。マーケティングの観点からみても、販売品目を絞ったり、差別化戦略を取り入れたり行っていましたが、「経営理念」から導き出された戦略でした。常識を覆したうらには、自社のユニホームを着て商品説明をしたり、フランチャイズ展開の裏をかいてヤ〇ダ電機を倉庫代わりに使ったりと常識はずれな考えがありました。強い相手には遠慮はいらないというように、こっちまでもっとやれ!次は何を仕掛けるとヤ〇ダ電機が撤退するまでの展開が面白かったです。
撤退してからの売り上げ減の理由も緊張感がなくなり気持ちが緩んだことが原因とまとめられていました。気持ち一つで売上げも変わってくる、いかに経営理念の浸透が大切かがわかります。
これからもクレドを信じてクレドを実践するのみ!またこれからはインナーブランディングも考えていきたいと思います。
大金久美子
なすの斎場グループ
4月課題図書 常識をくつがえせ!小さいは、強い
小さな電気屋さんがヤ◯ダ電機なんにどーやって勝ったのか、想像もつきませんでした。
実際に読んでいくうちに自分がエトウさんと一員の様な感覚になり、トムソーヤの話やアンパンマンのお話などあーそーゆーのあるよねって共感しながら読み進めることが出来ました。
アイデンティティの確立やミッションインストールなど最終的に相手が誰でさえ、自分の進む道がわかっていれば怖いことはない。勝てる分野に狙いを定め100点満点を貫くこと。なすの斎場も素晴らしいクレドがあり、ありがとうを紡ぐお手伝いをしていると考えればタクセルがこよーと何がこよーとそこは恐る事じゃないじゃないか、と改めて感じました。
家電の選び方も電気屋さん目線であり、私は結構ネットを利用してしまっているので次何か買う時はきちんと考えて買おうと思います。
ピンチがチャンス、考え方一つで自分達のプラスに持っていけるエトウさんを参考に日々の業務においても常に成長し続けていこうと思います。
屋代 実沙紀
なすの斎場グループ
4月課題図書
目の前に大型量販店がやって来るという不安や焦りから、地域密着の「町の電気屋さん」として何を提供するべきかという答えにたどり着き、ヤマダ電機の出店を貴重な体験だったと振り返られるようになるまで…まさに「蟻のひと噛み巨象を倒す」を体現したようなエピソードです。相見積もりを逆手に取ったり、ヤマダ電機のシステムを利用して展示場・倉庫扱いする等、とても想像がつかない反撃方法でした。
共感する部分も複数あり、特に
・不快、不満、不便、不安を良い方向へ変える
・「お客さんが大事にしていることを、同じくらい大事にできる店でありたい」
この2点を念頭に置いてこれからもお客様と接していこうと思いました。
赤羽根奈央子
なすの斎場グループ
4月の課題図書
常識をくつがえせ!まさにどの項目をみてもどういうこと?と目をひくものばかりでした。その中でも仕事は楽しそうにやろう。提供すべきはモノではなく価値などそうだよなあ~と納得。葬儀も金額だけをみたら高いと思ってもコトの提供が満足できれば決して高くない、逆に徳をしたと思ってもらえるのだと思います。これからに生かしたいと思います。
相馬 なつみ
なすの斎場グループ
4月の課題図書
まずは、自分がなにものかを知ること。そして自分の会社がどういう存在かを認識すること。
常に理念を胸に刻んでおくことで意識が高ままってると、慢心することなく成長しつづけるようになる。
改めて、クレドの大切さを認識することができました。
そして、アンパンマンのように、損得抜きで困っている方の役に立ちたいと思う気持ちはすごいなと思いました。自社の強みを生かすためには、どのような方向性で、なにに特化すれば良いのか、自分たちは、なにもので、なにのために、この地域にこだわって商売をしていくのか、目標設定をするときに、もう少しよく考えたいと思いました。
高橋嶺太
なすの斎場グループ
4月課題図書
読み始めから絶対絶滅の展開にハラハラしました。
揺るがない方針を作り社員が一丸となって実行することの大切さを知りました。
個人的には「アイデンティティの確立」と「ミッションインストール」自分が何者かを知り、何をすべきかをはっきりさせること、の部分に共感しました。「自らの意志さえ揺らぐことがなければ
人生なんて、いずれは道が開けてきます」
まさにその通りですが、具体的にどのようにすれば良いのか、そこを分かりやすくたとえ話しで書かれていたのでとても勉強になりました。
竹中紗智
なすの斎場グループ
4月課題図書
題名から常識をくつがえすとは?と疑問に思いつつ、読み始めるとエトウさんの人柄がにじみ出ていて実際にお店で話を聞いている気分でした。ヤ○ダ電気の写真を見た時は思わず声が出て、しずか西那須野の向かい側の質屋がサガミさんになった気分になりました。うちで事前相談をして、そのまま向かい側のサガミさんに相談用紙を持っていくような環境…。そこからの発想の転換はエトウさんのアイデンティティが確立していたからこそ、なしえた事だと思います。その他、佐伯を盛り上げるために佐伯ラーメンの販売を開始、ラー博で隣の敵が調理を手伝ってくれた下りは思わず涙が溢れました。特に本書の中で、アイデンティティの確立という文字を目にして非常に考えさせられ、多方面から自己を見つめるべく様々な方の本を読むようになりました。今月もありがとうございました。
櫻井 裕子
なすの斎場グループ
4月課題図書
反撃の狼煙ー小さいは強い!ここが胸に刺さりました。
地道にやってきたことが結果として花開く。
クレドの勉強会や、他社さんとの勉強会も毎月読書をさせてもらっていることも自分たちの血肉となっている。と考えると結果を出す。いや、出せるはず!と思えました。
渡辺悟
なすの斎場グループ
4月課題図書
常識をくつがえせを読んで
電気屋さんの話聞いて、なぜ??と思いましたが、一番印象に残ったのが自分が何者かをしり、何をするかをはっきりさせる事と書いてありすごい衝撃でしたそして具体的な例をわかりやすく上げているので、すごく読みやすくすらすら読めました。
自分が何者なのかそして何をするかをはっきりと考えながら過ごしていきたいと思いました。