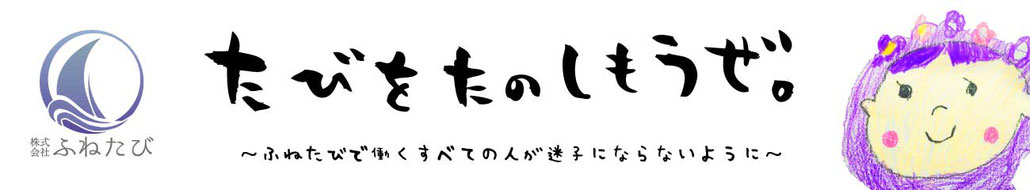なぜ、社員10人でも分かり合えないのか
宮本法子
なすの斎場グループ
【6月課題図書】
自分のことで精一杯、他者1人分かり合うのも必死です。同じ仕事をしていく仲間に興味はある、分かり合いたい、どのような努力が適切なのか、ヒントを探るように必死に読み進めた図書でした。
分かり合う必要性について、世界レベルの競争に巻き込まれる現状において、より強く結びついた組織の在り方の模索の1つと理解しました。主観は思い込み。まずは思い込みを徹底的に取り除く。それは対お客様に対しても同様でした。1つの声を丁寧に拾う。主観によらない正確な情報の把握。明確な言葉での会話。基本的なことのようで行動に移すには努力を要するものばかりです。まずは端的な意味の有る言葉、共通の言葉、迷ったら“なぜ”を繰り返す週間を身に着けていきます。
生きる要因に「DNA要因、環境要因、時価要因」が記されており、以前生物学者が「人は何故死ぬのか」の問いに「変化するため」との返答が浮かびました。そして常に変化していく社会で今何が必要なのか。迷ったら戻る場所は“内村鑑三”との記載に「余は如何にして基督信徒となりし~」の文面が浮かび、さらにどの図書にも共通する「信用」のキーワードについての掘り下げ“信用を財産に”という文言に、なすの斎場での基盤はクレドにあるのだと、より強く落とし込むことができました。
「その時歴史が動いた」これが「その時なすの斎場が動いた」物語になった時、まさにその時自分がそこにいられたことが“幸せ”だと実感できる瞬間だと想像しました。今の幸せだけでなく、未来に幸せが約束されている会社にいられること。今の自分にできることは最大限に活かしいこうと活力をくれた図書でもありました。毎回大切な気づきとそれを提供してい下さる社長には感謝します。
田中 勝
なすの斎場グループ
6月課題図書
小さい会社でも、大企業に負けることなく、
世界中から注文が来る同社の、顧客を考え抜いた姿勢には驚きました。
納入後の使用状況、使い方の調査から細かく提案されている。それと同時に、原因や理由を考えるプロセスが出来ているため、考えて仕事が出来るような組織になっている。
また、言葉にしにくい問題点も、文字から物語化など
共有化しやすい。逆に言えば、少数でもここまで仕組化しないと真の意思疎通は出来ないという事がよく理解出来ます。中々奥が深い内容だと思いました。特に印象深かった内容として、売れなかった理由は考えない。売れなかった理由より、売れた理由にこだわる事。確かにそうだなと消費者目線でも見れました。
ブランド力=信用力X知名度 コレなんか、わかりやすくてとてもいいです。
宮内 佐知江
なすの斎場グループ
6月課題図書
あちこちにあるよく見かける鏡を製造されているのがコミーさんとう会社だと初めて知りましたし正直あまり鏡に関して意識していなかったので改めてすごい商品開発されたなと思いました。本のタイトルにもあるようにコミーさんの会社全体としてのキーワード何事も「なぜ」と社全体で考え「なぜ?」を5回繰り返すだけでも脳が働き始めると書かれていましたが確かに「なぜ」と疑問に思わなければそのまま流れてしまうこともあるし、良い発想も疑問に思うことから発見できることもあるだろうと感じました。SS時間やヌシ化や物語化など取り入れたら変化を望めるかなと思うことがいろいろ参考になる本でした。
藤田 勝文
なすの斎場グループ
6月課題図書
規模や方向性は様々あるが、VMVが浸透している組織は強い。ことを再認識する図書であったと感じます。その中で一番共感したことが、ヌシ化のエピソードでした。「担当でなければわからない」葬儀社あるあるですが、中小企業であればやむを得ないことかと感じていましたが、小さい組織だからこその落とし穴になっていることに共感出来ました。
「なぜ」で成長する感覚は大切にしていきたいと感じます。これは人の成長・企業の成長に繋がることは勿論、弊社のおいての「事前相談」の質の向上に繋がると感じました。「なぜ」家族葬を希望されているのか?「なぜ」火葬式を考えているのか?「なぜ」不安なのか?「なぜ」家族関係がうまくいってないのか?「なぜ」事前に相談したいと考えたのか?「なぜ?」の本質は対象者(モノ)に興味(自分事として)を持つことだと考えていたしたが、本書を通して改めて「なぜ」の重要性を実感しつつ、「なんとなくの気付き」を確信に変えるきっかけになりました(^^)/
高橋清志
なすの斎場グループ
6月課題図書
なぜ、社員10人でも分かり合えないのかを読んで。
お話の内容はコミーさんの鏡を売っていくお話がメインでしたが、売っていくための戦略、社員同士の意識の共有等の内容でした。
全てはお客様の為にという考えのもと、ミラーの無料貸し出し、無料交換。徹底した現地調査聞き込みを行い常にお客様に寄り添い良い製品を提供していけばよいのかと言う物でした。その内容を社員全員で共有するための会議。何のためにこの会議を行うのか、社員全員が理解し共有することで皆が同じ考えにたどり着けるといったものでした。食い違う意見などがあれば「なぜ」を5回繰り返し社員にも考える力を身に着けさせることが出来る。
「ヌシ」と言う者をつくってはいけない。皆が同じ仕事をしていくためには皆が平等であるという事なのではないかと考えました。
相馬親太郎
なすの斎場グループ
6月読書感想文
自分自身、大きな組織にも小さな組織にも属した経験があるため、当時を思い返すと、残念ですが良くない意味で当てはまることが多い内容でした。その分、共感できる話しも多く、やはり小さな組織にありがちな【ヌシ化】を自分自身も経験し、人に仕事がくっついているというのは組織の成長を妨げるということをあらためて感じます。そしてそこに繋がることとして、自分の世界で仕事しているので、【なぜ】が生まれない。言葉も厳密ではなく、あいまいな表現になる。たしかにそうだったなと思いながら、本書を読んで、現在の自分も【なぜ】が足りないと感じましたし、【いろいろ】や【など】という言葉も多いので、明確にそして短くわかりやすく話しをできるよう、そして日々の【なぜ】を意識して取り組んでいきます。
平山 智美
なすの斎場グループ
6月読書感想文
小さな組織をむしばむ『ヌシ化』のところで、不慣れな新人が『やりにくい』と感じた違和感を重く受け止めるべきとあり,
いつも社長が言っているなと思いました。実際自分の業務の中にも思い当たることがあり、やりにくいことがあっても、ずっとこれでやってきたからと疑問にも思わない。改善しようという考えに至らない。慣れって怖いなあ‥と思いました。
『なぜ』を5回繰り返す。自分自身に問いかけることを忘れずに問題発覚能力を高めていきたいと思いました。
赤羽根奈央子
なすの斎場グループ
6月の課題図書
印象に残ったのは”言葉の定義を厳密に決める”というところで、長い言葉には逃げ口がたくさんある短い言葉にするなどありました。
私自身いくつになっても言葉で考えることは終わりがなく、人から言われたことも自分の解釈が入ると違う誰かに伝える時に言葉が変わってしまう言葉か変わると伝えた人の解釈が変わる。言葉の伝え方になやみは尽きません。
短い言葉で伝えるのは難しいもので自分はそんなつもりはなくてもきつい言葉になってしまったりもするので注意が必要ですが、”伸びる会社は言葉が顕密”ともありました。”いろいろ”などあいまいな表現は使わないように気をつけたいと思いました。
藤田 裕子
なすの斎場グループ
課題図書感想文
小さな会社だからこそ、専門化が進み「◯◯さんしか出来ない」となり、人事異動もできずにコミュニケーションが悪くなるという点は納得でした。大きな会社では代わりは誰でもいるのかもしれない。「コミー訓」という社長の信念が一緒に働く仲間を導き良くしてるんだろうと思いました。
なぜ?なぜ?の30分、このなぜ?を追求していく所も必要なコミュニケーションだと思いました。
屋代 実沙紀
なすの斎場グループ
6月課題図書
気配りミラーや飛行機の荷物棚ミラーといった「ああ、見たことがある」という商品を開発し、高いシェアを誇っているのが少人数の会社だということに驚きました。
「売れなかった理由」は考えないけれど、「売れた理由」には拘る。思い付きで作った回転ミラーをまとめ買いした人がいて、想像以上に売れた事を喜んで終わるのではなく、なぜ買ってくれたのかを追及したからこそ、商品に製作側が思い付かなかった使用用途があると分かった。「なぜ」と思う事が発見や成長の元となる…考え続ける事が大切だと思いました。
また、途中途中にある小宮山社長のコミー訓も興味深かったです。特に、信用という財産をつくる・SS時間を取る事は仕事をする上で実践していきたいです。
渡邊勇二
なすの斎場グループ
6月の読書感想文
なぜと繰り返すと本質が見えてくる。実は社会人1年目入社1ヶ月でたたき込まれたのがこれでした。意外と難しくなぜの答えになっていなかったり、変な方向にそれていったり。仮説を立てたりする時に、たまにこの考えを使っていることがあります。あるべき姿と現状のギャップが問題点。問題点をなぜと掘り下げると本質が見えると教わりました。コミー社員のように当然のようになぜとすぐに出てくる問題意識を常に持って仕事、生活していこうと思います。
この思考があるから大量注文になぜと思い、出向いて調査したり、ユーザーに聞いたりの行動になるのだと思います。
コミー用語を見ると、私たちが使う言葉にも個々で解釈が違うものが結構あるのではと思いました。クレドワークやキャンプテントでも考え方がそれぞれあったりします。それで良いものとコミュニケーションとしてまずいものがあるなと思いました。
高橋 真人
なすの斎場グループ
6月読書感想
飛行機の手荷物おきについている鏡やATMの鏡など、身近にある製品を作っている会社ということでとても入りやすかったです。
中でも4章のヌシ化の話は気をつけなければ、取り入れなければという部分でもありました。また「なぜ」と聞くためには、本当にそのことについて考えていなければなぜと聞けないので、本当にコミーの人たちは真摯に仕事に取り組んでいるのだな…とも感じました。
自分も普段からできること、たくさんのなぜをぶつけることができるように、一つ一つの物事をこれまで以上に真剣に考え、真摯に向き合って仕事に取り組んでいこうと思いました!
星 大地
なすの斎場グループ
課題図書
まず面白いのが、ヌシ化ですが葬儀自体担当=ヌシということにならないようにはどうするか。
もう情報共有だな、と。
他社と比べても既に、カレンダー入力での共有、伝達書での共有、LINEでの見える化、振り返りチャットとありますのであとはその精度の質をあげることにあると感じました。
他にも、悪いことを見つけたときには大騒ぎできる。という環境は最高ですね。
自分にとって不都合=ではなく
会社全体にとって不利益が=
になるよう、意識を統一して全体でひとつひとつをブラッシュアップしたいですね。
相馬 なつみ
なすの斎場グループ
6月課題図書
具体的な事例をとりあげてあるので読みすすめやすい本でした。コミーという会社は知らなかったのですが、いろいろなところで使われていると知り小さな会社でなぜそこまでできるのかと驚きました。なぜこの商品が売れたのか、問題があったのか、結果が良くても悪くても、なぜそうなったのかを徹底的に分析する。なぜを追求する大切さを学びました。
寺門 大輔
なすの斎場グループ
6月課題図書
本の項目で大きくクローズアップされていた、「ヌシ化」の項目については大きく同意できる点があった
特に、葬儀においては担当者依存になる面が多く、担当者不在の際に集金や相談があった際に、「ヌシ化」した担当者がいないと話が進まない、という面には、多くの面で実感しており、いまだ大きな課題として感じていた。こういった場面での特効薬として、著書では「情報共有」と「疑問をもつこと」の2点があげられており、これも何度も社内で提起されていたことだったので、ある意味この流れには「既視感」のようなものを実感した
特に、この2点を根付かせるためには、社内理念の更新・浸透の2軸が重要であるということを、実例を交えて学ぶことができた
月井 優二
なすの斎場グループ
6月課題図書
大量注文に対してなぜ?を持ち現場で確認。こちらの意図とは違う使い方を知り新たな商品にしていく。この本を読んで以前読んだ「売れないが売れるに変わるたった一つの質問」に共通している部分が多いのかなと感じた。
コミー用語集はおもしろいし、入社したばかりの新人には張り出しなど行えばわかりやすいかも。
極端ですが、30分の時間で30個のなぜ?が飛び交う朝礼は…ちょっと…あれですね。
渡辺悟
なすの斎場グループ
6月課題図書
タイトルがネガティブな本だなーという印象から本を読み進めていくと
『なぜなぜ』を繰り返して、考える社員を育てる、そして弱みを克服をするのではなく強みを活かすというところがものすごく共感ができました。
村上絢美
なすの斎場グループ
6月感想文
鏡のお話がメインでした。売るためにどうするのか、とても興味深く、読むのがスムーズでした。販売する前にお話を聞いたり実際に確認に行ったりと大変そうですが、販売する為に行う大切なことなんだと思いました。
また、『ヌシ化』でその人しかできないこと、『なぜ?』を繰り返し本当の原因を見つけるようにしているとあり、納得しました。疑問を持ち本当のことを気付けるようになる、私自身も追求して行ければと思いました。
竹中紗智
なすの斎場グループ
6月大人の感想分
小さい会社だからこそ特有の◯◯さんしか出来ない」 というやり取りが起こり、人事異動もできずにコミュニケーションが悪くなる、そして職場環境も悪くなるという点は非常に理解出来ました。企業・会社・組織が大きくなればなるほど、ヌシ化は薄れこの人じゃなきゃとはならず、全員が突発的にでも対応が可能になる。効率化を考えるならば会社が成長し変わる時、変化する事を拒まない意識の改善が本当に必要だと思いました。そして・・・「なぜ」世界に認められているのか。徹底した社員同士のコミュニケーション、いつでも社員一人一人が互いに「なぜ?なぜ?なぜ?」と疑問をぶつけ合う方法・・・お互いの思い込みを徹底して解消、整理していく。発展的な話は必ず(なぜ?)と声が出るけれど、否定的な話には絶対出てこない言葉だなと思いました。疑問を持つ事、事実を明確にする事の大切を再度学べた本でした。今月もありがとうございました。
櫻井 裕子
なすの斎場グループ
6月読書感想文
本のタイトルと読み始めるとミラーの話だったので、あれ?って感じだったのですが、コミー用語が自社でも認識が違う言葉があるな、と思いました。
何でも「なぜ?」と思わないのは興味がないから?もっとご遺族様に興味をもって遺族の一人として、深堀りしていこうと思いました。そのコミュニケーションは対お客様や一緒に働くスタッフにも言えることかと思いました。
大金久美子
なすの斎場グループ
6月課題図書
なぜ、社員10人でも分かり合えないのか
コンビニや銀行でみていたあの鏡がコミーという商品だったこと、飛行機にも使われているあの鏡が日本の小さな会社が作っていることに驚きました。
・CSではなくUSを大切にし、儲けよりも顧客との信頼関係を重要視し、コミュニケーションをはかり不安要素を取り除くために何度も足を運び、徹底的に社内で問題点を解決するために時間を費やすところが簡単にまねできないと思います。
・ヌシ化は自チームでもあるあるなので、誰でもわかる、できるにすることが大切。
・モノガタリ化などは、キントーンで共有する情報としてどんどん取り入れていかなければせっかくの情報が無駄になってしまうので改めてキントーン整備や情報を残すべくツールをフル活用したいと思います。
・なぜを5回繰り返し、考える社員を増やし強みを活かす。これもぜひマネしていきたいです。
高橋嶺太
なすの斎場グループ
6月課題図書
朝会で、なぜ?と問う習慣を体に染みこませるため30個のなぜを問いかけたというところに強く共感致しました。子供の頃は見るものすべてになぜ?と思っていた気がします。ですが、大人になるにつれなぜ?と思うことが少なくなってきたような気がします(実際には強がっているように思えます)
普段あたりまえに思っていることにもなぜ?と
問いかけてみると、そこから新しい発見があると
思います。私の好きな本で東大思考という本があります。この本は東大生の思考がどうなっているかを研究したもので、この中でも、東大生は物事全てになぜ?を投げかけていると書かれています。
お葬儀の仕事で、普段何気なく行っていることにも
なぜ?と、問いかけてみようと思いました。
関口将仁
なすの斎場グループ
【6月図書】2206「なぜ、社員10人でもわかり合えないのか」
①選んだ理由:「歴史は動いた」
新しい仲間との差をどうしても最近感じます。その中でこの「歴史は動いた」は良い取り組みだなと感じましたし、弊社でもやろうと思っています。
②選んだ理由:「参考になるものが多い」
皆の感想文では「ヌシ化」「なぜ?五回」「用語の明確化」「売れた理由」など、参考になることが多かったようです。私は「これとこれをやる!」というよりも、それぞれが参考になって仕事の質があがるような気がしました。
③選んだ理由:「小さくてもとがる」
売上5億で世界に輸出。NHKでも放送される小さな会社…。かっこいい!と思いました。私たちもそんな小さくてもとがるような組織になりたいと単純に考えています。みんなもそう思ってもいたいですが、そのためには日々変化・成長が必須ですね。