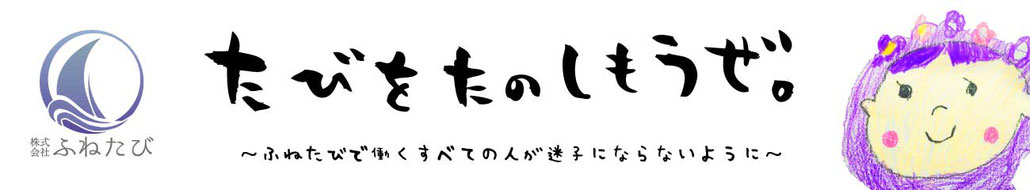【オーディオ】日産 驚異の会議 改革の10年が生み落としたノウハウ
藤田 勝文
なすの斎場グループ
【7月課題図書】日産の会議
実際に行われている会議手法が具体的に掲載されているので学びの多い図書でした。聞き流していく中で、実本を購入したい衝動にかられました。特に、決定権者が会議に参加しない方法・他部署のメンバーでチームを組むこと方法などは、実際に取り入れ始まっているのでより深い学びになりました。その中で、日産という会社がV字回復したストーリーに会議手法が大きな役割を得ていたことが衝撃的でした。今となっては残念な状態ですが、ゴーンさんの凄さを感じました。元々が卑劣なリストラと経費削減で営業利益を上げた人。という浅い知識で勝手にイメージを持っていましたが、やっぱり(あたりまえですが。。。)それだけでは無かったんだと感動しました。私の今までの生き方・考え方を振り返ると、部分最適化的な考え方が強かったなと気付きました。組織が大きくなればなるほど、この考え方だと、日産のように衰退するメカニズムを理解出来ました。危なかった!まさに目から鱗です(^^)/全体最適化の考えはクレドにも通じるところがありますので、しっかりと意識し、今後のミーティング、会議に活かしていきます。
田中 勝
なすの斎場グループ
7月課題図書
とても聴きやすく、興味ある内容でした。
日産といえば、カルロス・ゴーン氏の経営術にフォーカスがあたることが多いが実は、それを達成するために日々会議をしてPDCAを回しているんだなと思いました。
この会議のやり方は、これまでいかに無駄な会議が多かったか、これまでの時間を取り戻したくなるような、効率化を感じした。それだけ、無意味な集まりが多かったのかと感じました。
ここで取り上げられているような内容は実践をしていることももちろんふくまれるがいったんゼロに戻して参考になる点を抽出することで、次の一歩が築けるのではないか?と思います。
我々の会議もカルロス流に学んでみたいと思いました。
高橋清志
なすの斎場グループ
【7月オーディオブック】
日産驚異の会議。カルロスゴーン公認を聞いて。
世界的に有名な大企業の会議の在り方、行い方を説明してくれました。
議事録を作らない会議。意思決定権を持つものを入れない会議。様々な様式の会議の内容がありました。
確かに意思決定を持つ方が会議に入り意見を述べたなら大企業であればあるほどNoを唱える人はいなくなります。
これが多種多様に渡って話し合いの出来る環境で会議が出来たなら、もっと様々な意見が出てくるのではないでしょうか。
なるほどですね。
赤羽根奈央子
なすの斎場グループ
課題図書
短い時間の会議で結論まで出す。長引く会議で結論がでないのは非効率、会議の意義が弱まる、モチベーションが下がるとありました。なるほどでした。せっかちな私にはぴったりな会議方法だと思いました。結論まで出される会議は次のステップに進めることがとてもモチベーションが上がりやって良かったと思える会議になるなぁ~と感じました。
宮内 佐知江
なすの斎場グループ
7月オーディオ課題
会議の手法によってその時間が貴重な時間になるのか単なる会議になるのか、とても参考になりましました。
日産独自ではあるかと思いますが、課題解決を時間をかけて行っていく姿勢を社員に浸透させていったこと、ファシリテーターを重視されていて、ファシリテーターの資質によって会議の成否を握るぐらい重要であったり、同じメンバーで会議をしないなど色んな手法の積み重ねで効率の良い有意義な会議になるのだと感じました。
午後5時までに結論が出る会議など時間を区切り課題を持ち越さないや、アイディアをぶつけ合いどの課題が解決に最も効果的なのな結論づけることなど日産の手法を参考にしつつその時の会議が何が重要なのかを考えて参加しなければならないと思いました。
大金久美子
なすの斎場グループ
7月課題図書
日産の改革にこんな会議があったなんて知らなかったです。
ファシリテーターを養成し、会議のやり方を決め、それを全社大で取り入れておこなったのはすごいと思いました。
特に記憶に残ったとこ
議事録はつくらない。
結論はその日中に出す。
決定権を持つ人間は参加しない。
日産立て直しと、合理的な会議の活用法があって、ためになった。
日産が会議を変えたのは、危機感を誰もが持っていたからだという部分。
現状に満足せず、危機感を持てるかどうかがポイントなのだと感じた。その会議がどれだけの成果を生むかを考えながら参加できるようにしていきたいです。
平山 智美
なすの斎場グループ
『日産驚異の会議』
日産の会議は、議事録を作らない。結論はその日に出す、決定権のある人は参加しない。会議の間は意思決定権者は参加しないで、最後に実行するのかしないのかを全員の前で決めるとのことで、そんな会議があることを初めて知りました。
どんな会議でも時間を使うので、予定外の議題を持ち出さない、積極的に聴く書く話す行動するなど。改めて、会議というものを振り返るきっかけになりました。
竹中紗智
なすの斎場グループ
7月課題図書・日産 会議
前置きを聴く中、どう会議に結びつく?と感じ、震災時、リアルタイムで日産工場の話を知人に聞いていたなと思い出しました。時間内に結論まで持っていく、現在行なっている郡山進捗ミーティングが浮かびました。限られた時間で予定した項目のみ社長がバサバサと結論までファシられ、これが社長不在のスタッフのみで出来るようになれれば会議やミーティングの効率が上がると思いました。せっかくみんな集まってるし、あの話しちゃおう!を辞めようと思います。今月もありがとうございました。
渡邊勇二
なすの斎場グループ
7月課題図書
時間に結論が出るという事は、その後の成果までの期間、効率やモチベーションにもつながる事で、その日の会議で結論を出すのは絶対だと思いました。
行き当たりばったりの会議ではなく、資料や進行なども予め考えられていて、長くなりそうな時の進め方も考えられていた。同じ進行で行う事も効率的な会議に繋がっていると思います。
時間内に結論を出す為の手法、なぜなぜの視覚化やポストイットブレストなど社内でもいろんな場で使えると思います。
意思決定者は会議に参加しないという点では、これはなるほど!でした。意見を言いやすい場作りもそうですし、意思決定者の時間拘束しないと言う点も時間の使い方、生産性の考え方に沿ってみても、そうすべきと思いました。
星 大地
なすの斎場グループ
7月図書
日産の会議で議事録を作らないのは凄いなと本当に思いました。
話し合った内容より、何をすべきかがやはり重要だなと感じました。
部分的な最適化だと、確執も産まれますしなにより組織間での感謝や共有も無くなり、衰退していくのだと思いました。
ティール組織の本が、僕のなかで一番良かった本で、そこになかなか結び付かなかったのですが進むうちに生命体のような流動的な変化をするには確執のない柔らかな組織であり、全体が常に変わるということなのだなと理解しました。
すぐに実践すると、ガタガタになりそうですが笑 少しずつ実践していきたいてす。
屋代 実沙紀
なすの斎場グループ
7月課題図書
大企業の会議、といっても色々なやり方があるのでしょうが、議事録を作らない・意志決定者が会議中は不在という点が画期的でこのような方法でも会議が成立するのだと感心しました。この本で解説されているような会議のやり方を導入するのは大変そうですが、ポストイットに意見を書いて出し合う、という方法はクレドワークでやっているので、チームミーティングの際などもやってみたり、すぐに取り入れられそうな方法もいくつかあるなと感じました。
渡辺悟
なすの斎場グループ
7月課題図書
聞けば聞くほど内容が難しくなっており、なんどか聞き返す場面もありましたが、
その中で驚いたこ会議があるそしてその会議参加する必要があるかないかの話からはじまるというところが驚きで、会議であったりミーティングっていうのは参加をしないといけないものという考えがあったので、斬新な考え方だと思わされました。
相馬 なつみ
なすの斎場グループ
7月課題図書
ファシリテータがいることよりもファシリテータが持つべき技術を教育していくということも大切なのではないかと思いました。
そして、日産自動車が、東日本大震災後の車づくりの体制復旧を他社に先駆けていち早く成し遂げることが出来たのは、日々積み重ねきた「日産の会議」のおかげだったのだと知りました。
日産自動車の社員が「V-FAST」と呼ぶ「日産の会議」の一つは、その日にはじまり、その日のうちに結論まで達する。そのため社員たちは、この会議を一日集中討議とも呼んでいます。一つ目は、会議自体を1日で結論を出す設定にしてしまう。そして、二つ目のポイントは「明確な課題の定義と、適切な目標の設定をしておくことが重要なポイントだ」と気づき、今までのミーティングはその場で課題を伝えてそのことについて話し合っていたので、その日のうちに答えは出ていませんでした。会議の質を上げるために事前に課題を共有していこうと思いました。
藤田 裕子
なすの斎場グループ
7月課題図書
大企業の日産の会議では、議事録を作らない?会議手法があり 無駄をなくし課題解決をしていく。他部署メンバーでのチーム編成、キントーン室でもやっていたのでこれはいいい事だと改めて思いました。時間を書ければいいものではない、予定と違う議題を話さないなど 大企業でできていることだからこそ 出来ている成功している秘訣を真似して、より良いPDCAを回し会議環境を作ろうと思いました。
相馬親太郎
なすの斎場グループ
7月オーディオブック
意思決定者が参加せずとも、会議参加者の役割がそれぞれ明確になっており、より高度な会議になっていると思います。その中で、ファシリテーターの重要性を強く感じました。私の場合は、話しを円滑に進めるのが役割と思っていましたが、ファシリテーターが回りの意見やアイデアを引き出すことが本当の狙いなんだと気付けたことは学びになります。ファシリテーターのレベルで会議の成否を左右するんだなと思いました。他にも発言の責任は、誰ということでなくリーダーにあるというのは、リーダーの考えがチームに浸透している証でもあるので、自チームに生かしていきたいと思います。日産独自の心構えやルールがあり、覚えきれなかった部分を今一度、再聴、文字で確認していきたいと思います。
高橋嶺太
なすの斎場グループ
7月課題図書 (驚異の会議 改革の10年が生み落としたノウハウ)
意思決定者が会議には出席しない、
という考え方に驚きました。
会議の最後に出てきた提案の採用、
不採用を決定するだけ。
これは私の見解ですが、
なるべく社員の考え方、意見を
会議に取り入れることは大切ですし
どの会社にも必要だなと思います。
日産という、大手の会社でも、
このような手法を使っているんだなと、
会社の大小に関係なく必要な考え方だなと思いました。
1
村上絢美
なすの斎場グループ
7月【日産 驚異の会議 改革の10年が生み落としたノウハウ】
会議の時間がだらだら続くと集中できないので短い時間で集中して行う『集中講義』当たり前のこととは思いますが、難しいことだよなーと思いながら聞きました。ポストイットを使用し司会進行が進め、書いた人など、繰り返し話して、その会議中に解決まで進め、結論もしっかり当日中にすること、この本を参考に今後の会議を参加しようと感じました。
櫻井 裕子
なすの斎場グループ
7月
会議、ミーティングも含め、ついつい本題から話が逸れて時間が過ぎ、結局、何も決まってない、進んでない事があったので、まとめる人、進める人の役割は大きいと思いました。事前に何の議題について話し合うのかを提示し、会議までにそれぞれ考えをまとめておいてもらう事前準備は必要ですし、意見しやすい環境作りも必要かと思いました。時間配分なども含め、意識して参加する側もお客様ではなく、積極的に意味のある会議、ミーティングにしていく為に学び直したいと思います。
月井 優二
なすの斎場グループ
7月課題図書
通じて感じた事は良い意見を出すには偏見・先入観・固定概念を持たない事なのかなと。これを実行するにはルールが必要だ。更に質を向上、円滑にするには参加者の役割が必要だ。それが日産の会議なのかなと。
参加者の選任とルールが肝と感じた。正直ルールだらけの会議では意見も縮小してしまうと感じるが、これを不服と感じず環境の喜びと感じられる参加者の選任。
今感じる部分は少ないが、これから今回得た事を良しと感じる事はあるのだろうか。
1
高橋 真人
なすの斎場グループ
7月オーディオブック
長くてなかなか進まないこともありましたが、とても実用的だと感じました。
特に以前2回ほど集中討議?については社長からお話があり行っていたので、「これはあの時のミーティングの進め方…ここから来ていたのか!」と身近に感じることができました。
大会社でも一人が3件4件の案件を並行して持っているということも、なすの斎場のようだと少し親近感がわきながら聞き進めることができました。一番印象的だったのはやはり震災の話と、そこからの復旧に関するミーティングや進め方がストーリー仕立てとなっていたので面白くもあり、なるほど、と思う部分でした。リーフの話も「新規事業」などの観点では考え方としてとても参考になりましたが。
手始めに3日から本格始動するブリッジ会議episode2でも日産の会議方法を存分に生かして参加していきたいと思います!Vクルーとして!
寺門 大輔
なすの斎場グループ
7月オーディオ
内容で特に気になったのは、クロスファンクショナルチームという会議方法
なすの斎場では会議・ミーティングというと、CRM・施行部プランナー・施行ディレクター・施行パートナー・生花部と、小さくまとまってしまう印象を受けていた もちろん、各々の部署では最善を尽くしているが、「部署による最適」が「会社にとっての最適」と必ずしもイコールではないという指摘は新たな知見を得たと感じた
高級喪主花の販売や、電話での事前相談、初盆受注体制など、各部門の垣根を超えたワーキンググループの設立も、新たな分野の開拓に繋がるのではないかと感じた
1
宮本法子
なすの斎場グループ
【7月課題図書】
仏の顔も三度まで、そう自身に言い聞かせ取り組んだオーディブルでした。まだまだ慣れませんが、内容の難しさに、より自身を奮い立たせた図書でもありました。
会議のルールでは、お客様が商品を購入するに至るまでの段階を示し方策を考えていくという衝撃的な内容でした。葬儀という1つの商品を購入する上でどんな段階があるのか、それを元にどんな方策があるのか。ポスティング、ラジオ出演など現在広告として打ち出すもの以外に何があるのか。マーケティングなどの部類に入るのか、今の自身の立ち位置では分かり得ないことがあるのか、新しいテーマを打ち出されたような感覚でした。
1on1同様に取り組みあたり必要なもの、本書ではグランドルール。当たり前のようで、実践に結び付けるには、気持ちと行動が一致しなければできないこと。積極性、建設的など自身に足りない物を再確認したように思います。大きな変化は、何のために必要なのか、それを実行するためには、携わる皆が危機感持つこと。それは置かれた状況によらないことなのだと理解しました。頂く仕事が当たり前だと思わず、奢らず、常に感謝を持って取り組んでいきます。
その会社にあった手法を取り入れる、それは様々な手法を理解した上で選択できるものです。現在の状況が“井の中の蛙大海を知らず“になることのないよう、足元をしっかりと固める力と知識を頂きました。毎回大切な気づきと、それを提供して下さる社長には感謝します。