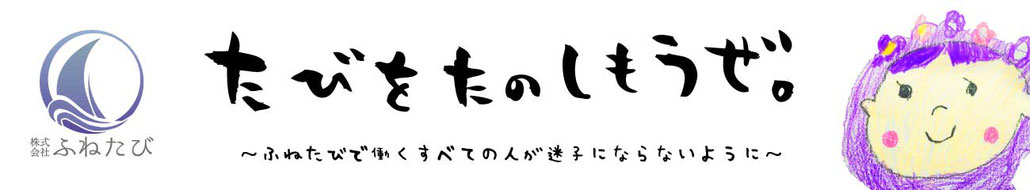【10月課題図書】
苦手なカタカナ用語や、計算イコール数字のイメージで戦略思考に至るまで時間はかかりましたが、とにかくワクワク感がありリズミカルな文章に、理解できなくとも理解できたような感覚で読み進めることのできた図書でした
数字は嘘をつかないと聞いたことがありますが、大切なのはその過程と手法だと感じました。大前提としてある議論。そのために幅を増やす手法。幅を示すことで地に足を付けた議論ができる。幅とは何なのか、それぞれの説明が分かりやすく理解することができました。また“ドリブン”や“スコープアウト”などなど都度出てくる苦手なカタカナ用語も調べ、また1つ大切な理解をすることができました。
100問挑戦前に「僕らは命に嫌われている」を聞く人の割合を娘とともにトライしました。即答は40億人。命があるのは今生きている人全員(世界人口80億人?外国の人も含めますか?)、スマホがあれば誰でも聞ける(スマホの所有率?スマホが使用できる環境?スマホ以外の機器の所有率)、趣味を持てる時間(隙間時間は?寝ないで働く人の割合?ニートは一日中聞けるかも、働き方改革?)など多くの議論が交わされました。議論は他人の考え方を知ることで自分の考え方にも幅を持たせることができます。そして何事も試すことは変化を好み成長にも繋がります。
実際の仕事現場で何をどう活かせるのかの答えはでませんし、お題に対してフェルミ推定とコンサル面接のようにスラスラ答えがでません。しかし提示されることで取り組む必要性を理解することは成長に繋がります。毎回大切な気づきとそれを提供して下さる図書と社長には感謝します。“思考停止せず、変化する社会に楽しんで立ち向かう”ことのできるよう創造性を育む努力をしていきます。
【10月読書感想文】
フェルミ推定の技術、読み進めていくうえで感じたのが8月に読んだ、仕事が速い人は、「これ」しかやらない ラクして速く成果を出す「7つの原則」
の内容に似たような考え方ロジックの組み立て方について深く追及されているなといった印象を受けました。
答えのないゲームをゴールとし因数分解によって細かく分析していく、ゴールまでの道のりを自身で分析し最終的に辿り着く!まさに冒険をしているような考え方を持つことによって思考することがどんどん楽しくなってくる。まさにそういった内容でした。
自分もそんな風に分析、理解できるようになったらそれもまた楽しいかなと。
事業を進めていくうえで絶対的に必要であるのは数字ではありますがこれらには絶対という数字はない、そこをフェルミ推定によって分析予想することによって先を見据えることが楽しくなるのではないでしょうか。私たちも数字を求められる事がある業種で仕事をしています。
この本の内容通りに因数分解はすらすらと出来るのは難しいかもしれませんが少しでも使えるよう実践に織り交ぜていきたいと思いました。
10月課題図書
フェルミ推定の技術を読んで、私にとって今まさに必要な言葉がありまりた。印象に残った言葉で答えの無いゲームの時代に突入してしまった。未知の数字を常識・知識を基に、ロジックで計算する事。今のマネジメントをするにあたって必要な言葉です。答えの無い戦い方、そしてそれに慣れていく必要がある。ビジネスに必要な武器を!
全体を通して算数の勉強をしている気分になり初心に帰った気持ちになりました。内容として同じ内容が繰り返し書かれているが、何度も復習が出来る本ではないでしょうか。ただの算数ではなく、意味のある内容でした。この計算式を参考に実際の現場で使われるマネジメントに当てはめていこうと思います。全てが数字で結果が出せますのでロジックで計算をする意識付けにいいでしょう。
【10月読書感想文】
数年ぶりビジネス書を読む機会を頂きました。明確な答えはそれほどないものの、たくさんの例題を用いて解説しているのは私の固まりまくった頭を柔らかくしてくれました。答えが出ないものに強い思考力を持つこと、一読して感じました。
「知らないこと、まだ知られていないこと」これら未知数について、明確な物事を進めるうえで頼りとなるものを与えるものである、ということ。
相手とお話をする時に、どのように考えたのか?それ以上に、どう伝えるのか?どう伝わったのか?に重要性があって、このフェルミ推定は自分が考えた筋道とそれまでの結果を相手にどこまで分かりやすく伝えるかの反復練習になるし、勉強になりました。
10月課題図書
一番最初、常識・知識を元にで世の中の仕組みについてどれだけ知識を持っているかが大前提(重要)、思考が深い人は得てしてお話しするのが苦手…なるほどこれはすぐに人物が浮かび納得。過去に読んだ図書での「なぜ?」がこの図書だと「気持ち悪い」になり各図書のフレーズが気になった。
正直難しかったが本の感想だが、理解しましたとは言い難い。九九のように繰り返しで体に覚えさせるしかないかと…100問…やりますか…
10月課題図書
この本でフェルミ推定という言葉をはじめて知りました。読んでいくうちてにフェルミ推定とは何なのか知り奥が深い算出方法ということが分かりました。正直、未知の数字を算出する内容は私には難解でしたがその中でもまだわかりやすかったのがコンビニ1店舗の売上を解く開発店長の気持ちの項目でフェルミ推定は算数ではなくビジネスであると記されていてなるほどと感じました。乳母車の算出例も購入する対象を1人目と2人目では違った分析の仕方で2人目は新品にこだわらないなどフェルミ推定の現実投影の部分を考慮した計算方法があり面白いと思いました。フェルミ推定を鍛えるためには因数分解を鍛え話し方、値を鍛えるそして丸暗記が最も効率的と記されていたのですべてを暗記は無理でもわかりやすい例えの算出方法は覚えてみようかなと思いました。
10月課題図書
フェルミ推定?なに?から始まりました。視点を変えながら考える事でいろんな仮説から答えの無いものに対しての類推を行うための考え方として存在するフェルミ推定。
いろんな方向で分解していく必要があるため、やってみたら分かるのでしょうが、かなり難しいと思います。ただ、回答がずれていても考え方の大元が合致すれば、ゴールが同じであれば結果良いのだと思いました。考えて組み立てを間違えないよう、数字に対しての意識を大切に、数字を苦手と思わないようにしないとだめだと、反復練習・・・読み終わって自分に必要なものだと感じました。
10月課題図書
本を開き、本題に入る前からワクワクしてしまう「はじめに」があるのかと思い知らされました。読み進めていくと私は完全に因数分解バカの部類でした。しかし、フェルミ推定は鍛えることができると書いてあって安心しました。フェルミ推定では物をさまざまな視点から考えることができ、発想が豊かになっていくと感じました。答えのない話をするというのはとても苦手ですが、逆に答えのない議論をするというのはとても面白いと感じました。なぜなら、答えのない議論をすることで相手の思考も自分の引き出しの一部になり、フェルミ推定に加えることができると考えたからです。フェルミ推定というものはビジネスから日常まで、全てに使えると感じたのでもう一度読み直し、フェルミ推定を自分のものにしたいと思いました。
10月課題図書「フェルミ推定」
ロジカルシンキングを超える戦力思考、フェルミとは何なんか?題名から気になり、話し手口調だったのもありシンプルに面白かったです。答えのないゲームに重きを置き、いかに現実を投影するかが重要であることを感じました。業績でストレッチ目標を立てる際、フェルミ推定をしっかり活用していこうと思います。まずは100問反復練習ですね。ちょっと検索してみましたが・・・身についたといえるまでは道のりが長そうです。また話し方(説明)のところで論点を話す話し方があがり、わかっているけど使い切れていない部分なので今後も意識していこうと思いました。
10月読書感想文
「フェルミ推定」難しいが好きです!
因数分解をするにしても、何に着目するのか、他にプロセスがセクシーになるすべがないかと、常識、知識もそうですが想像力大事だと思いました。
考え方を理解したつもりで例題をまず自分ならどう考えるかと、後半はまず自分の答えを出しながら進めました。結果「気持ち悪くない」と自分では思っても解説を読むとなるほどなと。1%で大きな差が出たり、因数分解が浅かったりで値が全く変わってくるので、重要数値で即実践は難しいですが、まずは気持ち悪さに気づき、1つの事にも他のアプローチはと自分に問いながら鍛えていきたいです。
答えがないとされてますが、個人的には答えはあると思ってます。
10月課題図書感想
今回のフェルミ推定は私としてはとても馴染みの深い内容でありました。これはロジカルシンキングを構築していく為には、とても必要な考え方であり、先生に教わり、中学の時に同級生と良く似たような問題を出して遊んでいました。この考え方により、全く知らない問題に出会っても、初見で分からないで終わる事は無くなり、細かく分解して、整理していけるようになりました。正解かどうかが重要では無く、どう辿り着くか?どう考えたか?どこの材料、要素を引っ張ってこれるか?30後半になっても、まだまだトレーニングの日々です。他にも私は、演繹法と帰納法等組み合わせて日々色々な事を考えております。本日のぼくおばMVPでも、聴きながら、四例をそれぞれパターン分析してまとめておりました。
本題に入りますが、読んで知識にするだけなら意味が無いので、読みながら、どう今の仕事に活かそうかなと考えた時に、フェルミ推定自体ではそのまま利用は難しい‥ではロジカルシンキングで当てはめると、儀典の進行では難しい‥‥。でもプランニングならばロジカルでお客様の不安を、この本的に言うと因数分解、つまり紐解いていける!!
家族カルテでも同じ事だなと感じました!漠然とし過ぎていて、不安なお葬式を細かく篩い分けして、不安の明瞭化、言語化をしているなと!
次にスペシャルに対してですが、私は最初は葬儀屋なのに、こんな事をしているなんてと驚愕でしたし、そこに感銘を受けました。とても自由な発想だな!ロジカルでは無く、凄くラテラルシンキングな会社だなと思っていましたが、実際はお客様の家族関係などの背景や想い、色々なバックグラウンドを元にクレドに沿って、ロジカル的に構築して形にしているわけでした。たまにあるユニークな発想は、少しラテラルかもしれませんが。
まとめますと、フェルミ推定、ロジカルシンキングとは、これまでの仕事では数字を追ったり、人に教える、解説する等、考え方の1つとして当たり前のように使ってきましたが、葬儀社に勤める者としても、いくらでも活用出来るなと思いました。現時点ではそもそもフェルミ推定、ロジカルシンキングを行えるだけの材料、知識を持っていないので、早くそこを補えるように努力を怠らないようにしていきたいです!
【10月読書感想文】
=答えのないゲーム。今まさに私が取り組もうとしている業務に直結するような内容で、今後の取り組みにとても生かせる考え方だなと思います。リーダー研修でも学びましたが、私は物の考え方が雑でしたが、【因数分解】の考え方、数字だけでなく行動も因数分解して考えるということやプロセスについて、結果ばかりを気にしてしまっていたが、答えよりも考え方が重要など、参考になることばかりでした。ただ、もちろんそこに知識や知恵の重要性も説かれており、内容としてはわかったつもりではあるが、すぐにできるとは思わなかったので、本書はあと数回、読み直すべきだなと思います
10月課題図書
フェルミ推定を読みましたが、難しいですね…。実際に業績目標をたてるためにどのように活かせるのか、答えが出ないものに思考停止せず向かっていけるように、数字への意識を持てたらと思いました。また、話し方のところで、私はこれも苦手です。声に出し読み返して口が覚えるイメージでやってみたいとおもいました。
【10月課題図書】
フェルミ推定は、あるビジネスの市場規模はいくらかなど、明確な答えがないものを論理的に答え(数値)を出す手法…。少々チンプンカンプン過ぎるので、本書にある通り「私はフェルミ推定の王になる」と覚悟決めてもう一度読もうと思います。この手法を理解出来たら、苦手意識が強い(数字)と仲良くなれそうです。スキルと同じで繰り返すことが大切だと思うので、手法を取り入れていけたらと思います。
課題図書
フェルミ推定難しい~、聞きなれない言葉ばかりに理解できたかというと理解出来ない…。その中でも取り入れられるものはないかと読み進めました。
日々行う「作業設計」「工数設計」も実はフェルミ推定とありました。ふだんの自分の業務に置き換えやすくここが一番わかりやすかったです…。
何かつまずきヒントがほしい時など開いてみると因数分解を使って解決に導いてくれそうだと思いました。
10月課題図書
フェルミ推定?初めて聞いた言葉…読書は嫌いじゃないけど、初めて手にするビジネス書…。うーん、難しそう!レオパレスの本棚に置くと、そこだけ異次元してくれるほどの存在感。そう思いながら読み始めました。
読み終えた感想としては、一度読んだだけではよく分かりませんでしたが正直なところです。ただ「これ、郡山の新規出店で相当使えるんじゃないの」ということは理解できました。
読みながらツッコミを入れたのは“結婚していて子供がいる家庭の炊飯器の耐用年数3年”…いや、そんな訳ないでしょ!(P79)、マッサージチェアの市場規模が左ページでは60億なのに右ページに行くと30億になってる!なんで?どうして?(P 58、59)
つまり、そのくらいアバウトでいいということなんですね。
フェルミ推定の王になるには道のりは遠いようですが、今後読み返す機会があることを確信しました。
10月 課題図書
本を開いて最初の感想は、数学の教科書みたい…でした。最終的には興味深く読み進められましたが、最初は難解に感じ、とりあえず第1章を何度か繰り返し読んでから先へ進んでみました。調べても答えのない、未知の数字を探求する。100問それぞれ面白そうな出題ですが、計算式を作るにしても、その分野について必要な知識を持っていなければ適切な式を導けないと感じました。
フェルミ推定をマスターすれば、その道中で磨ける技術は沢山ある…道のりは長そうですが、定期的に読み返したり100問について考えてみたいと思いました。
10月課題図書
フェルミ推定と言う言葉を始めて聞いたので、最初は何それ?と思いました。
答えの無いゲームで勝つためのスキルが求められている、それがフェルミ推定だと知りました。フェルミ推定とは①未知の数字を、②常識、知識を基に、③ロジックで、④計算することでした。そして、私の苦手な因数分解でした。因数分解を2つ以上出し、最良の方を選択する。難しいけど、出来る様になれば業績にも繋がる考え方だと思いました。
【10月課題図書】
読み進めての第一印象は「難しい」…なので、章ごとに繰り返し読み進めました。業務での大切な事は結果と思いがちですが、本書ではまったくの逆でした。答えの無いゲームなのだから因数分解、知識の置き方で出た答えは素敵。大切なのはプロセスだと。研修の際ノルマは無い。その代わり段階にあるプロセスが大事です。と伺いました。まさにフェルミ推定だと思いました。本書を100%理解できたかと言われるとできていません。100問で素敵な答えが出せるよう繰り返し読み進めていこうと思います。
【10月課題図書】
初めは拒否反応が出ましたが、(セクシーな因数分解)の仕方のバスケットボール人口の話で少し楽しくなりました。因数分解をする時に、何の数字で計算するのか?と考えたらポンコツ因数分解にならぬよう、分解していき、この数字はどうやって出したのか?何の数字を掛けるのか?など、なぜ?どうやって?と思ってましたが、ざっくりした数字を置いていきながらセクシーな因数分解の紹介がイメージがつきやすかったです。
答えが無いのだから、プロセス、比較、議論の言葉が印象的でした。
10月課題図書
呼んでく中で最後の100本ノックの話が印象的でした
自分でやるとできない、と痛感して考えさせられました。
未来推定したKPIの話はすごく勉強になりました数値に落とし込んだりするとよりわかりやすくなり現実が見えやすくなると思い勉強になりました。
10月読書感想
読む前にさーっとペラペラめくりました…。「む…難しいかも…」と思いながら読み進めました…。フェルミ推定は答えのないゲームということ、答えがないのだからプロセスが大事。思考停止をせず変化していくことに楽しんでフェルミ推定をしていきます。来季の業績OKRの目標を立てるのに役立たせていただきます。
10月読書感想文
フェルミ推定、という言葉にはまったく馴染みがありませんでしたが、例題にもあった「マッサージチェア」の話から、ケース面接で学んだことだと気づいた
OKR設定で求められる「数字出し」のロジックの組み立て方が参考になり、またそのロジックを「腑に落ちる」ように説明するところまで言及されているのが魅力的だった
一見荒唐無稽な「ロジック」であっても、「まず、〜とする」というところから先ずは取り組み、そして納得させるまでの着地点が大切であること、そして元となる実数値は確実であること、この2点を抑えることをこの図書から学びました
【10月課題図書】
非常にわかりやすく、実践してみる意欲が沸き上がる良本だと感じました。お葬式の中で初めてお会いしたご遺族様は当然知らない人です。その中で、お葬式を必要としている人とお葬式を提供できる人、という薄い関係性で繋がっている状況で、太いラポールを短時間で構築するためには、仕入れることができる可能な限りの情報と危険の伴わない仮説をたてることだと信じ、実践してきました。人の平均寿命・がん患者の年齢別平均進行スピード、病気別入院日数、、、etc。もともと仮説を立てることが好きなタイプでしたので、腑に落ちる表現・技法が満載なフェルミ推定を深く理解し今後に繋げていきたいと思います。
10月課題図書
フェルミ推定を読んで、ロジカルシンキングを行うだけの情報収集を行うことの重要さを感じました。
私はWEB業務を少し行わせていただいておりますが、ロジカルというかクリティカル的な考え方になっている部分がありました。
どうしても否定的に考えてしまい、なにかを勧める躍動性に欠けてましたが弊社では推進力が重要でもあるのでロジカルに、斬新に、効率的に今後は動いていきたいと思います。これからシフトを作成することも増えてきますが、そのなかでも固定できる業務の時間など個別に設定できる部分を考えていきたいです。
10月課題図書
ロジカルシンキングを超える戦略思考 フェルミ推定の技術
コンビニやマッサージ機など未知の数字を導き出すためにする因数分解も、数字がすんなり入ってくるものと?となるものがあり実際に業績目標設定でこの考え方はとても分かりやすかった。
今回この本は何度か読み返していますが、私にはまだまだ足りないようなので都度読み返してこの思考を取り入れていきたいと思います。
10月課題図書
難しいなぁ…と頭に入りずらいなか、なんとか読み進めてみていましたが、福山雅治さんのギャラを考える。のところで面白くなって、その後は比較的入り込みやすかったです。
そして読み終わってからはこれはまさにこれからの自分に必要な本で、全くの未知のエリア、未知の環境へ出店していくにあたり、必ずやっていかなくてはならない考え方が詰まっていたなと後になりかんじました。
予想立てる、推定する、推し量る。わからないものをわからない中で、それでもやらなけらばならない時にどう道筋を立てればよいか、その参考書としてぜひこれからも何度も読み返していきたい一冊になりました。