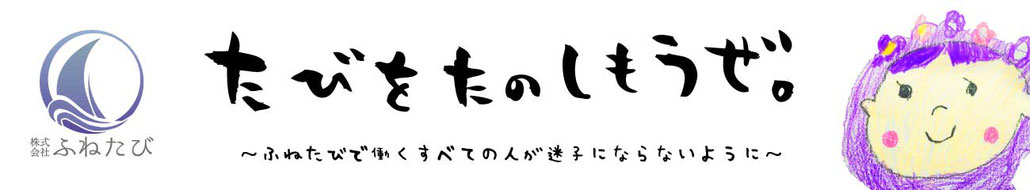【12月課題図書】
“成長のマインドセット”とは初めて聞く言葉で、成長と固定された概念などが何にどう影響していくものなのか、本書の目的がどこになるのかを確認しながら読み進めた図書です。
成長は自分の人生と向き合うことと本書では定義されていましたが、自身としては自己覚知して自分らしく生きていくものだと思っています。自分あっての他者なのか、他者あっての自分なのかという議論もありますが、本書での成長の過程図はまるで、マズローの欲求5段階接に似ており、自己あっての成長が基本、とより深く考察できました。また、嫌なことはその日のうちに忘れる努力をしていますので、(努力なしに忘れてしまうことも多々ありますが)自分自身に“心のブレーキ”を感じたことはありませんでしたが、それでも忘れられないことの塊が“心のブレーキ”であることを理解しました。理解より実践、心のブレーキを踏まない覚悟と、自己を知ることはどこまでも核になることだと感じました。
国会中継などでは“責任転嫁”に似た光景が度々見受けられますが、社会、会社、学校、家庭、どの場面でも当事者意識を持つこと、責任転換しない場面が増えたら良い。それは “自分の身に起きたとことは全て自分の責任”そう言い切れるか、との自分への問いにも繋がりました。また、“自分は何のために働くのか”その答えがビジョンスケッチに描かれる未来なのかと創造しました。
愛の反対は無関心。子育て同様、チームでも会社でも、常に無関心にならないように、今一度気持ちを引き締められた思いです。いつも大切な想いを気づかせてくれる図書と社長には感謝します。伝え方の下手な宮本ですが、適切なブレーキの外し方を実践していきます。
【12月課題図書】
心のブレーキの外し方、人が成長することとは何か?個人により無限の成長があります。
仕事が出来たとき、自分の夢がかなったとき等様々な要因によって成長を感じられる事があると思いますがこの本の内容で触れられていたことはそれらの成長の過程でブレーキをかけてしまっている、そのブレーキとは何なのか?またそれらを外すためにはどう行動すると良いかなどアイスバーグ理論、氷山の頂上(今自分の見えている部分)は理解しているが、海の中に沈んだ部分はみえません、見えないからこそそこで心のブレーキがかかってしまい前に進めなくなり成長のスピードを遅くしてしまっている。なるほどです。
【12月課題図書】
心のブレーキの外し方を読んで
成長をするためにはどうすれば良いのか、読みながら意味を理解しながら読ませていただきました。分かりやすい表現をすると答えを見つけるのではなく、自分が現在どの位置、または時点にいるのかを見るために参考となる書籍でした。仕事、人間関係、自分のやりたいこと等考え方が少し変わった気がしました。心のブレーキにて前に進めない。分かるなーで思いました。
12月課題図書
この本では信念や価値観、判断基準がマインドセットと言う意味とか書かれてありましたが、仕事や生活でも自分の中で判断基準や信念の軸があったら迷ったときに考えを明確に出来るのだろうと感じました。アイスバーグの図は成果に対し見えない部分で結果を出すためにどんなスキルで取り組んでいるかを知ることの大切さ、最終的にアイスバーグを大きく成長させて未来イメージを湧かせる、図に書き出すことで整理が出来るのはわかりやすいし自身の成長のためにも意識づけを参考にしたいと思いました。マスターの人生哲学、ポリシー、行動指針で書き留めてある言葉の中で結果は選択できないが行動は選択できるというフレーズは自分的にすごく響きました、自分の身近にもマスターのような利害関係がなく迷ったときに相談できる人がいたらいいなと思いました。
12月課題図書「成長マインドセット」
改めて成長とは何か?を考えさせられる本でした。自分が変化できること、レベルアップすることに喜びを感じますが、何か上手くいかない時などブレーキを踏みながら進んでいるなと本書を読みとても痛感しました。気になり出すといろんなことが気になり、アクセル踏みながら結構なブレーキを踏んでいたなと。ブレーキを踏まないためには期間限定、2年という判断基準も書いてあったので意識していきたいと思います。またマスターの哲学・行動指針の1つの「人生我以外皆師なり」私も好きな、実践できるようにしている言葉の1つです。他にも軸にしている言葉があるのでブレない軸、自分軸として固め、アクセルを思いっきり踏み、アイスバーグ自体もを大きくさせて、成長していきたいです。
12月課題図書
悩みのブレーキの外し方や100%当事者意識をもつことが、成長するにあたってとても大切なことだと感じました。
行動は選べるけど結果は選べないという話も印象的でした。結果ではなくどのような行動をとるかに意識を持って動くべきと改めて確認しました。
誰かのせい、環境のせいにしていても状況は変わらないこと、悩みの解消も難しい。だったら、自分の行動に責任をもって動くべきと思いました。
12月課題図書 成長マインドセット
主人公へとマスターがアドバイスする形で話が進んでいきましたが、セミナーの様で内容が頭に入りやすかったです。
成長とは何か、成長するために大切な事は?という点を意識して読み進めまられました。成長を妨げるブレーキと促進するアクセル…私はどうしても躊躇してブレーキを踏んでしまいがちです。ただ、結果は選べなくても行動は選べるという事で、誰かに任せきりにしたり誰かのせいにせず、行動を自分で選択していく事が重要だと思いました。
12月課題図書
今月のオーディオブック【人の動かし方】を自分に当てはめて自己の成長が行動理由になると私の場合ブレーキが外れるかもしれない。その後は車が一度の給油で走れる距離が決まっているように、ブレーキを外して走る期間を決める事も良いかも。あとは自分の正しいアクセルの踏み方と場所の確認。
12月課題図書
成長の地図には3つの大切な要素が入っている。まず1つ目が「成長とは何か?」を知ること、次にその「成長を阻害する要因」と「成長を促進する要因」を理解し、行動できるようになることが大切だと知りました。悩みのブレーキは私も決断を必要以上に重く考えてブレーキを踏んでいると感じました。
結果は選択出来ないけど、行動は選択出来るので、行動できるようになりたいです。
12月課題図書
主人公を中心に進むストーリー展開は、感情移入が得意な私にとって一気読みしやすい図書でした。
意識や想い・人生哲学を大きく成長させることが成果に繋がることには納得です。能力やスキルを身につけることは大切であるこては間違いないことですが、そこだけにフォーカスすると深い闇に突入する経験がありました。成長=アイスバーグを大きくする。意識していきます。
2年間の期限設定はなるほどなーと感じました。まずやってみる!ですね。自責の考え方も腑に落ちますね。うまくいっていない時は、いつも誰かのせいにしていまた。私は自責100%で進んでいったほうが、人生楽しいと思います(^^)/行動あるのみ!心がすっきりする図書でした!!
12月の課題図書
とても読みやすく読め、府に落ちる感じがありました。印象的だったのは大きな子供の部分です。自己中心的、他者を理解しないなど自分も当てはまることもありますが、今までの経験を思い返してもあ~あの時のあの人は子供が出てきたんだなぁ~と理解出来ました。マスターの人生哲学の部分でも私も自分の軸となる言葉をかきとめておこうと思いました。マスターのようにいつもニコニコして人を包み込めるような人になりたいなぁ~と思います。
12月課題図書
成長するにあたってアイスバーグのピラミッドの全てが必要と納得。これを読んで思ったのは、やはり目標や目指すところは、自分の意思、想いで決めるものだと思いました。想いがあるから行動になり、行動により能力がつき、成長となる。結果は選べないので、まずは信念をもって行動できるかにあると思います。
自分にはこういう悩みがあるのだと認識する事、そこでブレーキを踏まないと覚悟すること、期限を設ける事。悩まず進みたいと思えました。
【12月課題図書】
成長と言っても、今までは自分自身が成長することだけを考えていましたが、今の自分の立場は、周りを成長させることも意識していかなければいけないと再認識させられました。仕事を行う上で必ず発生する【責任】ですが、個人的にまだまだ【当事者意識】が低い、義務的であったと思います。本書を機にあらためて責任の割合を高く持ち、自分とともにメンバーさんの成長にもつなげていきたいと思います。
12月の課題図書
悩みブレーキの外し方は参考になった。2年という期間限定でブレーキを踏まない覚悟をすること、100%の当事者意識を持つことは成長に大切なことであると感じました。
ついつい出来ない言い訳を探してしまうこともあるがそれでは何も変わらないし、悩みの解消にもならない。自分にできること、やるべきことは何なのかを考え、行動することが成長速につながるのだと思う。
ブレーキをかけてしまいそうになってもアクセルを踏んでいこうと思う。
12月の課題図書
前職にて主人意識という理念を掲げている会社があり、どういう意味か役職者に聞いた時、自身のやること全てに責任はあると思って仕事をすれば、対顧客・スタッフ間はもちろん良好になるし、経験値ももちろん自然にスキルも身に付く(吸収しやすくなる)無責任な仕事をしているままじゃ、いつまでたっても悪循環で経験値は0でその先ずっと下っ端のままだよと言われ、その言葉で火がついて仕事をがむしゃらにやった記憶があります。当事者意識を100%にするその文字を見て思い出しました。常に危機感を持ち、堕落(悩まない)しない、私は回遊魚。先日ドヤ顔を書いた後に本を読んでいたらBMVを言語化するとあり、当てはまってしまって思わず吹き出しました。回遊魚の様に止まらず進み続けたい…これが私の目指しているところだったのだと気付きました。ブレーキ…当事者意識…特にスピードが出ている時こそ、急ブレーキを踏んでしまう私なので、どこに到着したかったのかを常に覚えていようと思いました。
12月課題図書
まず思ったのはこんなカフェがあったらいいなぁということでした。仕事のことを相談したり導いてくれるカフェがあったら通い詰めてしまうかもしれない…と。
自分自身は個人的にあまり悩まない方なので、それが何で悩まないのかを理屈立てて教えてくれているようでした。いろいろな部分で学びがありましたが、特に「結果は選べないが行動は選べる」というのはまさにその通りと思いました。
またバリューが持つ意味 の章は、社長塾でもVMVを考える課題が過去にあり、自分なりに考えてみただけだったのでこういった考え方や構築の仕方というのはとても勉強になり、すぐに生かせるものだと思いました。
今月もすぐに活用できる知識、ありがとうございます!
【12月課題図書】
成長とはアイスバーグを大きくすること。そのためにブレーキを踏まないことと同時に、より自分を成長を促進させるアクセルとしての自分軸をしっかり持つことが大事。ブレーキを踏まない期間はオススメは2年ということで、泣いても凹んでもがむしゃらにまずは2年間は突っ走ってみようと思います。壊れたブレーキで廃車にならないように気をつけながら。
強い理念や軸があれば迷いが減って強く進むことができるとありましたが、この仕事に就いたことで自分のぼやけていた軸がはっきり見えた気がします。課題図書で新たな知識を得る度に、今の自分にできること、やらなくてはいけないことも明確になってきています。
12月課題図書
まず最初にタイトルを見て、心のブレーキという言葉がとても気になりました。読み進めていくと、ブレーキの存在を知るというというテーマがでてきました。実は最近ブレーキをかけていた時期がありました。その存在は今は明確になりブレーキは踏んでいません。本にも書いているように小さな悩みを一生の悩みのようとらえていました。そして大きな子供ブレーキ。。。直感ですが、まさに自分だと感じました。現在子供を育てている身でありながら、自分が子供だということ、悔しいと思うことこそが子供なのだと感じました。心の子供を育てながら頑張らないとなと感じます。自分自身が成長したときに新たに生まれ変わる気がします。この本を読んで自分のことを追求していけそうなのでほんとによかったです。
12月課題図書
自分自身がマスターに仕事の相談をしているように思える読みやすい本でした。
ただ単にアイスバーグモデルが大きければいい、大きくすればいいという訳ではなく、成果とスキル・能力がいくら備わっていても、3つの層バランスが大切だと学びました。
80キロのアクセル、80キロのアクセルとブレーキの絵を見た際、仕事の成長を妨げてしまう要素だと思いましたが、実際に悩みのブレーキでありとても納得できました。私自身かなりネガティブ思考なブレーキを踏みがちなので、それらのブレーキをしっかり取り払っていこうと思いました。
12月課題図書
「悩みブレーキ」「大きな子供ブレーキ」感情で動いてしまいやすい自分にとっては、耳が痛い話もありました。踏む必要が無いときに踏んでいるブレーキがどこなのかわからないときは、行動してみれば良いということかな・・・??もう一度、読み返してみたいと思います。ブレーキをかけないようにしよう、と意識するより、アクセルをどこで踏もうか?いつ踏もうか?と考えられるくらい、前向きで広い視野が今の自分には必要だと思いました。
12月課題図書
成長マインドセット
文字と説明図がわかりやすく書いてあり 読みやすかったです。当事者意識の違いの所も読んでいて他人事じゃないな・・・自分もリーダーとしての考えに結び付けてみよう。と思いました。アクセル踏んでブレーキ踏んで、それを続けると壊れてしまう、当たり前じゃんと感じましたが きちんと頭を整理し 悩みをきちんと解決し 進むためにアクセルを踏む。バランスが大切。最近いただいている本は 本当になすの斎場で生かすことが出来るためのが多いので自分に置き換えることも出来るので考えさせていただけるものだとありがたいものと思って読むことが出来ました。
12月感想文【成長マインドセット】
遅くなり申し訳ございません。
自分のアイスバーグをバランスよく大きくすることが成長という事でスキルを身に着けることだけではないという事を知ることができました。悩みのせいでブレーキがかかると成長が止まってしまう、これも読んでいてわかるなと思いました。その中でも自分が悩んでいることを認識しブレーキを踏まないように意識しながら自分がコントロールできる影響の輪にだけ集中しようと思います。
12月課題図書
大きな子供のブレーキ、私には無いなと思いました(笑)
逆に、私には知識も特技もなにもないので、大人のブレーキ外すだけでも会社に入社して勤められるんだと感じています。
プライドや、自尊心などブレーキの要因は多々ありますが、勘違いだけしないようにしたいです。
私も自分が多少パソコンができると思っているだけで、WEB担当者になったときに船井の水島さんにズタズタに裂かれましたが今となってはそれが無ければ船井さんに取り上げられるWEBマーケティングはできなかったです。
ときに絶望も後の飛躍のバネにすることが重要ですね!
12月感想文
遅くなりまして申し訳ございません。
正直に話しますと、貰ってすぐに読み始めたのですが、最初の方の章で納得いかなくて12月の途中で一度読むのやめてしまいました。理想ばかりで、すごく綺麗ごとに感じてしまったからです。昭和の根性論に近いなとの第一印象でした。ブレーキを理解して、踏まない覚悟を決める。それは理解しました。しかし、個人ではどうしようもならない外的要因が多すぎる、とても小さな組織ならばがむしゃらに頑張ってブレーキを踏まない事が出来るかもしれないが。本人の意志とは関係なく妨げられるはずだと思いました。部下の佐藤との面談も、問題をすり替えていて、とりあえず頑張ってみろと言われているような気がしてました。結果、部下の佐藤も半年後に就活していたわけで。もっと具体的な提示が欲しいんだよなと佐藤の気持ちになっていました。私自身、元からやると決めたら自分の選択なので全力で!やめるならスパッとやめる人間なのです。グチグチ悩む人が苦手で、悩む時間なんて勿体ない!即断即決でしょって思っていましたが、やらないでやめる、もしかしたらそれがブレーキの一つかもなと少し反省をして、再び読み始めました。読み進めていると当事者意識100%!すごく全力で行うにはいい言葉でした。今までも振り返ると、ダメな人はダメ。言っても変わらない。本人が考え方改めないと無理と切り捨てる事が多かったですが、その時点で当事者意識を全く持っていなかったなと、非常に自己中心的な考え方であったと猛反省しました。少しでもその人の事を思って行動していたか?自分のしたいようにしていただけではないかと過去の自分と話したくなりました。そのすぐ後に出てきた言葉で、結果は選択できないが、行動は選択できるとありましたが、ダメな人も色々手を尽くしても結局何も変わらないかもしれないが、変わるかもしれない。変わる為の努力をしてあげられたか、他人事だとどこかで思っていなかっただろうか?と責任に対する重みが理解できました。一社員での考え方ではなく、組織を生き物のように動かしていく歯車的な存在になっていく社員には必要な考え方でした。改めて、最初の佐藤との面談を見ると、上司は完全に当事者意識100%でなかった、どこか他人事な感じであったのだと。だからあんなに最初はこの本は参考にならないと思ってしまったのだと。しかし、そのあと上司も少しは変わって、改めて面接をして佐藤も理解してくれてめでたしでした。この本を半分読み進めてようやく、なるほどなと感じる事ができました。とても構成がうまいなと感じました。考え方一つで、人は変えられる!今すぐにでも出来る事なので、とても参考になりました。最後になりますが、納得行った今でも、やはり面談では具体的な提示して欲しいと思いました。