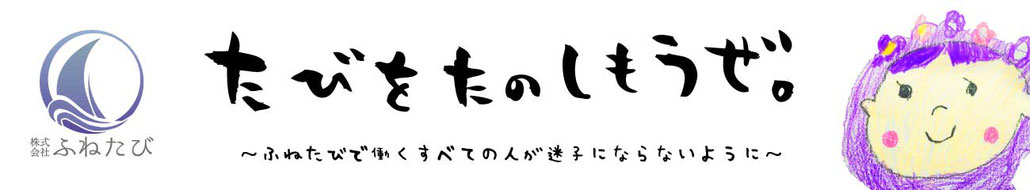【12月課題図書】
人を動かすために、人を動かす自分とはどういう生き物であるのか。以前フロイトと並行して議論したことのある課題図書。人は1週間後には約80%の記憶を忘れると言われますが、その通りで記憶を辿りながらも、新鮮な気持ちで読み進めることのできた図書です。
相手を動かすための手法、またその例がたくさん出てきました。実際にこれらすべてが実行できたのなら人間関係で悩むことを知らず、小さな不都合が世の中を大きく変えることもないのにと感じました。人はとても繊細な生き物故に、対処する方法、目的をもって自分を変えていく努力が必要。目的を持って自分を変えた行動が1つの成功にも結び付くものだと理解しました。
葬祭業は対人間関係から始まり、その関係が終りのない職業でもあります。当家様、御親族、ご会葬の方、また葬儀前の事前相談など関わる人すべてに関心を持つことから“ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式”が始まるのだと思います。時には不条理な発言、無理な要求、要請など多々ありますが、自然と本書のことを実行に移しているプランナー、ディレクターさんの行動が目に浮かび、お客様の考え方と要求に共感しているとはこういう事かと体感しました。また、北風と太陽のような葬儀も思い返し、議論で人は説き伏せることはできない、大切な演出を実行できているなすの斎場のクレドはここにあるのだとも思いました。
自分の向かうリビドー(フロイト)がどこに向いているのか。常に自分自身の安定を保つフランクリンの改革法、ソクラテスメゾットなど多くの忘れていたことを思い出しました。本書の行動を実践できるのか、人間関係が上手くない自身にとっては多くの課題が残ってしまった図書ではありますが、“笑えない時は無理にでも笑顔を作る”その笑顔が卑屈になることのないよう律していきたと思いました。一定のリズムで大切な想いを気づかせてくれる図書と社長にはいつも感謝します。
【12月オーディオブック】
カーネギー人を動かすを聞いて。
笑顔を忘れない、人の名前を覚える、人の悪口を言わない等普通に生活している人間ならなんてことの動作の一つではありますが、
これらのオーディオの内容はそれらを行った場合周りの人間にどのように影響を与えるのか、また自身が成長していくうえでどのような影響が出てくるのかと細分化して説明されていました。内容としましてはまさしく「その通り」の一言です。納得しかありませんでした。
私たちは社会人でありますから出来て当然とは思いますが、意識しなくてもそれらのことが出来ているか?人を動かすには相手の言い分を全面的に聞く、否定をしない。正直難しいところもありますが意識しながら実行して人を動かせるような努力をしていき良好な関係を築いていきたいと思います。
まずは冒頭にもあった人の名前を覚えるですね。何万人は難しいので身近なところからコツコツと頑張ります。
【12月オーディオブック】
カーネギー人を動かすを聴き
こちらも非常に耳に入りやすい内容でした。タイトルだけ見ると、難しそうで再生押すのも躊躇いました。
人によっては当たり前の内容でしたが、知っていても実践できてないこと、若干内容がずれていたことも修正できればより良い方向に事が運ぶんだろうなと思いました。人間関係で悩まれている方は相当いると思いますが、目的をもって自分をかえた行動が成功に繋がると改めて勉強させられた内容でした。これができたおかげで回りのスタッフの対応が変わったとか、お客様に喜んでいただけた等
是非実践あるのみです。
12月オーディオブック 人を動かす
情けは人の為ならず、という言葉を思い起こしました。誰かを動かしたいと思ったら、自分の言い分ばかり主張するのでなく、相手の立場になって相手を理解することが必要。悪口・不平を言うのは以ての外。誰かを思いやって行動すれば、それが巡り巡って自分の利益になるかもしれない…
また、非難しない・関心を寄せる・名前を覚える、という点はお客様とお話しする際も心掛けなければ、と改めて思いました。
調べたら原書は80年ほど前に出版されたようですが、時代を重ねても人間関係に重要な部分は変わらないのだろうなと感じました。
12月オーディオブック 人を動かす
こちらの本は以前どこかで成功させたい人が読むべき本の中の1つでオススメされていたのもあり気になっていたものでした。読み進めてみると、対子供・育児だと出来ていないこと(ここが違うよと違うところをそのまま指摘してしまうなど)が多々あり反省しました。また今月の課題図書にも似たような内容がありましたが、人の身になることはやはり重要なのだと感じました。他人事ではなく自分事になるよう、改めてより意識していこうと思います。こういった自己啓発本を読むと毎回、全部が出来れば完璧なのになと感じますが、着実に意識しなくてもできることを増やしていこうと思います。
12月オーディオブック
1つの長い物語ではなく、1項目がとても端的なので短い移動時間にも聞きやすかった印象。人を動かすというかまずは自身のコントロールが大前提。利他的…効率重視でもそれが相手には心地よくすっと耳に入る言葉になる、タイトルの通り人の動かし方。相手の目的とこちらの求める事を繋げる、相手の興味のある事に興味を持つ、人の本質は自分の為にしか動けない、だから素直にしてほしいではなく言葉を考える。振り返ると過去に私がかけてもらった言葉は本当の意味は違うのかもしれない。本書で伝えている項目は多いがトークスキルとして難しいと感じる事は少ない、本当にこれが素直に言える人は素晴らしい、たぶん惚れる。
12月 オーディオ
この本を知るまでカーネーギーさんという人物は知ることはなかったのですが、特に印象的だった内容は微笑みの話ので顰めっ面をしていた夫が1日を不機嫌そうな顔をやめて微笑もうとき奥さんに微笑みかけを毎朝実行したしら大きな仕事や幸せが舞い込んだとうい内容でなかなか自分を変えることは難しいと思いますがこの旦那さんは実行に移したことはすごい勇気だっただろ思います。命令ではなく提案する、これをするな、あれをしろ命令するのではなくこんな風にしたらどうだろうか?これなら上手くいくかもしれないないやこうすれば良くなると提案をするのはどんな場面でも相手を尊重できる言い回しだと改めてきづかされました。相手の対面も保ちつつお互いがより良くすごせるような関係作りは心がけひとつだと感じました。いろいろ見つめ直す考えさせられる本でした。
12月課題図書
この本は読んでいて、痛いところを突かれたと思うこともありました。
人を動かすにしろ、人に好かれる、人を説得する、人を変えるにしろ、まず最初は自分から変わらないといけない原則からスタートしているというのは、この本が単なるノウハウではなく、自分の生き方見直すように訴えかけているように感じました。
人を動かす3原則、人に好かれる6原則、人を説得する12原則どれも大切だと思いました。
12月課題図書
自分がどれだけ相手に重要感を感じてもらえるかが大切だと思います。そのために承認欲求を満たすこと。そのための行動(他人に興味を持つことが前提)が「人を動かす」と認識。これは角度は違いますが自己肯定にも繋がるポイントだとアドラーを思い出します。その中で、当たり前のようですが、名前を覚えるなど、当たり前のことを当たり前に行うことの重要性を再認識です。そして、このことは過去の偉人といわれる方々が実践していたという裏付けも説得力に繋がります。こちらの意図通りに動かす。のではなく、こちらの意図を理解・共感していただき、自燃の状態で動きたくなるのがベスト。そのために相手を理解し、褒めることを実践していきます。
12月オーディオブック
【常に謙虚であれ】私も大切にしていることですが、これができてるようで、できていないと気付かされました。職場や家庭でも、これが徹底できるともっと円滑な生活になるんだなと思います。忙しいとつい、短気になったり、自分中心の考え、感情になったり、やはり良いことはひとつもないんだなとあらためて考えさせられました。もっともっと相手を思う気持ちを持って接していきます。
12月オーディオブック
分かっていても出来ていないことが多いなと思うところがあり、本当に自分次第だし、心を込めて人を褒める。相手に興味を持つなど一つ一つを意識しながら実行する大切さを感じます。
どれだけ相手の立場に立って考えられるか、すべて思いやりに繋がるなと思いました。
12月のオーディオブック
人を動かす方法
自尊心を傷つけない、人を誉める、悪口を言わないなどすべてがちょっとした自分の気づかいで変わっていくのだなぁ~と感じました。
友好的な態度で相手の友好的に気持ちを引き出しうまくいく。北風と太陽!なるほどでした。
敵を見方にする方法や円満な家庭生活方法などなんだかすべて感情的にならず冷静に穏やかに接することが重要なのではないかと思いました。
12月のオーディオブック
読み終わってみて、どの方法も納得させられる話ばかりでした。
仕事も、プライベートも自分も関わりあった人達との関係がプラスになると思いました。人を承認することの大切さ、相手の良いところを見つけること。褒めることを意識することで、人の短所ではなく長所を見つけることでこれからの自分の生き方も変わっていけると思います。
今後の人間関係を築くために大切なことを学ばせていただきました。
12月オーディオブック
言われてみれば確かになぁという内容が多々ありました。
特にシェイクスピアの詩の引用を指摘した時の話は印象的で、事実をただその通りに伝えたとしても、それが関係性のマイナスやひずみとなってしまうならば伝えない方がよい…というのは自分自身の戒めのようにも感じました。
論理や理屈ではなく、その行動によってどのような結果になるかということをしっかりと考えたうえで発言をするということの大切さを教わった気がします。
とはいえ、ほんの内容をすべて実行しようとすると、何も話せなくなってしまうと思うので、できるところ、相手の話を否定せずにまず聞いてみるところから始めてみたいと思います。
【12月オーディオブック】
一つ一つの内容がとても聞きやすくわかりやすく、スッと入ってくるように感じました。全て自分の足りてないところを教えてくれるような気がしてとても聞き入ってしまいました。ベンジャミンという方のお話で、顔と名前を一致させるために努力をしている話がありましたが、当家様の家族構成を覚えることや、来館されたお客様を覚えることに活用できると感じました。これから菜根のファンが増えていく中で名前を覚えてもらったらとても嬉しいと思いますのでこれから活用していこうと思います。
12月オーディオ
人を動かすには、人を好きになる。話しを聴く事、褒める事を意識して行っていきたい。こういうお話はこれまでの課題図書などにも出てきたと思うので、それだけ重要なのだと思った。
「論理の生き物ではなく感情の生き物」というのがしっくりきました。
相手を変える方法がこの本で1番の学びでした。
ものすごく納得したところがあったので取り入れていきたいところ。その内容に関しては3年後まで自分の中で留めておきます。
【12月オーディブック】
人が自分から動きたいという気持ちになって動くようになる方法について・・・。カーネギーは以前から目にしていて初めて聴きましたが実際にその考えを常に胸にとめていることは難しすぎると感じました。全員常にニコニコじゃなくて、喜怒哀楽あって初めてヒトとヒトは人になると自論があります。ですが新たな価値感の1つとして実践してみます。
12月オーディオ
この話は職場だけでなく人と接する時には誰にでもあてはまるのかと思いました。相手を理解し、否定しないことが自分にも同じように返ってくるのだと思いました。
普段の自分の口癖や行動が相手を傷つけていないか、不快にさせていないか自分を振り返り意識してみたいと思います。
12月オーディオブック【カーネギー 人を動かす】
遅くなり申し訳ございません。
自尊心を傷つけられると反論したくなる、これはわかる気がします。自分の行動言動で変わると思いました。
人を動かすのは相手が求めているものを与える、人との接し方で大きく変わる、ほめて励ますことで頑張りたくなる、その通りだな、と思います。実際にやることができたら本当に動かせるだろうなと思います。
12月オーディオ
自分には相当難しい内容でした。
結局は相手を動かすために駆け引きを行うことが目的で手段として笑顔を使う。とか同情を買う、と言っているように感じてました。
自分の意識と相手の意識の相違は物事を進めるうえで非常に難しいことですがその難しさも乗り越えると、そのこと自体が物事の本質を高める気がします。
相手の身になって考えることも、私は君の身になって考えているんだよ?というのは僕には難しいです。
恥ずかしくて言えないですね。
お礼言われても、基本的に恥ずかしくて無視してしまうので(笑)
ただ、新卒の方の向けに、、彼らが僕の歳になるころには僕は藤田さんの歳なので、今までいただいた言葉とかその他諸々、彼らに返していきたいなと感じました。
【12月オーディオ】
人を動かす
相手に対しての視点 どう思うか?人の好い所見つけてそれを習慣化する。今の私にできてるか?昔よりきっとできるようになってるはずと思いながら聴きました。まだまだな所もありますが きっと今後の自分の変化が出来たとき聴き返したら もっと面白く感じれるんだろうなと思いましたし 感情だけで動きがちな部分に気を付けなければと実感しました。 穏やかに冷静に!やってみます。