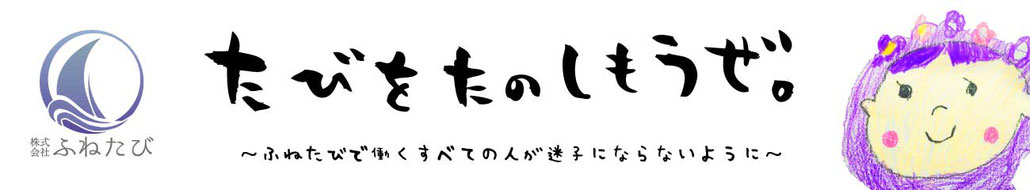【2月課題図書】
プレゼン、人前に立つ、人前苦手という思考に直結してしまうため、読み始めが億劫でしたが、自分の考え方を伝え相手に変化を求める、そして意外と家庭内でも実践しているとの読み初めに心が少し軽く読み進めることのできた図書でした。
内容力、伝達力、人間力。またゴールのイメージは6W2H。理論で納得させ、物語で共感させるなどなど。実際にこの通りに作成していけば、自分の考えが相手に伝わるのだと想像すると少し楽しい反面、様々な成功されたプレゼンの裏にはこれだけの理解と実際の行動、また練習など多くの時間を要するものだとも感じました。
プレゼントを聞く機会は少ないですが、なすの斎場経営方針発表会の隠された裏側、努力が見えたようで、人に伝わるように伝える大変さを知ることができました。今では小学生でもプログラミングが当たり前の時代、プレゼンも同様。時代に乗り遅れないように、常に変化を好み成長が必要であると理解しました。
実際の取り組みに関わらず、様々な物事を知ることは自身の成長にも繋がります。機会の損失にならないよう、適時新しい情報を下さる図書と社長にはいつも感謝しています。3つの要素が足し算ではなく、掛け算で仕上がる行動を目指します。
【2月課題図書 】プレゼンの定義
社内外でプレゼンを聞く機会が日々多くなっていると感じていたこと、入社時研修の資料作成でプレゼンの技術を身につけたかったことなどもあり、没頭して読みました。まず定義としてプレゼントは自分の考えを伝えて、聞き手に変化を求める行為である。ついつい作成していると伝えたいことをたくさん盛り込んでしまい、忘れがちになってしまいます。自分だけが満足するものではなく、聞き手の変化を求めること、肝に銘じます。また、プレゼンを構成する3つの要素には内容力、人間力、伝達力が必要。これらは掛け算の関係性であること。さらに定義の聞き手に変化を求めるためには伝達力が必須でその中でもつなぐ、繰り返す、呼びかける、問いかける、寄り添うの5つの言葉を用いること。途中、実際の設定方法なども載っており、まさに教本だなと感じました。ネットで調べれば何でもわかる時代ですが、ラインを引いたり、付箋をつけたり自分だけの教科書として本書を常に手元に置いておこうと思います。
2月課題図書
プレゼンの資料作成の基本がしっかりわかる内容でした。一つ勉強になったのが、書かれている内容のポイントをしっかり押さえてプレゼン作成すれば記憶に残るプレゼンに仕上げる事が出来るのではないでしょうか?まるで実際に講座を受けているような雰囲気でした。今から使えるルール等、資料作成する際は、この本見ながら作成していきたいと思います。プレゼンは型がしっかりできればうまくできると思います。
オールカラーで図解の説明がとても見やすかったです。こんなにたくさんの資料作成のノウハウをか書かれている著者が元々はコミュニケーションが下手だったと記されていたのは驚きでした。
伝える側は自分の伝えたいことを主きに考えがちですがプレゼンの主役は聞き手で聞き手の心理を理解するこ 、相手に伝わってこそ資料の価値があのるだと感じました。そしてそれを伝える為の言葉のテクニック、身振りなど伝わるプレゼンすることはいろんな術を学ぶ必要があると改めて知りました。
2月の課題図書
プレゼンというものをいままであまり経験がないと思っていましたが、子供の頃から学校で何かの発表会などもプレゼンになるのかと思うところから始まり、やはり相手のことをしり必要性を感じてもらうことが重要なのかと感じました。
資料の作り方もあり、フォントの使い分け、強弱も勉強になりました。これは、イベントの資料にも取り入れていきます。
2月課題図書
これから菜根でセミナーを行う際や、パートナーさんの育成の資料作りに大いに役立ちそうです。また、事前相談も私たちのプレゼンの場でもあり、事前相談のご案内の時に取り入れたい部分がいくつかあったのでパートナーさんにも共有していきたいと思います。私は伝えたいことを詰め込んで伝えがちなのですが、お客様が聞きたいと思う内容を話すように気を付けていきます。
2月課題図書
以前この本をいただくまでは、自身が受けたセミナーで使用された資料を解体してプレゼン資料を作成していました。プレゼンには細かく全てを入れ込んで作成する資料と、要約ワードだけを入れた資料で話し手が全て口頭で伝える2パターンがあります。言葉に自信の無い私は後者を選ぶことが多かったですが今後はこの本をベースに作成していけたらと考えています。又、作成依頼する時などこの本と共に依頼することで説明をする時間も短縮され作業効率も上がるなと思いました。
【2月読書感想文】
プレゼンよりは、セミナー等の資料作成を行うことが多かったのですが、自分の作っていたものは、私が伝えたいことをとにかく文字におこしているだけの資料だったことに気付かされました。
一方通行でした。
要点をまとめることが不足しておりました。本書の6W2H、そしてプレゼンの基本型の構成ができていなかったので、作成中に自身が迷子になることもあったため、法則や言葉遣いを意識しながら、次に資料を作る際には本書を読みながら作成してみます。図解されているので、わかりやすかったです。今後はその中で、資料作成にかかる時間も削減できればと思います。
2月課題図書
以前2年目研修で行った内容に近いものを感じました。
プレゼンがうまくいかないのは練習をしていないから。
今回の著書では内容力、人間力、伝達力の掛け算と書かれていました。得意苦手を自己分析し苦手をなくそうと思いました。
デザインはシンプルで良いというところに納得。デザインにこだわる事が多かったですが、プレゼンの目的は聞き手を動かす事で、特におしゃれとか面白さは求められていない。納得や共感を得て最終的に行動を促すことが出来ればよい。
色の選び方や写真の考え方はすぐに取り入れようと思った。
これから資料作成やプレゼンの機会などが増えていくと思うので、教科書にしたいと思いました。
2月課題図書
プレゼン会議などの場だけでは無く、会社へそして先輩方へ自分自身の考えを伝えるという意味でも役立つと思いました。シンプルメッセージ、ノットファクトバットメッセージはPOPなどを作成する際に意識して使っていますが、お客様へ数十分や1時間単位で行うセミナーでは、いかに飽きずに興味を引いていただけるかという意味でも必要と感じました。今後はセミナーなどを行う機会もあるかもしれませんので、その際改めて読もうと思いました。
2月読書感想
現在パワポも思うように使いこなせていませんが、基礎が書かれていて分かりやすいと思いました。『プレゼンの成功は聞き手が行動すること』『聞き手が主役』なるほどと思いつつ‥準備や構成、資料作りそしてプレゼンをしている方、人に伝えるとは大変なことなんだと思いました。私は人前に立つのが苦手ですが、少しでも人に伝わるよう伝えられる人になりたいと思いました。
【2月課題図書 】
プレゼンというものに触れてこなかった私にとってはとても為になる本でした。きっと最初は自分が作ったものに満足して内容が疎かになってしまうだろうと感じました。相手のために資料を作成し、相手に伝わるように練習をし、試行錯誤していくこと。これは普段の業務でも同じ事だと思いました。普段の打ち合わせから相手に伝わるように話すというのは当然のことですし、自分のためではなく相手の為というのはもちろん皆がいつもしていることだと感じます。もしこれからプレゼンの機会があれば、今回の課題図書を手元に用意し、言葉だけではなく、目から理解してもらえるわかりやすい内容づくりを心がけていこうと思います。
屋代 実沙紀
なすの斎場グループ
2月 課題図書
プレゼン資料の内容の決め方、作成のポイント、そもそもプレゼンとは?という事や、発表の心構えなど、プレゼンの基礎が分かりやすく解説されていました。以前受けたプレゼン研修を思い出し、プレゼンに対する苦手意識を無くすことや、わかりやすく明確な資料を作成し、きちんと相手に伝わるプレゼンができるようにしたいと思います。
2月課題図書
ずいぶん前に方針発表の資料作成に参考にした図書です。改めて読み返すことで良い復習になりました。私の場合とくに研修資料を作成することが多く、時間の割り振りや、インプットとアウトプットの活用、文字のフォントを意識することで、聴き手が情報に集中できる環境づくりを心がけています。とは言ってもまだまだ改善の余地がありますので、今回の図書は参考書がわりに手離すことが出来ない良本だと思います(^^)/
【2月課題図書】
普段はプレゼンする機会はあまりないのですが、実際にプレゼンを行うことになった時の為の良い応用が書かれていました。
プレゼンの主役は利き手であること、自己満足で資料を作成し利き手に聞いてもらおうと思ってもうまくはいきません。
なるほどなと思いました、たぶん自分でもこの本の内容のようにプレゼンター主体の話をされても半分も耳には入ってこないでしょう。
利き手の心を動かす(話を聞いてみたい、この商品を買ってみたい)と思わせるような資料作成、プレゼンのやり方を学習していきたいと思います。
書中盤よりパワポの説明が多くされていました、パワポで資料を作ることが多いのでこの本は携帯して持っていたいです。
読書感想文
プレゼンは、聴き手のために…ちゃんと聞いてもらうために作成しなければ意味が無い…
うまくできないのは練習していないから…
そうですよね。となんとなく昨年1年間学んだ内容かと思いました。
作成のポイントなどが説明されていたので、パワポ資料作成の時にはこれを読み返して良いプレゼンに繋げて行こうと思います。
【2月課題図書】
プレゼン資料を作るのではなく聞き手の価値+伝えやすい構築=土台 の図形はよく理解出来た。慣れていない事は作成がゴールになりやすいので一番最初にここを理解すべき。あとはポイントでインパクト(潜在的価値)などを加える、もちろんここも聞き手の価値を考える。
伝え方以外にも基本的なパワポの使い方も掲載されいるのも良いと感じた。
【2月課題図書】
こちらの冊子は先にプレゼン資料作成のために社長から頂き、何度も読ませて頂いていましたが、改めて読み返してみました
・情報量を絞る
・結論が先、理由が後
・ファクトのみを語る
この3点は、プレゼン資料作成に限らず、普段のスピーチや打ち合わせ、プレゼン外のお客様向け資料にも活用できる点だと感じています
また簡単なパワポの小技などもあるので、これからも活用させて頂きます
2月図書
以前私も読ませていただきまして、今回改めて読みました。
文字が重要だと改めて感じました。
フォントに関して以前はまったく気にしておりませんでしたが、この本を読んだ後は自分で言うのもなんですが良くなりました。
経営方針の際にもこの本を読んだりしていたので、あまり資料を作る機会の無い方は作るときに一旦ちょこっと見てから作ると凄く見易い資料になると思うのでオススメです!
2月感想文【いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本】
今までプレゼンや資料作成などを見ていただけでした。2年目研修で学んだ事も書いてあり、より分かりやすかったです。プレゼンは何を誰に伝えて行動してもらえるのかを考え伝えたいことは目立つとこに書いておくことの重要性が分かりました。今後資料作りやプレゼンを行う際には取り入れて実行できればと思います。
2月感想文【いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本】
経営方針を初めて何回目かに社長にいただき、資料作成の際に何度も目を通した本です。
相手に伝わるプレゼン、まだまだですが今後も参考にしていきたいです。
2月課題図書
始め何かの説明書を読んでるみたいでしたが、もし今後資料作成などする機会があれば参考にしていきたいです。無駄な話をだらだらと書いてしまいがちで、何を伝えたいか、理由なども簡潔に伝えるように意識していきたいです。誰に伝えたいことなのか、見る人のことを考え書く、話す。少しでも苦手意識を減らしていきたいです
2月感想文
以前一度読みましたが、時間をおいてみて再度読み直すと若干当時よりも印象が変わったように感じました。
以前はセミナーやプレゼンなども聞き手になる役割が多かったですが、やはり話し手になることが多くなったことで、どちらの視点でもみれるようになったからかなぁと思っていました。
かつては伝えたいことを全て文字で入力して読む!というプレゼンとも言えないものが、伝え方を変えるだけで全く別のものになるのはとても楽しい経験になっていくと感じました。改めて数年後見返すと新しい発見が得られる本だと思います!
2月課題図書
資料の作成をしたことがなかったので、経営方針の資料の作成は、最初は社長がテンプレートを作ってくれて、そこに文章や数字を入力していたことを思い出しました。資料作成のルールのワンスライド・ワンメッセージはよく言われていたなと思いました。「振り返り」と2回目の「要点」で聞き手の頭の中を整理してもらえるようにしたり、行間を整理して聞き手の負担を減らすなど、聞く人の事を考えて資料を作成しないといけないとおもいました。まだまだ資料作成に時間がかかっていますが、もっとわかりやすく、見やすい資料が作れるようになりたいです。
2月課題図書
資料作成&プレゼンの教本
まず初めにこの本を読み始めて思った事は、大学とかで変な授業するならば、こういう授業を積極的にすればいいのになぁーでした。
プレゼンは、一部の方を除き、会社勤めする多くの方に必要と言うか、必須スキルだと思います。社会に出て、多くの方は会社内で資料を作って、上司にダメ出しされて何度も作り直したり、自ら今回の様な本を買って勉強をする方が多いと思います。結局は、やる事になるのだから、早めに学生に取り入れれば、win-winだなと感じました。
話は逸れてしまいましたが、そもそもこの本自体が著者から読者へのプレゼンな訳なので、この本はとても伝えたい事が簡潔に書かれていた?では無く、描かれていました!まさに著者の意図通りに。この著者も伝えておりましたが、言語的情報<視覚的情報と言った形で構成されている事が読み易く、頭に残り易いのだなと感じました。勝手な解釈ですけれども、きっと中身の細かい技術云々そのものよりも、こういった興味を持ってもらえる内容の作り方がどんな物かを感じて欲しかったのではないかなと捉えております。
実際の中に書かれている様々な技術については、一回読んだ位では身につくものでは無い事は重々承知しているので、今後は個々の深掘りをしていき、自分のものにします。そして今後、毎年の様に新しく入って来る人達にドヤ顔でプレゼン披露するつもりです!!