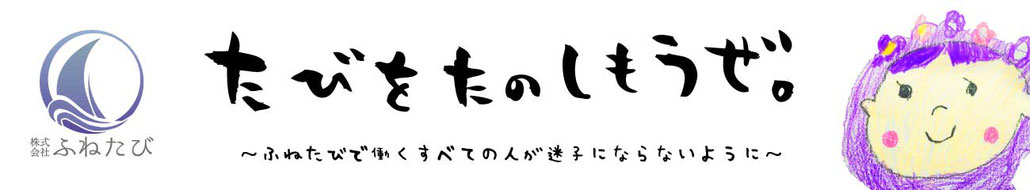3月4月課題図書【THE CULTURE CODE ―カルチャーコード― 最強チームをつくる方法】
金八先生の腐ったミカンは日本だけではないと実感。短い言葉で言い合う。痛み衝突が必要。禁止ではなく良くするためのルール、それは目標ではなく物語に共感。潜在能力が高いと言われる子供を教育すると、本人だけでなく指導者にも変化が起こりスキルアップにつながる、これは面白いと思う。抽象的だがこの本を読んで感じた事は「なすの斎場は葬儀社ではなくクレドを実践する為の会社。その為にチームが有り実践(提供)する為の一つの手段が葬儀」なのかなと私は思いました。
3月 4月課題図書 最強チームをつくる方法
本書は、安全な環境・弱さの開示・共通の目標の3つが鍵が重要であり具体的な事例をあげておりとても分かりやすくなすほどなと思いました。
今まで勘違いしていた部分があり、人に弱さを見せてはいけないという固定観念がありました。しかし、本書を読んでいる内に実際はそうてではなく、助を求める事も、弱さをさらけ出すことの一つだと勉強になりました。
第15章で優先順位を言葉で表現するという文章がありますが、その中でも、人を大切にするという文言がありました。私の中で何か足りない物、忘れていた事を思い出させてくれた内容だと思いました。
とても読みやすく、実例がわかりやすく勉強になりました。
【3月4月課題図書】
自分以外の誰かと仕事をする。それが対1の2名であっても、巨大な1000人規模であってもチームはチーム。ピザを一緒に食べられる程度のチームが良い、足し算ではなく掛け算の力など以前の課題図書で読みました。それに加え、どのような方法で“最強”になっていくのかを確認しながら読み進めた図書です。
安全な環境、弱さの共有、共通の目標。現在のチーム、また前職、家族関係などに置き換え考え、言葉では理解できたようで、実際に落とし込むための時間と、検証した結果に合わせ行動できるようになる必要があると感じました。言葉で理解していても行動に移せないのでは意味がありません。弱さの共有では自己開示の必要性、またそれを受け入れる安全な環境、その上で共通の目標が強みに繋がるのだと解釈しました。
なすの斎場での経営方針発表“10年後、その後の未来の約束”。いつでも戻ることのできるクレドの他、SDGs活動、キャンプクレドなど行動のためのアイデアがたくさんあります。与えられた環境に浸るだけでなく、“いつでも変化していい”と捉え行動に移すことが「自ら変化を好み成長が喜び」に繋がるのだと実感しました。
“最強チームを作りあげることができるか”と問われると自信はもちろんありませんが、今の仲間、またこれから迎える新たな方々に、楽しく、中毒性のあるといっても過言でないような過ごし方を提供できるようにしていきたいと深く想うと同時に、弱みを強さに変換できるような想像性を育んでいきます。今月も大切な気づきを提供して下さった図書と社長には感謝します。
3月4月の課題図書
読み始めて最初の方に最強のチームにしか見られない特徴というところで家族のようなで中毒性があり居心地がいいとありました。入社して3年くらいたったころ私も”なんだか同僚たちを家族のようだな~”と感じていました。新しい仲間にもそんな風に思ってもらえるようにしていきたいと思える一文でした。弱さを見せるために必要なこと、まずはリーダーが弱さを見せる何回もとあり弱さを見せるというのは人間らしさにつながり親近感もでるし”ここは自分の弱さを安心して見せられる場所”という一文もあったように安心材料になると思いました。
3・4月課題図書
まえがきの冒頭にチームとはお互いの相互依存関係が日々の活動の中で認識し合える範囲にある人びとの集団と書かれていて、事例のひとつ2足す2が10になるの内容でいちばん大切なのは個々の能力ではなくメンバー同士の相互作用ということ、個々の力が素晴らしくても協力し合わなければ結果は出せないし、逆に個々の力が普通であっても協力し合えば最高の結果が出すことが出来るということを知りチーム全体の力、協力があってこそ目標達成に繋がるのだと思いました。
弱さを見せるという内容で危機的状況で操縦士たちが通知という短い言葉のコミュニケーションでやり取りし知恵を出し合ったり、ピクサーで実施してるブレイントラストで意見を出し徹底的に分析をするなど弱さや問題の洗い出しをし、客観的に見ることで解決策が生まれることもあるのだとこの本を通して感じました。チーム力を高めるにはいろんな角度で物事を見たり考えたりすることなども大切だと思い、意識付けしていこうと思う内容が詰まった本でした。
【3.4月課題図書】
人はひとりで生きていくことは出来ない。人類が誕生した時から人は協力し合い繁栄してきました。そんな時代より表現の仕方は違うかもしれませんがチームというものは存在しており今なお受け継がれている物であることが実感できます。
今私たちもチームを組んで日々の業務を行っていますがそれらの事になぞられるようにやはり業務も一人ではできません、仲間の力があってこそ伸びることもできるし、コミュニケーションを図ることが出来ています。
人間は個性の生き物ですがそれらを相互理解し話をする、聞くことに重点を置き円満なコミュニーケーションを気付いていくことが大事なのではということが分かりました。この辺は今月のオーディオブックにも共通していることで話す、聞く、コミュニーケーションを取るというのが最強チームを作っていくうえで以上に重要項目になっていくのではないかと思います。
【3,4月読書感想文】
自分自身、チームを作るにあたり意識していたことは、心理的に安全な環境の提供ができるか?帰属意識を高められるか?クレドの浸透がいかにできるか?を考えていましたが、弱さを見せる。ぎこちない瞬間を意図的に作るという考えには驚きましたが、なるほどと思いました。弱さを開示して共有する。自分ではリーダーは弱さを見せてはいけないと思っていましたが、リーダーが弱さを開示することによってメンバーも弱さを見せて良いんだという意識が良い環境を作るということは実践していきます。ただ、弱さ=愚痴にならないよう気を付けます。とても学びのある一冊でした。
【3.4月読書感想文】
昨今、心理的安全性の高い職場作りが提案されていますが、まさにジョナサンの活躍でメンバーに安全な環境を提供した事例を読み改めて自分の中で深く落ちた気がします。また弱さの開示がもたらす効果も助けが必要で、繋がりや協力関係が持てると納得しました。ただ仕事中に弱みを見せることに少し抵抗がありますが、それによりチームが強くなるのであればやるべきだと思います。そして共通の目標、クレド。コアバリュー。ザッポスのようなCRM。ベクトルを合わせてより良いチームにしていけたらと感じます。個人的には教える時についついやってしまうサンドイッチフィードバック。これに気をつけようと思います。
【3.4月読書感想文】
チーム作りでいろいろ考えることがありましたが、最強チームは心理的安全性が必要。
心理的安全性を作るために、優れた能力でなくてもできることがあるがたくさんあることに気付けた。
意見をたくさん言い合えるチームに向けて、私自身中和する力や、弱さを見せること、コミュニケーションをとるためにザッソウ、無駄話で話す時間を増やすなど、まずはチームの最強の土台をつくるためにチームは安全だということを常に呼びかけていきたいと思います。
読書感想文
ジョナサンの行動で、メンバーが安心安全な環境が作られていたことに感心しました。自分自身、仕事だけでなく、家庭、保護者と関係、地域とのつながりなどに活かしていけると思いました。
チーム力を上げるのも下げるのも、一人いればできること、ならばチーム全体を上げられる一人でいたいと思いました。ここは安全な場所なんだと、弱さも見せていいんだよ…と、今いるメンバーはもちろんこれからも増えていく仲間にも提供できるよう努力していきます。
【3月4月課題図書】
ティール的組織を目指す中で、心理的安全性の向上、特に帰属意識の向上は重要なファクターであると再確認出来る良本だと感じました。特に「帰属のシグナル」が具体的で参考にしていきたいと感じます。また、自分の意識改革としては、「強い=安全」から「安全=強い」というマインドセットが出来たと感じます。その中で改めてクレドを振り返り、クレドの浸透こそが「最強チーム」に繋がることを確信しました!
3・4月 大人の感想文
非常に深く、そもそもチームって?素晴らしいリーダーって?頭を真っ白にして、様々な現状と照らし合わせて聴きました。特に10章から15章に関して、深く考えさせられる内容で、中でも3つの質問など、自分がリーダーから聞かれたら良いなと感じたので実践していけたらと思いました。明確な優先順位、マイヤーの話についてはクレドの在り方そのものであり、全てはシンプルに考える事で物事も業績も教育もスムーズになると理解しました。聴いてておもしろい本だったので再度聴いていこうと思います。
【3、4月課題図書】
チームにとって安全な環境があることによって最強チームが構成される。
自分も安心できる環境だと のびのびと仕事なども効率よく進めれています。
物事は考えようだと思いますが 考え方をプラスに変えることが出来れば 周りにも良い影響を与えれていて 逆に マイナスばかりだと悪影響で チームが成り立たなくなります。分かる気がしました。
弱さをさらけ出すことにより チームの協力関係が深まる。なんかよくわからないとも思いましたが 自己判断ができるように 考えていけるチームが作られ なすの斎場でいうのであればクレドとは?に帰ることが出来る やっぱりクレドってすごいなと 本を読んで感じました。迷ったときには ここに戻ろうと思いました。
4月課題図書
弱さを共有するという点は、先日の高知研修の際に出たのと少し似てるなと思いました。チームで円を完成させれば良い。これは自分の特性やメンバーの特性がわかっていあないといけないので、まずはチームのレダーチャートなどを作ってみようと思います。
リーダー仮面のリーダー論とは全く違うもので、私はこちらの全員で作り上げていくチーム、そこに導けるリーダーになっていけたらと思います。
課題図書
まずは自分達のビジョンを明確にすることが非常に重要だと再認識いたしました。
なにかを説明するときにも、いくら必死に説明しようが「なにがしたいのか」「なんでしたいのか」ということが明確になっていないとなにを話しているかわからなくなってしまうことが多くあります。
その認識が共有できているからこそのコミュニケーションや意見共有なんだなと。
ゴールを明確にして、共通の目標をしっかりと共有してチームビルディングをしていきたいと思います。
3、4月課題図書
最強のチームをつくるスキルが3つあることを知りました。
①安全な環境をつくる②弱さを共有する③共通の目標を持つ
重要なのは安心な環境作りがベースとなって、リーダーの弱さを見せる、そして一緒に目標を追いかけるという順番でした。わかりやすい実例がのっていったので学ぶことが多かったです。
そして、全然出来ていないと思いました。まずは安全な環境つくりから始めたいと思います。
3・4月感想文
とても難しい本でしたが、ところどころたとえ話や実際に起こった事例など(ザッポスのお話など)も出てきて、進めやすくなっていましたが、それでも理解しながら読むのが大変でした。
その中でも特に印象的だったのは、前半にも後半にも出てきた「すべての行動は周りに影響を及ぼす」ということ。それはいい意味でもあるし、悪い意味でもあり、気を付けなくてはと思った。
そしてもし悪い影響の及ぼす行動がチームで見られた時に、周りがそれに引っ張られないようにするためには何をすべきか、どうすればよいかをしっかりと考えることができた今のしおやチームがとても良いスタッフに囲まれているので、そんなチームをどこでも作ることができるように、学ばせてもらいながら次のステージにつなげていきたいと思います!
課題図書
私が特に気になった点は、第8章の弱さのループの一部でした。これを読むまでは、弱さを見せる事は、弱点を見せる事で、見せて得をする事はないと思い、長い人生生きてきましたが、この章で少し考えが変わりました。弱さが協力関係や、信頼関係につながる!と。コミュニティーの中で弱さを見せるコミニケーション!弱さのループ!読んだだけの今の段階では、まだまだ分厚い余計なプライドが邪魔をして、実施は出来ないと思いますが、しっかりと自分もそれを晒し、相手のも受け入れるような関係性を構築したいと思いました!!
3月・4月課題図書
以前読んだリーダーの仮面とは全く違う印象を受けましたが、色々な事例が挙げられており、読み物としても面白かったです。
より良い仕事ができるよう、チームのパフォーマンスを上げるためには、安全な環境・弱さの開示・共通の目標とあり、ミーティングやザッソウ、1on1の重要性を再認識しました。腐ったリンゴにならないように、チームに良い影響を与えられる人間を目指したいと思います。
3.4月 課題図書
前々回の課題図書、「リーダーの仮面」とは真逆の印象を受けました
「リーダーの仮面」では、リーダーに求められるスキルは、大別すると【タイムラインの管理】と【共通目標の設定】であり、チームメンバーへの配慮・共感はリーダーではなく、仲良しグループであるとされていました
本書ではメンバーの帰属意識を高める面にフォーカスされており、【共通目標の設定】と【メンバーへの配慮・声掛け】の2点が挙げられていました
私自身が最も注目したのは、リーダー無しでもチームが稼働するのが理想、という点でした
この点は私にとっても大変魅力的な要素でしたが、現状の小規模チームでは厳粛なタイムライン管理が求められらるのではないかと感じました
自身の考えとしては前々回の「リーダーの仮面」に共感する場面が多かったのですが、自身に足りない部分が補う要素、と考え、本書の内容も取り入れて行きたいと思います
3.4月感想文【カルチャーコード― 最強チームをつくる方法】
最強チーム…?と思いながら読み進めました。安心できる環境作りで効率よく仕事を進める、その中で妨害者の対処方法などもあり、すごく勉強になりました。確かに、リーダー=強い人というイメージはありましたが弱みを見せて相互的に最強なチームになっていける、繰り返し伝えることが大切。安心して仕事ができるように考えるきっかけになりました。
【3・4月課題図書】
安心できる環境作り、弱さを見せる、など勉強になりました。何より冒頭の「大きな私」にならないよう自分を見直し、信頼関係を築いていきたいと思います。
小さなシグナルを送り続け、目標(目的)を見失わないような地図になれるようコミュニケーション(声かけ)をしていけるよう、また指示待ちではなく自分で考えて行動できるようにしていきたいです。
3.4月課題図書
安全な環境をつくる、弱さを見せる、共通の目標を持つとありますが、確かにバリバリのビジネスマンで非の打ち所がない人達の集団よりも、弱さを見せて少しおちゃらけるくらいの姿を見せた方がより心理的にもコミュニケーションも取りやすいチームになるのかなと感じました。著書の内容を会社全体で全て取り組むというのは少し難しいかとは感じましたが、自分の所属しているチーム内で少しずつ取り組んでいこうと思いました。
【3月4月課題図書】
私はリーダーと聞いて、スティーブ・ジョブズのようにカリスマ性で周りを引っ張っていく人物を想像しましたが、この本で紹介される最強のリーダー像はむしろ逆でした。率先して弱さを見せ、チームが安全な環境であることをメッセージや態度で示し、その上で共通の目標を持つことができれば、チームの力を引き出し、偉業を達成することができる。スキルが高い人を集めれば良いチームになるわけではなく、むしろ周りを安心させるコミュニケーションが重要…。ちょいちょい腐ったリンゴになり弱さを見せっぱなしの自分ですが、小原田がオープンとなり新たな目的と課題が見つかりましたので是非実践していこうと思います。
西 祐輝
なすの斎場グループ
3月・4月課題図書
私はチームを作るということにとても興味がありました。私がまだわからないチームの作り方。そしてリーダー達は常日頃実践し、チームをまとめていてくれているんだと改めて実感させられる本でした。私はいままで沈黙の時間などがとても苦手でしたが、本を読んで時にはわざと気まずい時間を作ることが大切なのだと感じることができました。
この本は3店舗を見据えた本だと感じました。深く読めてはいないのでもっと熟読しようと思いました。