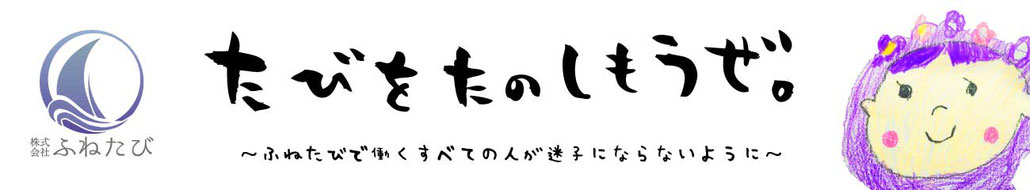5月オーディオブック「めんどくさい が消える脳の使い方」
脳科学や医療現場を元に書かれた本との事。初めの めんどくさい=わからない の解釈はこの本を聞きながら体験できた、これはこれでどうかと思いながら…。具体案がいくつもあったが自分にあっていると感じた所はストレスのかけ方・かかる場所などを分散する事。作業工程・確認などは多くなるが めんどくさい に対策を立てて行動する。自分がなぜ めんどくさい と感じるのかこの感情に興味持てた時点でとりあえずは良しと思う。
5月オーディオブック
めんどくさいと考えることは脳がそれを拒否しているから、人間を司る脳がそれを拒否や嫌だなと考えればめんどくさいが発生する。
なるほどなと思いました。確かに考えることをやめれば面倒だと思うことは無くなるのでしょうが、人間は成長する生き物であること、生まれてから死ぬまで一日も休まずに働いているのですね。考えることをやめてしまうと生きているとはいえません。よくつながっているなと思います。
しっかり考えたり、体を動かすことで脳はリフレッシュできるという事なのでしっかり考え末永く付き合っていきたいです。
5月オーディオブック
めんどくさい=わからないことが、本書の解説で納得ができました。まためんどくさいと感じる時に取る行動としてめんどくさいことを後に回す。これは自身の行動を振り返るとその通りだと感じました。ただめんどくさいと感じることは悪いことではないと捉え、自分の脳を成長させるよい機会と受け止め、少しずつめんどくさいがなくなる脳への指示出しなどに取り組んでいこうと思いました。昔勉強した医療単語などが出てきて脳な適度のストレスをかけられたかと思います。
5月オーディブック
人と同じく覚えて実践することが出来ない事がコンプレックスで、脳科学も取り入れてなんとか人並みに覚えたり出来たりする事が出来ましたが、テンション/モチベーション/効率に関してはやはり精神論ではなく脳の使い方。幼い頃に「めんどくサイ」という絵本を読んで、恐怖のあまり「めんどくさい」という言葉をなるべく使わないように(使ってしまってますが)心がけてはいましたが、最近私生活でその言葉が増えたなと感じます。本書の中、コルチゾール分泌に関しては、それに繋がる早寝早起きについての根拠をやっと信じる事が出来ました。まずはコルチゾールとやらと仲良くなって効率を上げていこうと思います。
5月オーディオブック
めんどくさいとは、脳がわからないと判断していること。なるほどなと思いました。苦手なことや新しいことを始めるときは、つい後回しにしてしまいます。話しを聞いて、これって結局、自分の知識や技術が足りていないからじゃないか?苦手なことだから億劫になるんじゃないか。そうも感じました。それと、今までは脳は動いているという意識しかありませんでしたが、脳は生きている。この意識を大切に考えていけば、脳への伝達もきっと、今までと違うものになるのかなと思いました。
5月オーディオブック
興味深い内容で聞き取りやすかったと思います。
めんどくさいが消える7つのこつという事で、興味があったのがそれが出来たらこれができるという言葉でした。なぜかこの言葉が印象的で面倒というより頑張ってもっとやろういう意志につながるのでばないかと思いました。
朝起きてメールのチェックをやめよう。最初にに自分のやりたい事をしようという事で、現状では朝起きてチャット見ようみたいと流れで生活しているので一度流れを変えてみよう思いました。
5月オーディオブック
自分もめんどくさがり屋でめんどくさいのは自己の甘えだったり怠けな気持ちの問題かなと思ってましたが、科学的に脳の作りが関わっているのだと知りました。マルチタスクが苦手な方なので著書の内容のようにをこなすには重要な仕事を優先する、緊急度は高いが重要度は低い仕事退社率のアップダウンが激しくその後の作業がめんどくさくなるとの事で注意のかまえや脳を上手に使う事で効率もアップするとの事なで意識してみようと思います。脳は自分を構成している内蔵だと割り切ってしまえばすんなり行動が変えられるそうなので脳→内蔵だと考えを変えて行動するのもアリかと感じました。
5月オーディオブック
めんどくさいの正体はわからない事 という解説になるほど、と思いました。何故めんどくさいと感じたのか漠然としたままにするのではなく、自問自答し、理由を深堀りしてみることで自分の苦手な事に気付けて向き合う切っ掛けになると思いました。「めんどくさい」への対処法が色々解説されているので、できそうな事を実践していきたいと思います。
5月のオーディオブック課題図書
「めんどくさい が消える脳の使い方」
自分自身めんどくさいという言葉を使うことが多く どうにかしなきゃと思い題名で私が選んだのですがすんなり入ってきました。 脳からの信号で 通じる命令をする。理屈?とは違うのかもですが 私には 考え方を変えるコツが良くわかりました。意識をかえることで効率も変わる。自分が後回しにしてしまうことが多いので やる気コツが聞けて 自分の中の「めんどくさい」を消すマインドセットにつながるきっかけになりました。
5月オーディオブック【めんどくさい が消える脳の使い方】
めんどくさい、これは言ってしまうことがよくあります…。ですが、これを読んで変えようと思いました。7つのコツを習得し、めんどくさいなと思ったことも脳の仕組みを生かしていこうと思います。早起きが得意になれるよう、目覚めたら頭を高く上げ、一番めんどくさいと感じてしまっている掃除に関しては10分間しかしない、などめんどくさくならい行動も大切なんだなと感じました。
5月オーディオブック
めんどくさいと思ってしまう脳はとても厄介だが、とりあえず動いてみることが大切ということがわかった。そうしていくうちに自分の脳へ命令を与え、めんどくさいという過程を消すこと。自然と行えるようになれれば仕事もプライベートももっと最高になる気がしました。これから先、誰かのお手本になる機会が多くなる中、自分の成長と周りへの影響を考えるとこの本を聴けて良かったと感じました。
オーディオ
面倒臭いと思うことって、苦手だったりつまらなかったり、あとは自分にできるかわからないことだったりと面倒くさいのなかにも種類があるなぁと聞きながら感じていました。
面倒くさいと思うことは別に悪いことだけではなくて、面倒ならやらないようにしちゃえば良いと思ってます。
あまり、僕にはフィットする本ではなかったと思いました。人それぞれじゃないかなぁ。。。と思います。
掃除が面倒くさいから、ダスキンがいるし、食事作るの面倒くさいからお弁当屋さんがいるし、火を付けるの面倒くさいから電気があるし、家に行って話すのが面倒くさいから電話があるので面倒くさいをどう改善するかは超大切ですね!
5月 オーディオブック
めんどくさい…生活をしてる中でよく出てくる感情です。めんどくさいことは後回しにしがちですが、後回しにすることでずっと頭の片隅にそれが残っている、だったら早く手を付けて対処してしまえ!とわかっていても後回しにするという悪循環。
どういう時にめんどくさいが出てくるかという項目で、手順がわからない場合、融通を利かせないといけない場合、現実との気持ちにギャップがある場合というのに納得しました。
めんどくさいを適切に扱う方法として、手書きでやることや手順を書き出す、こなした量を見て確認できるようにする、一日の予定は一日のお尻から逆算して立てる。
朝礼前のやることノートは、1日を計画的に動くためのものだけではなく、めんどくさいを消すという副産物もあるということを理解しました。
明日は気持ち新たにやることノートに向き合ってみようと思います。
【5月課題オーディオブック】
「めんどくさい=わからない」には大いに納得しました。ついつい理屈っぽく考える癖があるので、自らの思考でめんどくさいラビリンスに入り込んでいるところがあるなーと学びを得ました。左脳で考えるよりも、右脳に刺激を与えることが、めんどくさいラビリンスからの脱出に繋がると感じましたので、早速本日から実践していきたいと思います。
5月 オーディオブック
仕事をしているとやはりめんどくさいことは後回し、やりたい仕事を優先してやってしまうということがあります。
「わからない」「不透明」ということを因数分解し、その面倒だと思えることを一つ一つ払拭していくこと、そしてまず小さなことでも実行することで「めんどくさい」という思いを感じる前に行動をしていくのが大切・・・と感じました。実行してみると結構くせになり、頭で分解しながら払拭して行けるのだなと感じたので、これからも続けていきたいと思います!
5月のオーディオブック
脳に通じやすい命令は3つ脳のリズムに合わせる時間帯に合わせる起床する時間にカウントさせるなるほど!覚えたいことがあったらっ起床3時間後にします。人間関係のめんどくさいは情報戦略の違い?私は細かい報告を求めてしまうそうです。自覚がありませんが・・・。
本を聞いていてめんどくさいと思うことも人間らしさではないかと思っているなあ~と感じたのでめんどくさいを消すとは考えたことがなかったと気づきました。逆に仕事をする上では必要なのかもしれないとも思いました。オンとオフで切り替えればいいんですね!
【5月オーディオブック】
つい、「めんどくさい」と思ってしまいがちですが、起床時間や深部体温を上げてパフォーマンスを上げるなどのコツがある。緊急性、重要性など優先順位を考えて習慣にしていければと思います。
継次系に近い自分は一つずつ区切り、順番にこなしていくようにしていこうと思います。自分を知り、コントロールしていきたいです。
5月分
課題図書の方と合わせて考えると、すごく良い相乗効果になると思い、楽しく自分の中に入れ込むことが出来ました。めんどくさい。これは誰にでも起こりうることですし、人が変わればめんどくさく感じない事柄にもなりえます。なぜめんどくさいと思うのか、なんて人生で考えた事もなかったなと反省させられました。面倒なものは、面倒!!それで終わっていました。ある事柄を、避けるのではなく、しっかりと深堀していき、本書のようにパターン別けし、自身を客観的に観察できる人間になりたいなと思いました。めんどくさいことを脳科学的に考えて、それをワクワクするリーダーの教科書と合わせて、楽しく仕事する!良い雰囲気の職場にして、みんなで突き進みたいですね!!
5月のオーディオブック
マルチタスクの仕事術の話がありました。急に難しいワードが出てきましたが優先順位や重要度から戦略的に取り掛かるという内容だと認識しました。戦略を立ててこなしていくという内容だったので、仕事のはじめと終わりにこの時間をつくろうと思いました。
脳の働きと行動を考えて、めんどうくさいと思ったら何かしらの行動を起こしたり、作業工程の見直しを行おうと思います。
めんどくさい=わからないという事ですが、著書はわからない単語が多数でした・・・。
5月オーディオブック
日々の生活で、めんどくさいとつい言ってしまうことがありますが、めんどくさいと思う時は、分からないときとのことで、脳の仕組みなんだと納得しました。めんどくさいと感じたら日々の生活での行動を変えてみようと思いました。日常生活の動線の中にやるべきことを組み込んでやる気がなくても出来てしまう状況をつくっていこうと思いました。
5月オーディオブック
聞き慣れない専門用語が多く、化学的な根拠が記載されていて、物質名など横文字が多く想像していたより難しい内容だと感じてしまった。
めんどくさいと感じてしまう時、わからない時で脳の仕組みが原因とわかり納得。
面倒だと感じたら違う動きをしてみたりと取り組めることから始めたいと思います。
5月オーディオブック
目先の仕事を優先してしまい、タスクを後回しにしてしまうすることがよくあるなと思いました。
緊急性は低いけど重要度は高い業務だとわかっているのに・・・。
これはやる気や性格ではなく、わからないことでめんどくさいとなってしまう脳の仕組みだと知りました。
まずは少しやってみることが大切だと思いました。
今まさにやらなければならないことがたくさんあるので、やることノートを利用しながら終わらせていきたいと思いました。