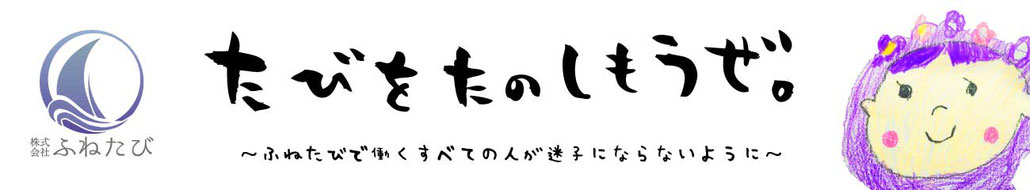5月 読書感想文
この本を読んでみて、自分の現状と、本の内容を比較した時、わくわく感がメンバーに伝わっていないのかと思わせてくれた内容でした。
リーダーのわくわくがチームを成功へと導くリーダーの空気が1人ひとりの空気に影響を与え、それが職場全体の空気になり、結果が劇的に変わる
チームすくりにおいて、リーダーがどんな心でどんな姿勢でどんなあり方で仲間と接しているのか。
それこそが、もっとも大切なことだと感じました。
日々意識をして、自らわくわく出来る仕事をしていきたいて思いました。
5月課題図書【世界一ワクワクするリーダーの教科書】
さすが世界一と謳っている内容でした。ワクワクせざるを得ない好事例、物事の捉え方に関心させられっぱなしでした。パワポの資料の様な文面の見せ方に資料作成の参考にもなるなと。お花見の【予祝】なんかは来年あたりからなすの斎場でも取り入れられてそうな予感が…。最終章での怒涛の詰め方、気持ちの上げ方も読んでいて気持ちの良い物でした。
【5月読書感想文】
ワクワクする。この本を読んで最初に思ったことは、正直、私は結果が出ないと逆にビクビクしていた気がしました。困難を楽しんだり、あそびを入れたりできず、固くなりすぎていたなと思います。それでは、良いチームができない。チーム作り=空気作り=結果を意識、褒め上手を意識し、メンバーさんと接していきたいと思います。野球の例えが多くてわかりやすかったので、すぐに取り入れていきます。そして、自分のまったく使われていない潜在能力にワクワクしながら取り組み、人生の最後に『もっと冒険しておけばよかった』と思わないようにします。
【5月課題図書】
リーダーでなくても意識してできる内容だと思いました。ブラシスとして新しいメンバーさんに対して、相手の変化を望むばかりでなく、自分が見本となるスキルや人間性になることが大切だと思いました。コントローラー型ではなくメンター型で、そして楽しむことができるようにしていきたいと思います。
5月の課題図書
読みやすく読んでいてワクワクする本でした。読みながら考えていたのはリーダーになってからの変化でした。とくに今月はみつわさんに行かせてもらったり、いちかのプランについて考えたり、サンヴィラージュさん勉強会があったりと新しいこと満載でした。それを大変と思うか、ワクワクするかで結果が変わっていくのならワクワクするしかないですね!私は新しいことは好きでワクワクする方ですぐやりたくなる方なので合ってた合ってたと◯をもらった感じでした。仕事のことだけでなく子育てについても書いてあり楽しんでいる姿を息子に見せられるようにしようと改めて思いました。
5月課題図書
世界 一ワクワクするリーダーの教科書。
題名の通りワクワク満載でした。書いてあることが私にとってはプラスに、感じるものばかりでした
夢にワクワクする…常に今まで言われ続けていた事、感謝をし前を向く、難しい問題には面白がる事!
いや、ほんとポジティブになれました。お互いに理解しい人間関係を築く、視点を変えてみる。
長嶋監督に真似て いいところを見つけて書くノート。1日を喜んで生きる。明日からやります‼️
5月課題図書
自己啓発本はあまり好きではないのですがなかなかどうして、ビジョンについてなど明確に記述されている部分も多くなによりも読みやすかったです。
バリュー:変化を好み成長が喜びであること
自分自身が成長を辞めてしまうとチームはもちろんメンバーの成長も止まり、ワクワクしないなと感じました。
不平不満の混沌としたチームと、先を見据えてまっすぐに進んでいるチームでは、後者の方が良い人生になると思います。
自分が変化しなくとも、世の中は、周りは勝手に変化していってるので変化をし続ける、中心ではなく遠心力で物凄い速さで進んで、いろんな景色が見れる外側で居たいなと思います。
【5月課題図書】
大嶋啓介さんといえば、鴨頭さんにもっとも影響をあたえた経営者というイメージがありました。
業績OKRをフレームワークとしている私たちにとって、非常に馴染みやすい思考だと感じます。「わくわくが源泉」。楽しいが人の潜在意識を引き出す一番のポイントであることには納得です。社長も以前から意識されている予祝についてのロジカルな説明が腑に落ちました。2033年2000件あめでとうございます!!
なぜポジティブがいいのか?
なぜ笑顔がいいのか?
なぜ感謝なのか?
そう考えるとまさに教科書的な一冊だと思います。これからも実践していきます(^^)/
5月課題図書
とにかくワクワクしてしまう内容でした。「思い込み」は6歳までに85%つくられる。思い込みが過去の経験や体験から作られるのであれば、思い込みを変えようと、変えたいと思いました。「予祝」ワクワクしますね。業績でワクワクすること…よく言われますが、目標達成がゴールではなく達成後のことを広く考えようと思いました。
月課題図書【世界一ワクワクするリーダーの教科書】
これはどんどん自分でも実践しなきゃいけない内容だと感じました。
成功したからワクワクするのではなく、ワクワクしているから成功している。ワクワクはチーム内で雰囲気を良くし、結果を最高のものに変えるなど確かになと納得する内容ばかりでした。
それはどんなチームにでもいえることで、予祝することで得ることができる。予祝という言葉を初めて聞きましたが、実際に予祝を行うことで夢を引き寄せる=ワクワクすることで、潜在能力を解放し、最高の結果を出すことだできるのだと思います。
常に笑顔で、楽しくあり、ワクワクする妄想をすることを癖づけて、楽しめることを探しながら楽しいチーム作りを行っていきたいと思います。
5月読書感想文
私生活、仕事でワクワクしているか・・・。50%くらいかなと思いました。
OKRのオブジェクトのところの重要性がわかりました。チーム目標を考えるうえで自分、メンバーがワクワクしない目標では結果が変わってくると思いました。ネガティブ部分を見せないように心がけていましたが、心からポジティブに心に素直に生活できたらワクワクの時間が増えて楽しい人生になるなと思いました。ワクワクを波及させるためにも表現の仕方も重要だと思います。
ネガティブな思い込みはやめにして、ポジティブ思考で潜在意識に目を向けると、これからもまだまだ自分には成長の余地があると思いました。
ポジティブな想像をする時間をつくろうと思います。
5月課題図書
ワクワクが与える影響、職場でも家庭でも子育てでも、理解出来る内容でした。そして読み手の私も読み進めていて、ワクワクしました。ワクワク、楽しむことってほんとに大切ですね。予祝ヒーローインタビューなんかは今後入社させる方へのワークの1つとしてやると面白いかもと感じました。あと、困難やピンチのときはウェルカムピーンチと唱えるようにしようと思いました。
余談ですが、学生時代、居酒屋てっぺんの朝礼の動画を見たことを思い出しました。なかなかの迫力で、あの居酒屋で働くの楽しそうと思った記憶があります。既に私は大嶋さんにワクワクが仕掛けられて(仕掛けられた)いました。
5月課題図書
本の中で「ワクワク」という単語がゲシュタルト崩壊しそうなほど使用されていて、改めて「ワクワクする」ってどういう事だろうと考えながら読み進めました。
途中途中に、面白い事例やワーク的な要素もあり、楽しく読了できました。私自身仕事の中でどれだけワクワクする気持ちがあるかというと答えに困るのですが、新人さんに教える中で、新人さんが楽しく社会人生活を送れるようになるためにも、私も「ワクワク」を持ちながら教えていかなければ、と思いました。
余談ですが、私が頂いた本書にドッグイヤーの跡が多数あり、前の持ち主はこのページのどこに感銘の受けたのかな、と想像しながら読みました。何人かの方が触れいている「予祝」のページにもばっちり跡が付いていました。
5月感想文【世界一ワクワクするリーダーの教科書】
リーダーでなくてもとてもワクワクする内容でした。リーダーの空気で結果が決まる、それはあると思いました。周りに影響が出るのはもちろんだと感じました。可能性を信じることでワクワク度がUPするので思い込みで頑張ろうと思いました。笑顔でポジティブでいようと改めて思いました!
【5月課題図書】
タイトルの通り、ワクワク!これに尽きる本でした。リーダーがワクワクしていないのにチーム皆のモチベーションが上がるわけないということ。そして結果に直結するのはとても面白い内容だと思いました。困難にぶつかった時にワクワクすることで乗り越えられ、その時の経験値もそれぞれ変わっていくのだというのを実感した本でした。これから様々な計画を立てていく中で常にワクワクしていこうと思いました
5月課題図書
ワクワクでしか成功は続かない、ワクワクしているのすごく重要だと書かれていましたが最近ワクワクを感じられる、感じることが少なかったなと振り返りました。というよりワクワクは何か楽しみなことがあるとかではなく自信の気持ちの持ちようだとこの本を読んで感じました。
アメリカのある地域の90歳の方へのアンケートで人生を振り返ってもっとも後悔したことは?という質問の答えでもっと冒険しておけばよかったという回答には自分も少なからず同じことを思うだろうと別な意味で共感してしまいました。また人生でうまくい人といかない人の決定的なことは思い込み差、できないと思い込んでいたことが多かったので思い込みを変えれば結果が変わることを参考にしたいこうと思います。
『何をするか』の『やり方』ばかりを重要視してしまいがちだか、どんな素晴らしい方法も,無理にやらされてやっていたり,ダラダラした心でやっていては良い結果は出ない。究極のリーダーたちは,この『どんな心で』の“心のあり方”を重要視し,意識を向けている。だから,結果も人生もどんどん良くなる。最高の未来のつくり方は,『今の心をワクワクさせること』。どのような状
況であったとしても今の心をワクワクさせる。成功したから幸せになれるのではない。先に幸せであることが成功を生む。
自他共に認めるネガティブですが、だからといって常にネガティブで生きているわけでもなく、ポジティブでエネルギーに満ち溢れる自分もいることも自覚しています。ネガティブな思考の全てが悪い訳ではない。ポジティブな自分でいられる時間を少しずつ長く保つことが出来れば、大きく成長できると感じられた一冊でした。
【課題図書】
自分のワクワク‥‥‥‥‥何だろうと考えた時、自分の好きな事、大切な家族の為にしてあげたいサプライズ等を計画している時です。その他の時は、やらされてる、やらなきゃいけない‥‥なんて事しか考えて居なかった気がします。しかしこの本を読むとそれ以外のワクワクが有るとことも知り、目標や、夢へのワクワクも持つべきだと思いました。無理矢理持つのでは無く、心の底から持ち、思いを深めていく事の大切さも学びました。もう少し視野を広げ色んな事にワクワクして行こうと。
今からでも自分でワクワクを作ることは出来ると思うので早速明日のワクワクを作っていきたいと思います。
五月課題図書
ワクワクするというとても前向きな言葉で引き付けられた本でした。前半戦は、気持ちの持ちようで自ら楽しむことも、苦しいと思うこともできるという精神的な話でした。日々の仕事も、本当にこういった事が大切だし、突き進む原動力になるんだと改めて思わされました。
P71の表題『誰だって、どんな出来事でも楽しくできる』これは心に刺さりました。不満だらけの世の中ですが、それをどう楽しくやって成果をあげるか!!明日と言わず、今日から実践していきたいです。
5月課題図書
仕事の面、リーダーとしてという面でももちろんですが、個人的には子育てにおける核心を突かれるような話が多々あり非常に目からうろこでした。「できないという思い込み」や、「人間は本来ポジティブ」というエピソード、これらを気を付けることは子育てはもちろん、リーダーとしてスタッフに対応するときでもとても大切なことだなと感じました。
親がこうだと決めつけてしまうと子供(部下・スタッフ)は本当にそうなってしまうので、決めつけはせずに、すべての可能性を信じて進んでいきたいとこの本を読んで思いました。どんな時でもポジティブに考えていきたいと思います!
5月課題図書
結果として人生をワクワクしようという冒頭から話がまとまっているよう感じた書籍でした。
この本を読みながら私は自分の人生をワクワク過ごせているだろうか?結果はYESです。
今仕事をすることも楽しいしプライベートも順調に楽しいと感じています。
それをリーダーとして周りにどのような影響を与えていくのか。リーダーの雰囲気で職場はガラリと変わります。いつかの課題図書で読んだヌシを作らない、ごもっともだと思います。責任はありますが当社のクレドのような同じ目線で業務に励んでいけたら益々素晴らしいワクワクが体験できるのではないでしょうか?
5月課題図書
大嶋啓介さんらしい分かりやすく、ポジティブな内容が詰まった1冊でした。本書、夢が叶う叶わない人の共通点。当時この項目に沿って物事を選択し、結果、私はなすの斎場と出逢って入社したなと思い出しました。マイナスの言葉ばかりが出たとしても、信じて背中を押す、そこにわくわくを埋め込める作業を追加しようと思います。他力本願や思い込み、そこから離れ、物事を素直に受け止める思考があれば、わくわくするに繋がると思います。ティール組織を考えていく上で、全体的がこの思考があればこそ成り立つだろうなと再認識出来ました。
5月課題図書
リーダーにとってワクワクしていることは重要なことだと知りました。
「楽しめば楽しむほどうまくいく」「遊べば遊ぶほど、うまくいく」それこそが夢の叶え方だと思っていませんでした。リーダーのメンタルがチームの空気をつくり、結果をつくるはなるほどと思いました。
社長がワクワクする目標と言っているのを思い出しました。
目標達成できないのはワクワクしていないから、夢にワクワクしていないからというのもわかるなーと思いました。これからはワクワクする時間が増やせるようにしたいと思いました。
5月課題図書 ※遅くなり申し訳ありません
これまで読んできたリーダーの教本は、「つよいリーダーシップ」を発揮することに焦点が当てられ、メンタル面についての補足がなかったことを本書を読んで実感した
「仕事や逆境を楽しむ」というメンタルが好調を呼ぶ、というのは個人的にはオカルト的に感じており、あまり波長の合わない考え方ではあったが、新たな面を学べたと感じた
特に、失敗を恐れずに走りながら覚えていく、と成長する、といった点は、以前の自分にはなかったが、最近その考えが自身の元になっているのは、リーダーとしてのメンタルの変化を、本書から逆輸入できたように感じた