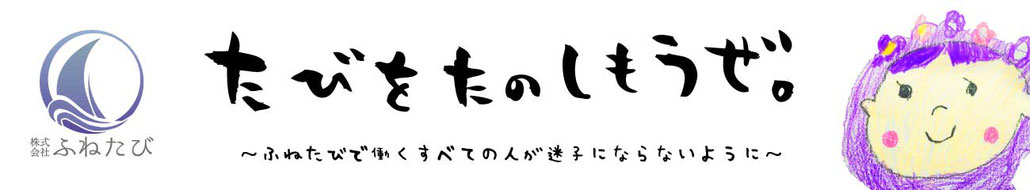【2.3月課題図書】
理論的思考、逆説思考、さらにはロジカルシンキング、クリティカルシンキング、ラテラルシンキング、加えてデザイン思考と、思考の種類の多さに加え、プラスアルファの思考術を学ぶにはかなり困惑しながらも、目の前の図書だけに、と集中して読み進めた図書です。
人間の行動は新しいサービスを受け入れることによって変化している、それはユーザーが受け取るサービスやプロダクトの価値が値段や機能性より、どんな体験ができるのかということに変化していきているということ。そのため、使う人のニーズを正しく理解し、課題を見つけ解決に導くためのクリエイティブな考え方であるということを理解しました。内容も、問題定義後の共感、定義、アイデア、プロトタイプ、テストの5段階を経るとそれぞれの項目を理解しました。まずはニーズを的確に把握することが必要です。
今月のオーディオ課題図書では「人の心を満たすものがサービスになっている」、本書では「以前と異なり生理的、安全的欲求(マズロー5段階接)が満たされているからこそ次の段階へ進む」と、同様の内容でも異なる見方、伝え方の大切さを得られたことは次へ繋がる成長の一歩でもあります。また数ある思考種類の中で、課題目的にあった思考法を選択する必要性も感じました。正直〇〇思考が○○には適しているまで順序だてて整理できていませんが、必要な時に手に取る図書が近くにあるのはとても有難いことです。変化を好み成長するための大切なツールの1つです。
他人の気持ちに共感することがこう見えて一番苦手な自身ですが、その中でも「よしやろう」と思えた自分を思い返せる気づきをくれました。自分1人では何もできない、正しいものを正しく作る、創出していくための過程を何かに活かせていきたいと思います。今月も大切な気づきとその機会を与えてくれた図書と社長には感謝します。突出したものでなくても、日々見える景色に小さな疑問を覚える自分になっていきます。
2月 3月課題図書
この本を読ませていただき、特に興味あった内容として、デザイン思考を学ぶとは、マインドセットを変えるという事。=考え方と書いてありました。初めて聞く言葉で日常でも使える内容だと思いました。
私の不得意な内容で、【答えを提案しない】話し手が答えに詰まって口ごもったとしても答えを提案して助けてはいけません。自分の期待通りの事を言わせるのではなく、話し手側から出てくる言葉を静かに待つという事を私が出来てない部分があるのでそこをマインドセットという事で自分の改善点を意識したいと思います。
この本を通して、これから何をするか?ここを意識していこうと思いました。
2月3月課題図書
人々が直面する問題解決=デザイン思考。解決に対するアプローチがわかりやすく、特に冒頭5段階のプロセス。10種類のアプローチ(構築するアドバイス)が本当に良かった。クレーム改善、新商品開発などあらゆる物事に有効に対応できると感じた。いつでも見返せるように自分なりにまとめた物をデスクトップに残しておこうと思った。問題や改善策の実例も多く現状の業務に落とし込んだイメージが描きやすかった。あと挿絵がとてもかわいい。
2月3月読書感想文
デザイン思考のポイントとして、人を挙げているが、『人間の行動は新しいサービスを受け入れることによって変化しており、私たちは常に人々が何か困っていないか、不便に感じることを改善できないかと考える必要がある』という部分は、まさにクレドのバリュー、変化を好み成長が喜びであるという部分と通ずると感じました。それと、自分で作るツールキットの存在は有効的で実際に使用しての実践はチーム内でやってみたいと思います。
2・3月課題図書
デザイン思考と題名にあったのでデザイン関係の何かかと思いってましたが全くそんなことなくマインドセットという本当の問題を解決するたの考え方を知るためのプロセスの事例であり実際のインタビューなど実践されて得たデータや分析なのでとても説得力を感じました。共感、問題を見つけるための情報を集める、実際にお客様対応から問題解決につながるヒントをもらえる可能性もあるのではないかと思うのでちょっとしたご意見でも情報を集められるようお客様との対話を実践していこうと思いました。スタンフォード大学は授業も受講するのに履歴書並みの自己アピールが必要で選考を通過したあとも欠席は認めず受講したくてもできなかった学生がいることを理解して誠実に参加を求めていると書かれていたことが印象的でした。アメリカ大学ランキング3位に入るトップレベルに求められるものは格が違うと思いました。タイプ別のユーザーの例は分かりやすく葬儀社関係でいうならどんなお客様が当てはまるか考察してみようかと思います。
2月3月課題図書
デザイン思考を読み、文中にあった我々アジア人とスタンフォード大学の方々の学び方の違いといった(前の講義で疑問に思ったことをピックアップしておき、次の講義で質問できるように備える)ここの常に学ぶ姿勢を持つといったところがバリューにも繋がるし、デザイン思考を学ぶ上で必要になってくるのだと理解できました。
また、デザイン思考のプロセスやツールキットを今後活用していこうと思います。
「スタンフォード式デザイン思考」
・問題が何であるかを正確に把握するために、ユーザーの視点やニーズに焦点を当てる。(ユーザーと対話をして調査をする)
・問題の根本原因を探るために、反復的に「なぜ?」という質問を繰り返すことが重要。
・アイデアを生み出す際には、従来の考え方にとらわれずに自由な発想を大切に。グループでのブレインストーミングやアナログ思考を活用することで、新たな視点やアイデアを生み出すことが出来る。
問題解決には創造性や柔軟性が不可欠であることを理解出来ましたが、横文字で頭痛のする内容でした。
2・3月課題図書
スタンフォード式デザイン思考
うん、うんうなずきながら読み進めることが出来ました。 相手の言葉を待つ、答えを待つ。沈黙が苦手な私の課題です。もしこうなったらどうする、を意識してみること仕事の会話も楽しいだろうなと思いました。共感する事かポイントになり、なぜ?と相手に疑問を問いかけてみようと思います。
昔より本を読んでいて納得し、日々の仕事に結びつけて考える事が出来るようになった気がします。
2月3月大人の感想文
デザイン思考について以前花浄院さんで研修を受けたことがありますが、あまり記憶に残っていなかった為、改めて考え方の引き出しが増えました。実際に先日行われたワールドカフェもユーザーをスタッフとしてブレスト、課題解決に向けての課題の可視化など、本書に該当する内容だったと理解しました。ユーザー=顧客だけではなく、チームミーティングなどでも活用できたらと思いました。課題解決に対して、ブレストがしっかり出来ないと意味がないとも理解したので、上記に合わせ、ブレストについてもより多くの意見を出すにはどうすればいいのか、考え方の引き出しの増やし方についても学びたいと思いました。
2.3月課題図書
スタンフォード式デザイン思考
デザイン思考とは?と思いながら読みましたが
人々のニーズや問題解決をするための考え方であり
様々なところでデザイン思考が組み込まれていることを理解することが出来ました。
また、デザイン思考を実践するには周囲の環境づくりや気を配る場面が多くあり中々難しいものだなという印象も受けました。
一定の考え方にとらわれず自分なりに自由に発想を大切になど活かせることが多くあったので意識していきたいと思いました。
2・3月読書感想
やはりほかの皆さんと同じく「デザイン思考ってなに?」からの入りでした。映画や大学の講義の話などを入れながら、おそらくできる限りわかりやすくデザイン思考について書いてあるのだと思いますが、内容が難しくて「読んでるが頭にはいていない」状態になってしまったかもしれません。
ただその中でもファシリテーションの工夫やブレインストーミングのコツなど、日常の仕事に活かせる内容も多々あったので、すべてを理解することは難しくとも、せっかくなので覚えたことでできることは一つ一つおこなってみようと思います!
課題図書
全体的に考え方のポイントなど理解するのに時間がかかりそうだと正直苦手意識のまま読み進めました。苦手意識のままだったので頭に入ってない感じですが、その中でも学びや発見はないかとおもい、勉強になったところはインタビューのところで答えを提供しないとか矛盾を探せなど掘り下げていくなぜ?を使う相手に興味を持ち想像していく。1on1でも使える部分だと思いました。
課題図書
タイトルを聞いてデザイン系の話かと思い込んでました。問題にぶつかった時などの考え方についての話でシンプルでわかりやすく、自分にもできることがあると思いました。
一つドキッとしたのが、沈黙の時間を待てずに答えを出してしまったり、自分の望む答えを言わせようとしているところがあるな、と反省です。
3月課題図書
デザイン志向ってなんだろうと思っているところから始まりました。この本はデザイン思考を実践するための方法が具体的で分かりやすい内容でした。デザイン思考とは人の抱えている問題やニーズを解決する考え方のことでした。デザイン思考のことだけではなく、ファシリテーターやチームビルディングのことも改めて学ぶことが出来ました。問題点を見つけてニーズを満たすことが成功の秘訣だと思いました。
2月3月読書感想文
「スタンフォード式デザイン思考」
すべての中心には人がいて、人こそがサービス、製品、「システムのあり方に影響を与える重要な要素であり、特定の人の問題やニーズを知り、解くための考え方。共感→問題の定義→アイディア→プロトタイプ→テストをいったり戻ったりしながら進むこと。
なかなか難しそうな内容だと思いましたが、実際に全社クレドで行ったワールドカフェのようなブレストに近い内容だと感じました。
チームの課題など、ディスカッションし、課題が何かを共感すること。良いところを伸ばす前提をひっくり返しアイディアを出すこと。失敗してもいいので試すこと。こうすることでチームにおいての課題を体現をデザインでき、コミュニケーションをとることが出来るので今後積極的に取り入れていきたいと思います。
2・3月課題図書
「ここでお伝えする好奇心とは(196P)」の一文が刺さりました。私は多々、知っているふりをしてしまうことがあるからです。
実際、マズローの5段階欲求などは知っているからとそれ以上、現実の、自分の問題に引き寄せて考えるということをしていません。Google検索もよく使用して、一時の知識で何事かをわかったような気になりがちです。
頭でわかっていてもやらない、やれない、そもそもわかった気になっているだけで理解が足りないことがこの本にはたくさん載っているので、実際にやってみる、体験するところまで落とし込みたいですし、葬儀社であることを念頭に置いて具体化したいです。
指摘されて気付くこともまだまだ沢山ありますが、言わせてしまうのではなく、自ら想像し、考え、時にこちらから関心と好奇心をもって聞いていけたらと、前向きな気持ちになれる本でした。行き詰まりを感じた際には何度でも手に取って読み返そうと思います。
「スタンフォード式デザイン思考」は、問題解決においてユーザーの視点やニーズを重視し、問題の根本原因を探る際には「なぜ?」という質問を繰り返し、自由な発想を大切にする。これにより、創造性や柔軟性を活かして新たな視点やアイデアを生み出すことができる。この方法は、問題解決に取り組む際とても重要だと思い、参考になりました。
2月3月課題図書
デザイン思考とは…「人々がもつ本当の問題を解決する」ためのマインドセット。
日々、何か問題はないだろうか‥この問題は解決できるだろうか‥など物事を考える時間を作ろうと思いました。そして、自分の周りにいる人に共感を示そうと思います。日常的に気をつけて取り入れていこうと思います。
2月3月課題図書
デザイン思考とは…「人々がもつ本当の問題を解決する」ためのマインドセット。
日々、何か問題はないだろうか‥この問題は解決できるだろうか‥など物事を考える時間を作ろうと思いました。そして、自分の周りにいる人に共感を示そうと思います。日常的に気をつけて取り入れていこうと思います。
読書感想文 スタンフォード式デザイン思考を読んで
冒頭のすべての中心には人がいる。という部分から改めて社訓である「ぼくのおばあちゃんにしてあげたかったお葬式」という考え方をデザインしているのではないかと思いました。繰り返しやって身に着ける、実際に手を動かしてやってみる、日ごろの業務の中にもまずはやってみる…クレドキャンプでの実践なども含め、経験則に沿って自分に落とし込むに…何かスポーツや運動などに近いものを感じました。
・こんなインタビューはだめ絶対・うまくいかないインタビュー・話し手と目も合わせない・インタビューさせてもらいたい理由・用意された質問リストに沿ってさっさと質問しようとする・事務的に「今日は質問があります。〇〇です。はいはい。なるほど。わかりました」と聞いてパソコンに打ち込むだけという、ある種事務的作業な部分は自分にも思い当たる節があり気づきを多く得られました。特に朝礼でファシリをさせて頂くことも多いので、物事に対して深堀するという部分を意識しながら取り組んでいきたいと思います。
2月3月課題図書
一般的なデザインという言葉が頭の中にあったので、その分野が苦手な私は正直うわっと思いながら読み始めましたが、ここでのデザイン思考とは人々の問題解決のための考え方という事がわかりました。
問題や改善方法の事例も多く、普段の業務にも行かせる内容だったと思います。
また、インタビューのこつの部分で、答えを提案しない・沈黙を恐れない・非言語の手がかりに気づけという部分が、当家様との打ち合わせや、スタッフ同士のコミュニケーションをとることの中でも活用できるかなと思いました。
2・3月課題図書
共感、問題定義、検証などはマーケティングとリンクするところがあるなと感じましたし、マーケティングに活かせるところがあるなとも思いました。問題解決策ですが、ここでもやってみる事が重要だと思いました。失敗は一つのプロセス!
1人で息詰まるのではなく、チーム内外でブレインストーミングのような意見出しを頻繁にやっていこうと思います。
ツールキット時間を見つけてやってみようと思います。
2・3月課題図書
共感、問題定義、検証などはマーケティングとリンクするところがあるなと感じましたし、マーケティングに活かせるところがあるなとも思いました。問題解決策ですが、ここでもやってみる事が重要だと思いました。失敗は一つのプロセス!
1人で息詰まるのではなく、チーム内外でブレインストーミングのような意見出しを頻繁にやっていこうと思います。
ツールキット時間を見つけてやってみようと思います。
2-3月課題図書
デザイン思考について理解を大きく深めることができた
例えば、「つむぎ西那須野のシェアを拡大化する」という目標を掲げた時、これまでを振り返ると「ポスティングを500枚行う」「イベントに10名以上集客する」といった、経過や命題的な点から手を付けていくことが多かったように感じた
本著を読み、「つむぎ西那須野エリアに住むお客様は、他者と比べどういった利点をつむぎ西に見出すのか」と、新たな切り口で考えることができた
また、さらにデザイン思考を深めるために、実践やプロトテストなど、ニーズに理解に関わる手法を学ぶことができた チームビルディングについてもいくつかのワークが紹介されていたので、今後のチーム運営にも活かしていきたいと感じる
2.3月課題図書
デザイン思考とは、、、でしたが、読み進めていくと自分の今までの思考とは全く違うということを思い知らされました。思い込みがある分、違う視点からの思考を生み出すというのはなかなか難しいので徐々に実践して思考を柔軟にしていこうと思えました。人が増えていき、多くの思考が飛び交う中でもプロセスを守り新たな発見を見出していきたいです
2.3月課題図書
デザイン思考とは、、、でしたが、読み進めていくと自分の今までの思考とは全く違うということを思い知らされました。思い込みがある分、違う視点からの思考を生み出すというのはなかなか難しいので徐々に実践して思考を柔軟にしていこうと思えました。人が増えていき、多くの思考が飛び交う中でもプロセスを守り新たな発見を見出していきたいです
2月3月課題図書
最初の題名でデザインの本なんだなと思い開いたところ難しい内容がたくさんでした。デザイン思考とは問題や不安を解決に導くことなんだとわかりました。人それぞれ考え方が違う分ニーズが違うがそれをどのようにして解決していくのか。。。とても奥が深い内容でした。葬儀もお客様が値段や機能性よりもどんな体験ができたかが1番大切なのかなと思いました。私も今後、相手に寄り添うことができるように頑張りたいと思いました。
人々が必要としていないものが優れたUXをもつことは、単に彼らがそれを必要としていないことを理解させることにすぎない。
この本は、全てがこの1文に集約されておりました。本書は、これの為に書かれた本でした。これ以上でも、これ以下でも無い。読んだ人なら説明不要だと思います。ただ最初にこの1文を読んだ時は、理解するのに3回読み直し、なるほどなってなってからは、そりゃそうだろう。当たり前だろ。って思いましたが、実際の行動を見返してみると、それに反した行動、計画の方が多い事に気が付かされました。葬儀こそ、ホスピタリティーが大切な業界ですが、現状は従来の会社のように、数字を追っ掛けてて、数値が低い時には低い理由を探し、目標数値に達する為に、何をするかになっている。そもそも本書とは根本が逆でした。後半では、チーム単位レベルに落とし込む事で理解を深めようとしましたが、そこはなんとか理解出来ます。しかし、それを顧客に拡げる考え方をしようとしたら難しい。分かりやすく書いていないので、髙橋さん、藤田部長も書いていましたが、難しいです。これの本質を理解して、仕事に落とし込めた時は、スーパーサイヤ人みたいな、すげー奴になってるんじゃないかなとのワクワクがありました。
2.3月課題図書
新しいことを何かやる上で必ず必要になってくる考え方だと感じました。
この本にあったプロセスの考えを忘れずに、なすの斎場のイベントなどで皆様が楽しんで行けるイベントを作って行ったり、どうすればお客様に寄り添えるかなどを念頭において業務に取り組みたいです。
投稿忘れてました。
申し訳ありません。
2.3月課題図書
デザイン思考」とは何か、言葉は聞いた事はありますが、あまり聞き慣れない言葉だったので、知ることができました。
本当に必要なものがなんなのかを理解するためにデザイン思考は必要だと感じました。
チャレンジすることが大事だということ。
そして、デザイン思考は、実践して理解をする事だと感じました。
デザイン思考は、すぐに身につく事ではないので、少しずつ、身につけていく事が重要だと感じました。