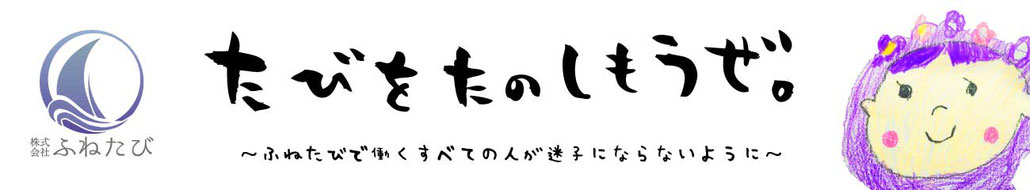【11月12月課題図書】
帰宅した娘が「今回はユニクロ!」と図書を見つけての第一声。小学生、高校生、中高年、そして年配の方にも知られている“ユニクロ”認知度が高く、服やブランドに無頓着な自身でも知っているほどです。初めて知ったユニクロが東京であったことから、第1号店は東京だと勝手に思っていましたが、第1号店は広島と知り驚き。そこから世界へと名の知れるブランドになるまでの長い歴史を知ることができました。“世界は繋がっていた”エピローグから読みだした自身に壮大な歴史の流れを想像させながら、耽読。現実を忘れる瞬間もこの図書の良さでした。
時代の波に取り残された、商店街のシャッターからの始まり。物語は足し算と引き算の積み重ね。「信用」から学び「信頼をひとつずつ積み重ねる」努力。原点は何も見えないなかで、なにかをみてやろうと思い描くひとりの青年の情熱が造り上げた“ユニクロ”、戦後の混乱期、高度成長期、オイルショック~リーマンショック、コロナショックなど様々な時代背景を経て、そして未なお再成長期。引き算の数々を足し算に変えていかなければならない、たとえようのない響きです。
初期には17か条あった経営理念が今では23か条、中でも“社会を変革し社会に貢献する経営”には、弊社のクレドに繋がる感覚でした。ユニクロとは何か、ユニクロの服とは何かを問い続ける姿勢を、なすの斎場の葬儀とは何かと問い続ける日常に置き換えることもできました。また、“会社というものはすべての働く人たちや関わる人たちにとってユートピアであるわけではない。その規模が大きくなればなるほど様々な矛盾と直面し、それが組織の中でも見えづらくなっていくものだ、そんな矛盾とどう向き合うのか“の文面にはなすの斎場の100年物語の課題”そんな矛盾とどう向き合うのか“と提言してくれているようでした。
村上春樹氏の図書に触れたことはありませんが、「両手が血で汚れている、それを拭えるようなハンカチはこの世界のどこを探してもない~」の演説が記憶に残っている自身にとって「壁と卵」は衝撃でした。取り組む仕事の理由が何であるのかと問いかけられたようです。以前の課題図書同様に、明確な答えはでずとも今ここで働くことが「楽しい」と感じられる自身を取り戻していきたいと思いました。今月も大切な想いに気づかせてくれた図書と社長には感謝します。終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りの力をだせる力を今は温存します。
伊藤美保子
【11.12月課題図書】
杉本貴司の著書『ユニクロ』は、柳井正氏の経営哲学とユニクロの成長を解釈した内容でした。柳井氏が無気力な青年から世界的なアパレル企業の創業者へと成長する過程が描かれています。特に印象的なのは、「売れるものをつくる」という理念です。この考え方は、単に商品を販売するのではなく、顧客のニーズを的確に捉えた商品開発を重視する姿勢を示しています。
柳井氏は、目標設定と計画の重要性を強調しており、成功には綿密な準備が不可欠であると書いてあります。彼の挑戦と失敗を繰り返しながらも、常に学び続ける姿勢は、私に置き換えても仕事や人生において直面する課題に対するヒントを与えてくれます。
また、ユニクロの成長は、単なるビジネスの成功にとどまらず、社会的な課題にも向き合う姿勢を持っています。ブラック企業批判や環境問題への取り組みなど、企業としての責任を果たす姿勢は、現代のビジネスにおいても重要な要素だと感じます。
この本を通じて、柳井氏の内省的な思考や挑戦する姿勢に触れることで、私自身も新たな目標を設定し、計画的に行動することの大切さを再認識しました。『ユニクロ』は、経営者やビジネスパーソンにとって、非常に為になりました。
田中 勝
11月・12月課題図書
ユニクロを読んで思ったのが、やる気があって何事も挑戦続けていけば何とかなる。そして誰にでもチャンスがあるという事が教えていただけました。
社員のモチベーションも高く試行錯誤しながら成長していく姿を物語っておりとても興味ある内容でした。色々アップデートしていく必要があり、足し算引き算の繰り返しという事で私の人生の教訓にもしたと思いました。ビジネスのリアルを体験出来たような気がします。
ユニクロから学んだ事で、どう考え抜き、どう行動するのか?このマーケティング実践本で得たヒントを活かして茨城で実践させていただきます。
月井 優二
【11月12月課題図書】
顧客のニーズをどう掴むか、大ヒット商品の販売はどのように至ったのかという話もあるが泥臭い人と人とのつながり方や向き合い方が印象に残った。キャリア、年齢、国籍までも違う人たちにもっとユニクロらしくという文化を浸透させる為、結果それが人材育成になり社員が主体的に成長できる環境に繋がったのかと感じた。
章としてはGU設立の話が個人的に良かった。企業と現場と顧客ニーズのズレが大きくそこから再建の話など。ベースとなる基準は必要だが結果自分たちが好きな物、身に着けたい物を提供する事が良いよねって話。自分たちが良いと感じる物を自信も持って提供する、その物の価値を向上させる事を続けていきたいと感じました。
市村恵
11,12月課題図書
社会的に成功した人物について書かれた本の多くが家庭環境まで詳らかに書くのは、その人の成功になくてはならない伏線になっているからだと感じます。海外に行くという息子さん(柳井正氏)に約200万円(当時の価格相場からすると現代の何倍もする)を出せる親御さんあってのストーリーかと思うとあまり共感もなく読み進めたのですが、読書好きという点で興味が湧きました。私も松下幸之助氏と本田宗一郎氏の本を好んで読んだ時期があります。柳井氏ほどお二人の哲学にのめり込まなかったのは、経営が自分事ではなかったからです。一時期プレジデント等のビジネス雑誌は経営者の心得やインタビューが満載でした。私はそれぞれの経営に通底する深い思考、学び続ける人格に触れるのが楽しかったのですが、知ったかぶりにも陥りました。そうした経験の中から学んだのは、大企業経営者の人生を文字で追ったとしても、経営者視点を知ったと驕るのではなく、自分だったらこうした危機のときにどうするかを考える機会にするということです。そもそもビジネスにおける本質的な危機的状況は、雇用される側の私では大して知らないままです。実際に胃を痛めながら背負って考え続け、どうにかしてきた人(経営者・経営層、つまり社長)と自分自身の差を知るしかありません。そういう意味では「泳げない者は沈めばいい」の件が堪えました。
ユニクロは一部店舗で生花事業も始めています。あまりそこに関心を向けると感想文とは離れてしまうのですが、これだけのことを乗り越え進んできた方が花に着目するということが、少なからずうれしいです。UNIQLO FLOWERはコロナ禍において柳井社長提案で始まったらしいですが、UNIQLOの発展で培ったマーケティング手法を活かしているらしいので、きっと学ぶことが多々あります。
実際の店舗に行くなどして、本から得た知識で留まらず現場からも学ぼうと思います。このような読書機会をいただき、ありがとうございました。
赤羽根奈央子
11、12月課題図書
ユニクロオープン初日から行列ができるほど人気その時代にはなかった接客はあまりしないやり方、今では当たり前でそれが逆に店に入りやすいし出やすい。ヒントがキャンパス内にある大学ショップそこからコンセプトとしていつでも誰でもすきな服を選べる巨大倉庫なるほど!でした。今でもそのコンセプトがそのままなのがわかります。
もちろん長年会社をやっていれば色々なことがあってあたり前ですが、やはり勉強すること(本を読んだり)アンテナをはっているからこそ行った先々で発見があるのだと思いました。わたしも出かけることはあまりないにしてもアンテナをはりいろんな発見、ヒントをひろっていこうと思います。
星大地
課題図書
経営的なことだけが書いてある本なのかと思っておりましたが、マネジメント要素もあり面白く読めました。
特にレジのスマート化などデジタル化が進んでいそうなユニクロでも人材育成が成長を支える柱になっているという点は現代社会でのブランディングの大きな部分だと思います。
服を売る販売員、ではなくCXをデザインするプロフェッショナルである。というスタッフの目指す像がしっかりと設定されている点も目的があって素晴らしいと思いますし、陳列等細かいところまで重要視する点も葬儀においても重要だと感じました。
失敗を恐れない。とありますが企業が黒字なら黒字なほどこれが言えるのだろうと思いました。
赤字であれば、失敗が怖くチャレンジもできず働き甲斐も損なわれると思います。これがやりたい、やる理由は?成功する確率は?その根拠は?データは?
毎度毎度それを議論するのではなく、ユニクロ大学を経て店舗運営力を培い自身で決裁ができるからパフォーマンスに基づくしっかりとした評価基準があり早期出世が可能で公平な能力主義が実現できているのだと思いました。
凄い、としか言いようがなかったです。
真家 直美
11・12月課題図書
ユニクロを読んで感銘を受けました!
人の人生は、多かれ少なかれ挫折をし、日々学ぶこと。
その中で【チャレンジ・失敗を前提】が私にかけていることと思いました。
しかし、弊社に入社してチャレンジができる環境、失敗をしても改善・提案してくれる環境で、私にできる(したいこと)をして、当家様につむぎ石岡を選んで良かった!と言って貰えるように寄り添い・葬儀が当たり前にならず、その都度、自分だったらこうしたい!こうして欲しい!と思うことを提案して、つむぎの良さを分かって貰えるようにしていきたいです!
そう、出来るように今出来ることを考え、コミュニケーションを図ることで、アイデアが浮かぶので、私に出来ることをチャレンジしていこうと思いました。
相馬親太郎
【11.12月課題図書】
初めに、柳井氏の寝太郎の話しは以外でした。そこから、ここまでたどり着くストーリーはとても読み応えがありました。私もアパレル事業をやっていた経験があり、さらには失敗したので、どうやったら成功?したのか、とても学びになりました。第5章のフリースやユニバレの内容は、世代的に経験していたので、業績が良い会社のイメージでしたが、裏ではこんな大変だったことに少し驚きがありました。ただ、その中で経験する失敗を成功の気づきに変換してしまう考え方や、広い世界を観察する思考、勇敢に人と違ったことをすること。そして、あたりまえですが、与えられたものを売るのではなく、やはり売れるものを作る。服を葬儀に置き換えて、考えていきたいと思います。
藤田 裕子
11-12月
課題図書
ユニクロは身近にある誰でも知っている会社
究極のゴールを見据えて果敢に挑戦する。多くの失敗を経験しながらも他と違う事の発想で進んでいく。常に時代を先読みし未来を予想しながら生まれ変わっていく会社。失敗を次の成功の気付きに変えることが書かれていていました。ユニバレ、ユニクロ世代ですが初めて聞きました。GUが弟分だという事も知りませんでした。本で学ぶ事たくさんありました。また点と点が繋がることは後になって分かる事、自分たちの仕事にも当てはまると思います。変化を好み成長が喜びであること…私たちのクレドに似たもの、違うと感じた時原点に戻る、私たちも真似をしながら進み続けて行かないといけないと思いました。
2024年12月27日 10:26
渡邉翔哉
11,12月課題図書
印象に残っているのが「売れる服をいかにつくるか」という考え方を大切にしていた点です。
これは只作ったものを売るだけではなく、まずお客さんが本当に必要としているものを考える必要があります。たとえば、ユニクロが「フリース」で大成功した背景には、寒い冬を快適に過ごせる服を求める人々のニーズをいち早く見つけたことがあると書かれていました。
これは葬儀社でも同じで遺族のニーズをいち早く見つけた会社が成長し、生き残ると感じました。
2024年12月27日 10:30
栗田 祐里
【11・12月課題図書】
今は知らない人がいないユニクロも進んだり後退したりしながら進んでいる事、なかなかのボリュームでしたが柳井氏の奮闘する姿に先が気になり読み進めていました。
現実の延長戦上にゴールを置かず、未来の目標に対して計画・行動してるところがなすの斎場っぽかったと思います。またユニクロとはなにか、ユニクロ服とはなにか、と解いているのが、不安ゼロのお葬式とは?ミスティクとは?と3秒ブランディングを目標にしているまさに今のなすの斎場にリンクするところがあると感じました。そしてその問いは経営陣だけでなく全社員が体現できるように落とし込んでいました。やはりこのユニクロとはなにか?ユニクロの服とはないか?と末端までと考えることが浸透し、考えることを止めていない。浸透する人材育成こそが成功の鍵なのかもしれない。
そして日頃お世話になってるユニクロの印象がいい意味で変わりました。店舗に行った時にいろいろ観察してしまいそうです。
田村風音
単なる柳井氏の自伝ではなく、ユニクロの歴史を創業期から現在までをじっくり紐解いておりユニクロは失敗と成功の繰り返しだというのが分かりました。しかし柳井氏の視野の広さと諦めない心がすごいなと。
私が読んで印象的だったのは「Be daring,Be first,Be different」の言葉です。ライバルが多くいる中でおもてなしや洋服作り等、他とまったく同じではつまらない。柳井氏が紳士服店から倉庫のようなカジュアルウェア店に転換してフリースを看板商品にして世界に進出していく姿はこの言葉ありきだなと思いました。
柚木陽介
課題図書 ユニクロ
この本は今までのビジネス書からは一風変わった、壮大な映画や物語のような本であった。皆さん、当然ユニクロはご存じの通りですし、今の現状も分かっている、例えるならば古畑任三郎や、刑事コロンボのような、分かった上で、その過程を楽しむ物語なんですよね。その過程がとにかく面白い。そして学びのエピソードが多すぎて、逆に学べない量、情報量のシャワー。もったいないので、この本は3冊位にまとめたり、映像化して欲しい物でした。個人的にはユニクロの本でしたが、その中で出てきたZARAの所が凄く印象に残っております。メディアや流行の縮図のようなものを垣間見る事が出来ました。とても面白かったです。
宮内 佐知江
11・12月課題図書
ユニクロの柳井氏と言えば日本長者番付に名がランクインされているというイメージが強く、柳井さんの人となりまでは知りらずこの本はご本人が書いた自伝本ではないですが柳井さんが今のユニクロを作り上げた舞台裏、エピソードを知る機会が出来とても面白く読めました。
読書好きの柳井さんが実業家たちの著書ビジネス本からヒントを得て自身の経営に大きく関わっていることは意外でした。ノートに自己分析を書いてできないことはしない、できることを優先順位をつけてやることはとても共感出来た部分でいくら悩んでもできないこと、よく考えれば悩むことまでなくできるかもしれないこと、とってもシンプルですが悩んでる時間はもったいない、できそうなことから順番に片付けていけばいずれトンネルの出口が見えてるくるはずだという柳井さんの思考法はその通りだと感じ、また政治に距離を置いてる柳井さんにも共鳴できました。柳井氏は世間的には家が商売やってるボンボンで苦労知らずのように感じますが決して全てが順調に進んで今に至る訳ではなく父子の関係性も一般家庭みたいな関係性ではなく我慢してきたことも沢山あったからこそ反骨精神の強さと意地でここまで大きなアパレル会社を作れる経営者になれたのかと偉大さを改めて感じ取ることができる本でした。
高橋 真人
11-12月課題図書
ユニクロの成長、もとい柳井正さんの歩んできた道は、決して順調満帆なものではなかったのだというのが最初ん印象でした。
不遇の時代、特に季節ごとのセールのお話は読んでいて自分も胃袋が痛くなるような感覚で読んでいました。
うちに活かせることは何だろう?という視点で読んでいましたが、ほかの方も書いているようにゴールを考えてそこへどうすればたどり着けるかを必死に考えていく姿がとても印象的で良いなと感じました。
またフリースがブレイクして「安っぽい」というイメージがついてしまった後のそれをどのように払拭していったかという手法も、ブランドイメージづくりや学べる部分が大きかったと思います。
会館を管理するようになれば、必ず良い時もあれば悪い時もあると思います。悪い時に何をしていけるか、気持ちとしてどう向き合っていくかを柳井さんに教えてもらったような気がしました。
渡邊勇二
11、12月課題図書
「そもそも新しいことをやると失敗するものなのです」この言葉に少し気が楽になりました。失敗から何を得るかが大切。その通りだと思います。失敗しそこから学び、改善することで成功が得られる、仕事の活力になりました。
安いでおなじみになり、フリースがヒットしても成功に思えてもそれがマイナス面にはたらいた時のブランドの切り替え手法もすごいと思いました。なかなか値上げをして成功する事例はないなかで、新たなブランドイメージの構築までが早かったと思いました。山﨑まさよし、ジョーダンバージョンのCMを見てみました。たまたま見た最近のCMも全く別物でした。その時々に合わせたメッセージの違いが見えました。
自身の最終のゴール設定をすることも今何をやらないといけないかを明確にすることだと感じましたので、最終のゴールを決めて逆算して今が客観的にみえるようにしていきたいと思いました。
大髙紅葉
11、12月課題図書
自分の物心ついた時からすでにたくさんの人から支持をされていたユニクロがこんなにも色々な困難や失敗を繰り返していたことに驚きました。成長と停滞の過程が非常に読みやすく書かれていて面白かったです。何にでも、とにかくチャレンジをする気持ちと失敗を恐れないことが大事なのだと勉強になりました。
自分も現状に満足することなく常に向上心を持って様々なことに挑戦していきたいと思いました。
瀧田 博志
11月、12月課題図書
まず、私はユニクロの「ユニバーサルデザイン」に感銘を受けました。誰もが着やすい服を提供するという理念は、多くの人に支持される理由だと思います。さらに、コストパフォーマンスの高い衣服を展開することで、ファッションの敷居を下げ、より多くの人々にファッションを楽しむ機会を与えています。
また、ユニクロがどのようにしてグローバルに成功を収めたのか、その戦略やマーケティングの手法も学ぶことができました。特に、現地のニーズをしっかりと把握して商品を展開する姿勢は、なすの斎場とってもにも参考になると思いました。柳井氏の考え方や戦略には賛否もあるかもしれませんが、彼のビジョンは非常に明確で、社員や顧客に対する思いやりが感じられました。
五十嵐美紀
ユニクロがここまで来た道のりや数々の失敗との向き合い方、柳井さんの社員との向き合い方など多くのことが参考・勉強になりとても楽しく読み進めることが出来ました。
読み進めていく中で、ただ行う葬儀ではなく当家様が望んでいるものを提案・提供することの大切さなど、葬儀という仕事に当てはまることが多くあり改めて考えることもできました。
勉強になることが多くあったので、今後も読み返して復習していきたいと思います。
藤田 勝文
11-12月課題図書
規模も業種も違いますが「変化を好み成長が喜びである」私達にとって重要なエッセンスを、一本の映画を見ている中で感じることが出来る素敵な本だと感じました。小さな点や大きな点が実は点ではなく一本の線になっている納得感と、サクセスストーリーでありながら、泥臭く残酷なことも誠実に描かれていて、読み終えた時は超ロングバージョンのジェットスターを楽しんだような感覚でした。討論会でもテーマにしましたが、澤田氏の伝説のフリース戦略がジョギング途中のトイレに用足しに向かっている中でアイディアが降ってきたとかろが痛快であり、常にアンテナを張り続けることの重要性を再認識しました。これはまさに「言うは易し、行うは難し」です。作中に何度も引用されている言葉に、その都度自問自答の時間になりました。全然行動量が足りない!と反省する中で、ネットサーフィンを始める私。これが現状だと。常に現状を打破し突き進むための原動力は目的だと。「言うは易し、行うは難し」です。間違いなく、ここから3年。私の背を推し続ける本書との出会いに心から感謝します。私は泳ぎ続け、とびきりのスイマーになります!!
平山 智美
11.12月課題図書
ユニクロを当たり前のように身近に感じていますが、「新しいことをやると失敗するもの。でも、失敗することは問題じゃない。失敗から何を得るか」という柳井氏の言葉。新しいこと…実行しているか?失敗したのか?失敗したなら自分は何を得たのか?
そして、本からたくさん学んで、自分を常に変化させていき考え方や行動を変えていく。いろいろな本を読んで思うが行動して学びを得る。学びをとめてはいけないと思いました。
福田巧
11,12月課題図書 ユニクロ
解なき問いと向き合い続けた10年~寝太郎から世界的な企業への悪戦苦闘。暗黒の10年間など小郡商事という小さな小売り業からユニクロヘ。父親から小郡商事を全面的に任され、時代が変わっても店を潰さないための決意・・・が決してあったわけではないような。ジャスコ、ダイエー、果ては海外まで外にヒントを求め続けた結果が今に繋がっている部分もあり、時代の背景もあり。本を読んでそういえば野菜売るって言ってたけど、やっぱり失敗だったのかと謎が解けた部分もありました。
ありがちな部分ではありますが、自伝的な部分が濃く寝太郎だった柳井さんが次世代にどうつなげていくのか、そこをもう少し読んでみたかった気がします。またユニクロといえばフリース世代の私には懐かしいフレーズもありつつ、いつの間にか値段も手ごろではなくなり、進化の果てはどこなのか気になります。
竹田美奈子
読書感想文
杉本貴司の『ユニクロ思考と戦略』は、ユニクロがどのようにして成功したのか、その背後にある考え方や戦略を解説した本でした。著者はユニクロでマーケティングに長く携わってきた経験を持ち、ユニクロの成長の秘密やリーダーシップ、商品企画やマーケティングの工夫について具体的な例を交えて紹介しています。ユニクロの成功がしっかりとした計画や戦略に基づいていることがよくわかる内容でしたが、私個人として経営者としての立場ではなく、いち主婦 女性目線として、UNIQLOの製品はとても素晴らしいと思う反面、子供達が年頃になると、UNIQLOだとバレる軽いやだと何度も言われた事がありました。
難しいです。
村上絢美
11.12月読書感想文【ユニクロ】
ユニクロが世界的な企業へと成長は独自の経営哲学と飽くなき挑戦の姿勢があることを学びました。「変化こそ成長であり、現状維持は衰退である」という言葉が特に印象的で、日々の生活や仕事においても、現状に満足せず挑戦を続けることの大切さを感じました。
そして、「失敗を恐れない」姿勢も心に残りました。失敗を糧に次の成功へのステップを見出すという考え方は、自分の行動を前向きに捉えるヒントになると感じました。
言葉や経験を通じて、挑戦すること、そして人として成長し続けることの重要性を再認識できたような気がします。
屋代 実沙紀
11月~12月課題図書 ユニクロ
この手の本には珍しく、登場人物の紹介があったので人物や人間関係についても頭に入りやすかったです。
誰もが知っていような大企業ですが、決して順調な道のりではなく今のユニクロに成長するまでには様々な挑戦や失敗があったのだと知りました。失敗を忌避したり対策することばかり考えるのではなく、試しに挑戦して失敗してみるのも(限度はありますが)良いのかな、と思いました。
フリースのくだりでは、そういば子供の頃冬に買ってもらうのを楽しみにしていたな、と思い出し懐かしくなりました。フリースの誕生にも社員のひらめきがあったんだと裏側もわかり興味深かったです。
寺門 大輔
【11-12月課題図書】ユニクロ
小さな小売り業態から世界的な企業へ成長する中で、超人的な人材の活躍や突飛なサクセスストーリーだけでなく、泥臭く悪戦苦闘の末、文字通りのし上がっていった様子を学ぶことができました
その中で特に印象的だったのが、「泳げないものは溺れればいい」という、非情的な一面もありつつ、それでも真摯に「変化を好み、成長が喜びである」点が企業を成長へと導いた場面でした
古くから会社を支えた古株社員が退社していく中、それでも新要素を取り入れ続けたことで地方の一企業から全国的、世界的な企業へとなりあがっていった点が、三誠のバリューに重なるような印象を受けました
現状維持はゆるやかな衰退、という言葉はありますが、「失敗を恐れない」姿勢と未知へのチャレンジ、それに向けての人材育成など、学ぶ点が多い書籍でした
大金久美子
【11-12月課題図書】ユニクロ
日本で当たり前に知っているブランドが、大きくなる過程や、「シンプルで高品質な商品を手ごろな価格で提供する」というユニクロの基本理念が、なぜ私達消費者に受け入れられるかがわかった。
ユニクロの成長には、ただの良い商品や価格だけでなく、企業としての強いビジョンがあり、環境への配慮や社会貢献活動にも力を入れているので、単なる売上アップだけでなく企業としての社会へのな役割も考えている企業であること。
失敗9割の様に、ユニクロの成功の中でたくさんの失敗をどう乗り越えてきたのかがわかった。成功には必ず失敗がついてくるという現実を受け入れ、その中から学び、次に生かしていくことの重要性を学びました。
小さなお店から日本中、世界中に展開していったユニクロが更に身近に感じられました。
相馬 奈津美
11、12月課題図書
ユニクロがどうやって大きくなっていったのかがわかる本でした。いろんな考え方があってとても勉強になりました。失敗をしても理由を考え抜いて次の成功はの気づきにかえるところ、そして、マニュアルが全てではなく、あくまでも現場の従業員がたちかえる原理原則にすぎないこと。仕事の効率化のためにいろいろなマニュアルがあったら良いなと思っていましたが、マニュアルだけではダメな事に気付きました。この本を読んで学んだことを1つでも身につけて仕事に活かせるようにしたいです。
丸山日花
【ユニクロ】
誰もが一度は耳にしたことのある企業、小さい頃から知っていた大企業の創設者は実は昔から天才という訳ではなくパッとしない青年だったことにまずは驚きました。多くの失敗や挫折を乗り越えてユニクロができたんだと。重要なのは失敗しない事ではなく、失敗から何を得たのかということ。失敗を乗り越えた先に成功があるということをこの本から読み取れました。成功談よりも失敗談の方が印象に残りますが、成功をしても努力を続けるモチベーションの高さを維持できるのがすごいと感じました。
薄井美咲
11月、12月課題図書
「ユニクロ」という誰もが聞いたことがある企業だったので興味を持ちながら読むことができました。ユニクロがどのようにして大きくなったのかが、わかりやすく書かれておりとても勉強になりました。「もっとユニクロにする」というが一番印象に残りました。差別化。この言葉がいつも耳にしている言葉でユニクロと同じだ!と心に残りました。陳列の仕方でたとえ無駄だとわかっていても差別化の為にやる、というところが感心しました。なすの斎場も圧倒的差別化として事前相談勉強会でもやっているお客様のお見送りやパネルの説明など、お客様にもっとなすの斎場らしさを知っていただけるようにしていきたいと思いました。
他にも失敗は恐れずにもっと自分が成長できるようにたくさんなことに挑戦していきたいと思います。
遠藤 来夏
11、12月課題図書
「ユニクロとは何か」は「つむぎのお見送りとは何か」に通じると思いました。
一般的なお見送りが出来ることは大前提ですが、そこにつむぎらしさがある事が選んでもらえる軸になると思いました。
そして現状に満足せずに自問自答を続ける事。
失敗をしても理由を考えて成功に繋げる事。
心に留めておきたいです。
1回だけでは流れてしまいそうなので、ちょっとずつ読み返します。
谷口 綺沙
11、12月課題図書
成功者になるまでに様々な失敗をしてきた創設者。
その失敗を乗り越え今や大企業であるユニクロが誕生し、発展しつづけている。失敗をおそれず、改善し高みを目指す姿勢は見習わなければならないなと思った。人びとが見出すニーズに応えながら、他とは違う何かを追求することはなすの斎場の葬儀に通ずるところがあると思う。
竹中紗智
11・12月課題図書
様々な経営者の方から尊敬する方は柳井さんと伺ったことがあり、どんなことをされた方なんだろうと、そしてどんな取り組み・マインドでされてる方なんだろうと思いながら読みました。様々なサクセスストーリーを経て、失敗を前提として前進され、それを糧として粘り強く全社員が体現できるところまで落とし込んでいく『とにかく伝える』その精神はブレないマインドが無ければ出来ない事だと思います。描くビジョンが明確であること、そして少し変更しても「どうやったらたどり着けるか」を動きながら考えていくスタイル、すぐやる人にも共通する点と感じます。継承された事業の中、どこか弊社にも共通する『らしさ』。同じ業界でどう戦っていくか、学ぶことができました。
馬渡 良平
11,12課題図書
ユニクロという会社は知っていても実態は全く知りませんでした。なんとなく海外の企業のイメージもありました。
その創業者が怠惰な若者で一代で大企業になるとは夢のあるお話ですね。
もちろん現実のお話であり失敗に失敗を重ねながら躍進していく姿はやはり世界企業だと思いました。
ユニクロはいまでも中国との問題で話題になりますがそのような困難でもこれまでのように乗り越えていく力を持っていることがこの本を読んで改めて感じました。
髙久樹羅
遅くなってすみません。
11.12月 課題図書
ユニクロという誰もが知る企業がどういう道のりで、世界的企業になったのか分かりやすくまとめられていました。
失敗した原因を考え抜いて、次の成功へ繋げる、行動することが大事だなと思いました。
自分も創設者である柳井氏を見習って、頑張っていきたいと思います。
菅俣悠馬
遅くなり、申し訳ございません。
ユニクロの成長の過程や、失敗を恐れず改善を続ける姿勢から多くの学びを得ました。創業者の挑戦する姿勢や、人々のニーズに応えながら独自の価値を追求する考え方は、葬儀の仕事にも通じるものであり、当家様が本当に望むものを提案・提供する大切さを改めて実感しました。
今回得た学びを日々の業務に活かし、より良いサービスを提供していきたいと思います。また、何度も読み返して復習し、自身の成長に繋げていきたいです。